| 宗教真理アカデミー |
| メールマガジン015号 |
| 菜食問題について |
<宗教真理アカデミー>(2006.4.16.配信) 【メルマガ第15号】 タイトル 「菜食問題について」 〜〜〜(副題)肉食厳禁の戒を破るとどうなるか?〜〜〜
▼肉食は罪なのか? 宗教においては、「菜食か肉食か」という論点があります。 ユダヤ教では「ユダヤ教聖書」に「これは食べてよい、これは食べちゃ駄目」という詳細多岐の項目があります。そのために、宗教生活が戒律でがんじがらめになって身動きがとれないような「窒息的ストレス」を信徒が感じるようになり、ユダヤ人の中に「ユダヤ教なんて嫌だ」という風潮も当時あったように思います。 そこで、ユダヤ教のがんじがらめ戒律主義のアンチテーゼとして勃興したキリスト教では、 「何を食すべきか」という議論の末、「信仰をもって神に感謝し讃美して戴く食物は、すべて清い」 という見解に大体のところ、落ち着きました。 勿論、「血を避けるべき」などの若干の注記はありましたが。 その点に関連して、キリスト教の一派「エホバの証人」の信徒が、輸血拒否事件で世間を騒がせたことを記憶している人は多いでしょう。 これは「輸血は血を食すのと同義だから駄目」という解釈のゆえの行動だったと思います。 輸血すると天国に行けなくなるから、輸血は絶対駄目、という解釈です。 しかし、一般のキリスト教宗派では、輸血を禁じてはいないし、輸血したら即天国に行けなくなる、と解釈することもありません。 (但し、輸血肯定論であっても、ウイルス汚染血液かどうかなどの問題は別個論じられるべきです) 戒律の厳しいユダヤ教であっても、肉食全面禁止ではありません。 「宗教的に適切に処理された牛肉」は食すことができます。これは「清い肉」とされます。 ハンバーガーショップのマクドナルドがユダヤ系であることは有名ですね。 (但し、日本法人の代表だった藤田田社長は、その名の由来が「口に十字架」で「田(デン)」ということで、ユダヤの商人でありながらクリスチャンだったのでしょう、豚肉の?ソーセージ・マフィンなども導入しましたが、当時、この試みは世界的には恐らく日本だけではないかと思います。) 一方、ユダヤ・イスラム教では、「豚」という動物それ自体をけがれた動物と見ると解釈すべきなのか、聖書には、「豚肉」はけがれたものであり、これを食する人は、汚らわしい人間だ、ということになります。 ゆえに、「豚野郎」はひどい侮辱の言葉になります。 こうした「豚肉忌避」については、ユダヤ教教義を引き継ぐイスラム教において特に顕著で、 豚肉を食べさせようとしたならば、「お前を殺すぞ!」というぐらいに激怒されることもあると覚悟すべきです。 なぜなら、イスラム教における天国は、煩悩熾烈な凡夫俗人にとって垂涎ものの、酒池肉林的なパラダイスなので、 (この点については、永井俊哉氏の書評「コーラン」の「第二節 コーランに描かれている天国と地獄」 参照のこと) くだらない豚肉を食べたばっかりに、こうした来世の「天国行き快楽三昧」というご褒美が「パァ〜」になってしまったら、それこそ大変、「永遠の大損だ、ふざけるな!」 という大激怒ものになるからです。 しかし、沖縄県では豚肉料理で健康長寿と言われていますので、「豚=けがれ=地獄行き」と言われても、沖縄県人の多くはピンと来ないでしょう。 日本人も、日本国内には、おいしい「とんかつ屋さん」が沢山あるので、ここで食すると地獄行き、とんかつ屋の調理者も地獄行き、と言われると、 「なんだ、その教えは!」 という反発を招くのではないでしょうか? 蛸(たこ)については、ユダヤ教・イスラム教で「けがれたもの」に分類されます。 ゆえに、蛸を取る漁師も地獄行き、たこ焼き食べる人々も地獄行き、ということになりますか・・・。困ったものですね。 同じユダヤ教でも、「厳格派から寛容派」まで、幅がありますが、エビ・カニなどは、厳格派は駄目ですが、寛容派ではオマールエビに舌鼓ということも可能のようです。 さて、ある人から、私のところに、米国の屠殺場の屠殺現場をネット公開しているアドレスを知らされたので見ましたところ、牛をひどい虐待をしながら残虐に殺して行く光景が映っており、まさに地獄絵図でした。 こうしたことを平気でやる一部のアメリカ人の「暴力性」は恐ろしいものです。このショッキングなシーンをみせて、一つの政治運動キャンペーンメッセージを流します。 「あなたはこうした牛たちを助けるために何ができますか? 牛たちを助けよう! 肉食反対」 そして、このメッセージに共感する人は、菜食になり、牛肉不買運動に参加したりします。 ユダヤ教で、牛を屠殺する場合、「宗教的に適切に処理した清い肉とする」ためには、 できる限り虐待せず苦痛を最小限、または無痛で屠殺する技術を用いる、という方向性になります。屠殺はすれども「苦」を与えない、ということが課題なのです。そこに人智を尽くすのです。 鶏肉の場合も同様です。 ユダヤ教では「宗教的規律に従った正しい屠殺」の業は許可制であるがゆえに、その業者は自分の仕事に誇りをもっている、ということです。見てはいませんが、恐らく、感謝を捧げる厳粛な儀式的な場、といった感じではないでしょうか。 ゆえに、これとの比較で、一つの社会問題が指摘できます。 産業廃棄物処理業や屠殺業などは、人の嫌がるけがれた業種と見られ、昔で言えば「穢多・非人(エタ・ヒニン)」にやってもらっていたもの、というような「社会的差別意識」があるのではないでしょうか。 このような、誰も手を出したがらない業種であるため、ヤクザや最下層の人々がそれをやるようになり、「ひどい形の業務遂行実態」を許容する社会となります。 上記のアメリカとひどい屠殺場も、恐らく、社会最下層の、社会に怨念を持つ人々が、その怨念を牛を対象にして残酷な屠殺行為で鬱憤晴らしをしている、というような構図があるように思います。 そして、人々はそれを見て見ぬふりをして、目をつぶるのです。「しょうがない」と。 けれども、屠殺業や産業廃棄物処理業などなどを「一つのちゃんとした職業だ」と社会的に認め、業種を許可制などにして、参入に条件をつけ品質管理基準も設け、業者選別をしたり、労賃対価も充分なものに設定すれば、「しっかりとした業態」にすることは可能です。 つまり、この問題は、「社会の差別意識」や「ローコスト最優先の道徳なき市場主義」と不可分の問題だと言えるのではないでしょうか。 さて、話を元に戻します。 釈尊仏陀が大悟の前にスジャータからもらったのは、牛乳粥でした。 修行僧ゴータマは、それまで厳しい苦行の一つとして肉食忌避をしていましたし、時に応じて断食も行っていたようで、この時、瀕死の状態だったと言われます。 牛乳は、動物性ですから、厳格な菜食の立場からすると、忌避すべきものです。 しかし、修行僧ゴータマは瞬時の判断で、これを受けるのが正しいと感じ、食しました。 以降、中道のバランスということに気付きを得て、大悟に一直線となります。 こうした恵み豊かな牛乳ですが、 現代の「ロー・コスト最優先」の大量生産現場においては、雌牛をたえず妊娠出産状態にして乳が出るようにして、それを搾乳機で吸い取り搾り取ります。アルプスの少女ハイジが羊の乳を手で搾るがごとき、昔の牧歌的な光景とは全く違います。 それはそれは、「ひどい雌牛虐待」に通じる無惨な光景と言えましょう。 「こんな現場はひどい!こんな牛乳飲むものか! 牛乳買うな、豆乳を買おう!」 これは、政治運動の一つとしては宜しいでしょう。 しかし、「牛乳=悪」という構図にすり替えられてしまう危険があるので、この点、峻別して認識すべきです。 「昔ながらの手絞りの牧場産の牛乳を飲みましょう」 ということなら、牛乳を飲むのが、即、悪とは言えないでしょう。 牛乳、ヨーグルトやチーズは動物性です。しかし、聖者シュリ・チンモイはこれを自ら食していたと思います。 (間違いがあれば、指摘して下さい。) 但し、牛乳に関しては、新谷弘美教授(米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授)が、次のような指摘をしています。(以下、内容要約) 酪農家が牛から搾乳したものは大きなタンクに入れられ、ホモゲナイザーで攪拌して乳脂肪を均一化する作業をするのですが、このとき、生乳の脂質が酸素と結びついて「過酸化脂質」に変化して、酸化してしまうこと。 そして、生乳に含まれるエンザイムは熱に弱く高温殺菌だと完全に破壊されてしまうこと。高温殺菌では過酸化脂質もさらに増えてしまうこと。 以上の加工により、市販の牛乳は、健康を阻害する食物に変質してしまっているのだ、と。 (『病気にならない生き方』新谷弘美著 サンマーク出版 106〜111頁) (ウェブでのこの本の紹介はこちら) さて、シュリ・チンモイやサティア・サイババ、その他のインドの偉大なヨーギは、皆、口を揃えて、 「菜食をすべきである」 と教えます。 菜食の方がよいことは、論を待ちません。 上記の新谷健康法でも、「人間より体温の高い動物の肉はそれを食する人間の血を汚す、なぜなら、牛・豚・鳥の体温は38.5〜40度、鶏の体温は41.5度、この平常体温でこの動物の脂は安定するので、この温度よりも低い人間の身体に入ると、ベタッと固まってしまい血液をドロドロにする要素となるからだ」 と言われます。(上記書籍115頁) 新谷健康法では、(白米ではない五穀米や十六穀米などがよいようですが)穀物と野菜中心の食事にして、動物性食物は全体の15パーセント程度にするのが理想だと言います。 このように、現代の科学的・医学的な「正しい食生活」の観点からも、 肉食は健康を損なう要素を多分に持っていることが判明しつつあります。 但し、こうした科学的裏付けが証明されつつあることに力を得つつ、なによりも、 「菜食は絶対的な宗教戒律だ」 ということで、極端に走り、原理主義的・狂信的な形で、 「絶対、絶対、厳格な菜食こそ!」とまで言い始めるならば、 「待て待て、それはちょっと違うぞ」というような、 間違った、偏った方向性へと暴走して行くことになります。 わかりますでしょうか? これは、外面的・形式的な、「戒律厳守行為重視派か」、それとも、 「内心の信仰の炎重視派か」 という問題に関わる問題です。 キリスト教では、ユダヤ教の「外面的・形式的な戒律主義」の悪弊を除去するために、 そのアンチテーゼとして、 「内心の信仰の炎重視」の教義になっています。 シュリ・チンモイは公式サイトにて、 ベジタリアンが悟れるならば、南インドの人々の大半は菜食なのだから、みんな悟ってしまうだろう。 けれど、実際は皆悟ってはいないだろう? このように、菜食は、重要なファクターであっても、あくまでも補助的ファクターであって、主要なファクターではないのだよ。 悟りに到るための主要なファクターは、あくまでも、 「渇仰心(かつぎょうしん)=菩提心=アスピレーション」 である、と述べています。 ▼正しい判断のための「渇仰心」第一主義 シュリ・チンモイは、魚肉は鈍重な波動をもっているので、渇仰心がその鈍重な波動に引っ張られて弱められる点がある、と言います。しかし、強い渇仰心があれば、魚肉の霊的鈍重さに勝つこともできるので、大した問題にはなりません。 つまり、ここにも、霊的な法則 「肉欲と御霊(みたま)との綱引きの法則」 が働いています。 肉の場合、屠殺された状況により、長時間継続的に、残虐虐待を加えられて殺された牛の肉には、怨念波動が血液を通して入っているため、修行者の渇仰心が、憎悪の方向に引っ張られ、破壊されるので、このような肉はけがれているものとして食するべきではない、と、シュリ・チンモイは教えていたと記憶しています。 (一種のサイコメトリです。食した肉の履歴が精神にパッと入って来るのです。) ですから、やはり、魚肉同様、牛肉・豚肉・鶏肉の場合にも、渇仰心との関係性の中で、 それが弱められ、修行を妨げるのかどうか、という視点が大切です。 「一かけらの肉を食したら、即、地獄行き決定!」−−このような過剰反応、そして(実質的視点を欠く)形式のみからの判断は、中道のそれではありません。 大聖者イエズス・キリストは慈悲の模範として、魚肉は弟子たちと共に食しました。 ワインという酒も少々飲みました。 それらが、分量的に渇仰心を妨げるほどにならない場合、かえって、良い作用をもたらすこともあることが、ワインの使用法などから、推察されます。 シュリ・チンモイは、真っ白の小犬を飼っていますが、小犬には肉を買って与えている、ということです。 厳格な原理主義的菜食主義者の、「肉不買運動」の見地から言えば、肉屋の生活を支援する行動としての、飼い犬に与える肉の購入すら、肯定されるべきではありませんが、シュリ・チンモイの場合、それは全く問題にしていないようです。 シュリ・チンモイが、陸上競技の不世出の大選手カール・ルイスの精神的支柱として、弟子カールを支えたのは有名ですし、シュリ・チンモイは、常々カール・ルイスを絶賛し、彼に多くの楽曲やコンサートを捧げています。 そのカール・ルイスは、菜食だったのか、というと、どうやらそうではなかったらしいです。チキンは食べていたという話を聞きました。(どなたか正確な情報があればお教え下さい。) 部派仏教の一つ、法蔵部が所有していた戒律集『四分律(しぶんりつ)』 (この「四分律」は後代の「律宗」に引き継がれた)には 「三種の浄肉あり。 まさに食すべし。もし、(1)ことさらに見ず、(2)ことさらに聞かず、(3)ことさらに疑わざるものは、まさに食すべし」(中村元博士訳。決定版撰集第21巻347頁) とあります。 原始仏教時代とそれに続く部派仏教時代、出家仏教僧侶は乞食・物乞いで食を保っていたため、 「もらったものは何でも食す」という原則の中で、肉の混入ケースがあるわけで、これが殺生戒に触れるならマズイので、三種類の抜け道ケースを設けたわけです。 (1)殺すところを見なかった肉は、もらって食べても良い。 (2)仏法僧への捧げ物として殺されたとは聞かなかった肉は、もらって食べても良い。 (3)もらう自分のために殺された疑いのない肉は、もらって食べても良い。 ここに見られる態度は、「何でも感謝して食すならば清い」という、「内心の渇仰心重視」のキリスト教的立場に似ています。 ちなみに、ゴータマ仏陀が死ぬ時、チュンダの家でもてなしの食事を出され、これを食して激しい病に侵され死亡したと伝承されていますが、この時に出された食事、パーリ語で「スーカラ・マダヴァ」が何だったのか諸説あるということです。一説には、「毒きのこ」であったとか、また、一説には、 「野豚の肉の煮込み」だった、という候補も挙げられています。」(中村元著 決定版撰集第21巻347頁) 果たして、ゴータマ仏陀が最後に食したのが、豚肉だったのか否か? 興味は尽きませんね。(誰かシュリ・チンモイかサティア・サイババに尋ねて下さい。笑) ただ、仏陀が大慈悲で、信徒から出された食事を 好き嫌い言わずに口にした、ということだけは言える、と思います。 しかし、後代の大乗仏教時代になると、『ランカーヴァターラ経』などで、「肉食厳禁」の態度が鮮明になって行きます。仏教の精進料理はこの思想の流れの中にあります。 政治的不買運動により、屠殺業を廃業に追い込み、慈悲にみちた社会を築こう、という目的のための菜食は、純然たる修道者の菜食ではなく、政治運動家の菜食と言えます。 「いや、生きとし生けるものへの慈悲心を養うためにも、不殺生の菜食は必要」 という主張に対しては、(無論、ここに一理はあるものの) スワミ・ヴィヴェーカーナンダは、「不殺生・不殺生というけれど、あなたが呼吸している時にも、無数の細菌・バクテリアなどを吸い込み殺しているではないか、植物だって生物ではないか」 というような(括弧内は要旨であり言葉づらは正確ではありませんが) 激烈な言い方で、「気付き」を促したこともあります。 こうした論法で彼は−−−「形式主義者の偽善」−−−を指摘しているのです。 「自分は蟻一匹殺していないよ、私は常に正しいし、自分には罪がない」そして、ハッハッハッ、との高笑い。 「おお、私の正しさを神に感謝、ハッハッハ。」 このような、形式的戒律厳守主義者が往々にして陥りやすい、 「自分の善良行動を誇る偽善」を 正しい宗教と霊性修行の道は、ひどく嫌うのです。 再度強調しましょう。 「自分の善良行動を誇る偽善」を 正しい宗教と霊性修行の道は、ひどく嫌うのです! このことは、ユダヤ教聖書の『ヨブ記』をみてもよくわかるでしょう。 つまり、神からみて、このような人は、「義人(正しい人)」ではないのです。 以上をまとめます。 渇仰心を妨げる要素の食物は避けた方が宜しい。 しかし、渇仰心を強める意識的努力と瞑想行などにより、 渇仰心の喚起たるインボケーションを強めることも可能なので、そうやって「渇仰心を補填」するならば、 若干の「肉食による悪影響」は、修行上、どうという問題ではない、とも言えることになります。 ただ、感覚が鋭敏になるほど、自然に肉食はいやになって行く、ということはあります。 |
|
| |
▼渇仰心第一主義の応用の一例 シュリ・チンモイは、たとえば、「弟子たちよ、やめた弟子(やめ弟子)とはつきあうな」と法令を出しました。 これは最初からのことではなく、何十年も教えていて、ある時、女性弟子が、やめた男弟子に引っ張られて、弟子の生活をやめて結婚して去って行ったことがきっかけだと、と言われます。(正確な情報があれば提供お願いします) つまり、霊性修行をしていない肉欲が強い人と接触することで、渇仰心が弱められ破壊され、肉欲方向で引っ張られて、霊性修行生活をやめてしまう、というケースの発生を最小限に止めるために、 「やめ弟子とは、つきあうな」 という、実に「大雑把な」法令を出したわけです。 ところが、形式的・原理主義的な弟子たちの中には、 自分の外部の人間はすべて、肉欲生活の人々だから接触しない方がよい、とか、 やめた弟子はすべて悪魔の仕業で堕落させられているから接触するのは大罪だ、 というような、極端な解釈をする者があらわれて、 小乗的な保身の殻に閉じこもってしまう事態を招くようになりました。 こんにちの日本東京センターもその例外ではないように思われます。 情けなくも、嘆かわしい、幼稚なレベルの話です。 これは彼らの「高慢心」から来る解釈で、「自分たち“だけ”が弟子として高邁な道を歩んでいる」という暗黒の自負心がその背景に蠢いているのです。 確かに、お子さまを保護するには、外出を制限し、友達を制限する方法が安全です。 「お子さま扱いが嬉しい」人には、それでよいのでしょう。 しかし、力ある大乗的な弟子は、そのようであるべきではありません。 人々に引き寄せられるのではなく、力強く人々を引き寄せる「引手」にならねばならないのです。 また、やめた弟子のすべてが渇仰心を捨てたわけではないですし、中には、シュリ・チンモイの弟子よりも強く高い渇仰心をもって生活している人すらいるのです。 こうした人を「識別」できるだけの大人の能力があれば、上記の法令から自由でいることができます。 形式主義者は、「やめ弟子とつきあうな」というグルの教えを絶対化します。 しかし、実質重視主義者は、この命令の「発令趣旨」にまで遡って考えます。 発令趣旨が「渇仰心の破壊の危険性を避けるため」であるならば、渇仰心がかえって強められるような交流であれば、「やめ弟子とも可能」という結論が導き出されます。 これが「渇仰心第一主義」です。 形式よりも内実を重視する立場です。 形式重視(のスタンス)は、お子さま用です。 内容重視(のスタンス)は、大人用です。 菜食問題についても、全く同様のことが言えます。 原理主義的な、狂信的な、「絶対〜」という偏向した強い言辞の力に 惑わされたり流されたりすることなく、 安直・硬直的な形式主義を、 断固とした確信に満ちた、実生活に即した実用的な「内実重視主義」で押し返し、 叡智ある中道を 思慮深く、冷静に選択して行く「センス」を磨くことができますように、 心から祈念しております。 以上、長くなりましたので、この辺に致します。 それでは、皆様の上に主の恵みが豊かに注がれますように。 また、豊受大御神(トヨウケノオオミカミ)の如く、主の恵みを豊かに受け取ることができる器となることができますように。そして、大日の恵みを受けて、豊饒なる実りを成して、それに喜び感謝しつつ、人格とカルマを成熟させて行くことができますように。 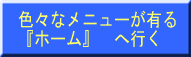 著作権について
|