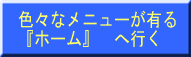|
���\�O�́@�u���@���̔ʎ�|�K�̗�q�ϖ@�v�i��Z�i�K�j
�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�u�������v���o�̖@���ʉ߂���@�`�`�`
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�j
�y��Z�i�K�z�@�u�������v���o�̖@���ʉ߂���
�@�u�������W���v������������ł���i�^�|�P�O�|�P�U�ȉ��j�B�������A���̖��ʂ����ŏI���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�C�s�҂̍s����ɂ́A�X�ɋ����傪�҂��\���Ă���B���̋����傱�����A������́u�{��v�A�����u�������v���o�̖@��ł���B�i�u�����E�������v�T�O�̊T���́A�^�|�P�T�|�Q�W�A�Q�X�A�S�U�B�u�����v�v���ڐ��ł́A��|�Q�|�Q�O�j
�@�u�������̎��o�v�Ƃ́|�|�|���u��ɂ͎����������v�Ƃ̐��������o�������Ɓ��|�|�|�ł���B�k�����P�l�B
�k�����P�|�|�|�ܘ_�A�����ȁu�������̎��o�v�ɂ́A�u�l����v�̑��Ɂu�@����v���܂߂�͓̂��R�ł���i�^�|�P�T�|�T�T�ȉ��j�B�������A����ɂ����ẮA�Ȋw�i�����w�E�ʎq�͊w�E���w���X�j�̕���̋Ɛтɂ��A�u���@�Ɏ����������v���Ƃ͓��R�̏펯�ɂȂ��Ă���B����́A�����ł́u�@����v�������̂��ƂƂ��ďȗ����Ă���B�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�j
�@���i�A�i�u�l���߁v�̓�Ԗڂ́j�u���{����v�ɂ���āu��ɂ͎������L��v�Ƃ������o�E�ϔO�Ɋ���e����ł���l�X�́A���̂悤�Ȏl�́u�v�����݁v�����Ă���B�����|�|�|
�@
�@�i�A�j�u�����̓��̂ƈӎ��̎�̂́A���̓��̐g�̎����ł���v�Ƃ̎v�����݁B
�@�i�C�j�u��ł�����̐g�̌̈ӎ����������{���̈ӎ��ł���v�Ƃ̎v�����݁B
�@�i�E�j�u�����̈ӎ��́A���̐g�̎��������͂œ������Ă���v�Ƃ̎v�����݁B
�@�i�G�j�u��ł�����̐g�̎����������s�ׂ��Ă���v�Ƃ̎v�����݁B
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�j
�@���������u�{���]�|�v�����u���o�E�ϔO�v���C�����ׂ��A�C�s�҂́u��ɂ͎����������v�Ɛ������v�҂���i�悤�ɓw�߂˂͂Ȃ�Ȃ��j�B
�@�����āA���́u�䖳�����v�Ƃ����i�����́A�[���Ȃ�j�^�������̂ƌ̈ӎ��̋��X�ɂ܂ŐZ������悤�ɁA���̈Ӗ������x�����x���A������䍂���B�����|�|�|�k�����Q�l
�@�@
�i�A�j�u�����̓��̂ƈӎ��̎�̂́A���̓��̐g�̎����ł͂Ȃ��B�^�̎�͓̂��O�ɕ����ɕՖ�����s���̐^��ł���v�Ɛ������v�҂��A
�i�C�j�u��ł�����̐g�̌̈ӎ����A�����{���̈ӎ��Ȃ̂ł͂Ȃ��B�{���̎���ӎ��͔ϔY�ɔρi�킸��j�킳��Ȃ������g���̈ӎ��ł���A�s���̐^��̏����ӎ��ł���v�Ɛ������v�҂��A�@
�i�E�j�u�����̈ӎ��́A���̐g�̎��������͂œ������Ă���̂ł͂Ȃ��B�̂̎��ӎ��͐^��̏����ӎ��̊����ɋN�����āA����Ɋ��S�Ɉˑ����邱�Ƃŏ��߂ċ@�\�\�ɂȂ��Ă�����̂ɉ߂��Ȃ��v�Ɛ������v�҂��A
�i�G�j�u��ł�����̐g�̎������s�ׂ��Ă���̂ł͂Ȃ��B���̐g�̎����́A�w�����́@�L��^��x�̓����Ɉˑ����邱�Ƃŏ��߂ā��s�\���ɂȂ��Ă�����̂ɉ߂��@�Ȃ��v�ƁA�������v�҂���B
�@
�k�����Q�|�|�|�ߑ������H�E�`�������i�n�j���j���|�E���|�K�́A�ɂ߂Č��i�Ȃ��̂ł���A�u�^��v�u�@�g�v�u����@���v�u�^�@�v�u���v���X�A�u�����̗L�鑶�݁v�ɑ���u�Ăі��v����؎g�p���Ȃ����̂ł���B�i�^�|�P�T�|�Q�A�R�j
�@�������A�����ł́A���������o���ґz�ɂ��Đ������`�B���邽�߂̈�̕��ցi�֖@�j�Ƃ��āA�u�^��v�Ƃ������t�������Ďg�p���Ă���B�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�j
�@���ɑ�܂��Ɍ����ƁA�i�A�j����i�G�j�̂悤�ɐ������v�҂��邱�Ƃ��A�u�䖳�����̎��o�v�ł���i�X�Ȃ�ڍׂ́A��|�R�|�P�ȉ��j�B
�@�z�i���j�̔@���A�u�l�ԑ��݂݂̍�̂܂܂̐^���v���i�]�|���������������Ɂj�g�݂�̂܂܂Ɂh�F�������o���邱�Ƃ��A�u�䖳�����̎��o�v�ł���B�u�䖳�����̎��o�v�́A�������ʂŐV�����C���|�W��������Ƃł͂Ȃ��A�P�ɂ��ꖘ�g���Ⴂ���Ă����h�u���{����v�𐳂����u�����������̎��o�v�ł����Ȃ��B
�@�^���ɕ����C�s�ɋ��ގ҂́A�u�i��ł���j�����ɂ͎������L��v�Ƃ́i���ΏK�������Ă��܂����j�v���Ⴂ�ƁA�u��͖{���������Ȃ�v�Ƃ̐��������o�Ƃ́u��̋Ɂv�̊Ԃ��s�����藈���肷��B
�@���̓����́u���ɂ̍j�����v��栂��邱�Ƃ��ł���B
�@�������C�s����҂́A�₪�Ă��̍j�����ɏ�������B�܂�A�u��͖{���������Ȃ�v�Ƃ����u���������o�v�̋ɂɏ��X�Ɏ����̈ӎ������������čs���A�����Ɉӎ������܂鎞�Ԃ��������������čs���A�Ō�ɂ͎����̈ӎ������̋ɂ�������o�邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�m���ɐ��䂵�čs���B�@�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�T�j
�@�u�������̎��o�v�ɏZ���鎞�ɂ͔ϔY�͔������Ȃ��B���̂Ȃ�A���̎��ɂ́A��̎��ӎ����哱�����̂́i�����[���ł͂Ȃ����̂́j�^��ɐȂ������Ă���A�i�����[���Ƃ͌����Ȃ��܂ł��j�^��̒��ړ����̉��ł͔ϔY�͔������Ȃ�����ł���B
�@����A�u�䖳�����̎��o�v��r�����A�u��Ɏ������L��v�Ƃ̍��o�ɏZ���鎞�ɂ́A�ϔY����������B���̂Ȃ�A���̎��ɂ́A���̌�́A�u�l���߁v�i�^�|�Q�O�|�Q�R�j��Ƃ��Ă��܂��A����āu���遖��ӎ��i�A�n���J�|���j�v�i�^�|�Q�Q�|�S�R�j�ݏo���Ă��܂��A����Ɋ�Â��āA�^��̉c�ׂƂ͈�w����u�䎩�Ɛ��v�i�^�|�P�W�|�Q�P�j�̎v�O��݁X�Ɛ��ݏo���čs������ł���B
�@�u�l���߁v��Ƃ����ƂŐ��܂��u���遖��ӎ��v�́u�O�d�̉�̊ϔO�v�ŏo���Ă���B
���O�d�́u��v�̊ϔO���Ƃ́|�|�|
�@�i�P�j�u�i��v���A�Ƃ����j���̉䂱�����w��x�ł���i�Ǝv���j�v
�@�i�Q�j�u�����������w�i��v���A�Ƃ����j���̉�x�̂��́i���L�j�ł���i�Ǝv���j�v
�@�i�R�j�u���i��v���A�Ƃ����j���̉䁄�������s��̂ł���i�Ǝv���j�v
�@
�@�|�|�|�ƁA�����l����ϔO�ł���B���́u�O�d�̉�̊ϔO�v�ŏo���Ă���u���i��ށj遖��ӎ��v�����������i�c�j�ł���A�u����v�ł���B�i�O�͎Q�Ɓj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�i�^�|�Q�R�|�U�j
�@�ʎ�|�K�̏C�s�҂́A�u��͖{���������Ȃ�v�Ƃ̉s���Ȕے�̌��ɂ���āA���́u���遖��ӎ��v�Ƃ���������@���a��A���f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�u���遖��ӎ��v�������ɒ@���a��Ȃ�A����]�|���������͏C������āA�u���遖��ӎ��v�Ƃ͐����́|�|�|�����ӎ����i�{�u�̑���j�|�|�|���o������B
�@���́u���ӎ��v�́A�C�s�҂́u�䖳�����̎��o�v�̓x�����Ɉ˂��āA��[��̒i�K�ɕ����邱�Ƃ��ł���B
�@�{�u�ł́|�|�|
�@
�@�u���ӎ��v���|�|�|�i�A�j�u�[���ۉ�ӎ��i������Ђ��������j�v�@
�@�[���u���ӎ��v���|�|�|�i�C�j�u���△��ӎ��i��傺�ނ��������j�v
�@
�@�|�|�|�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�i���ɖ{�u�̑���j
�@
�i�^�|�Q�R�|�V�j
�i�A�j�u�[���ۉ�ӎ��v�ɂ���
�@�u�[���ۉ�ӎ��v�Ƃ́A�[���ɂ���Ď����́u���遖��ӎ��v�́u�O�d�̉�̊ϔO�v�����o�I�ɔے肷��ӎ��ł���B�����A�u�[���ۉ�ӎ��v�Ƃ́|�|�|
�P�D�u�i��v���A�Ƃ����j���̉�v�́u�{���̉�i�s��́j�v�ł͂Ȃ��u���������̉䁁���@�̉�i�s��́j�v�ɉ߂��Ȃ��B�@
�Q�D�����������u�i��v���A�Ƃ����j���̉�v�̂��́i���L�j�ł���͂����Ȃ��B�@�@�@�@�R�D�u�i��v���A�Ƃ����j���̉�v���s�ׂ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�u�i��v���Ƃ����j���̉�v�@�́A�^��̊����Ɉˑ����ď��߂Ċ����ł��Ă���ɉ߂��Ȃ��B
�@�|�|�|���������u�O�d�́���̔ے聄�̎��o�v�����ӎ��ł���B
�@���́u�O�d�́���̔ے聄�̎��o�v�́A�O�������{�l���u�[�������炷�v���Ƃɂ���āA���遖��ӎ��́u��v�����o�I�ɔے肵�čs�����ɐ�����ӎ���Ԃł���B�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�W�j
�@�T�^�I�Ȏ�����������B
�@�@
�@����������������̎����Ă��鑽���̍��Y�����P�c�̂Ɋ�t���邱�Ƃɂ����B������t�@���Ă݂�ƁA���̐l�́|�|�|�u���z�̑������t�����̂́i�N�ł��Ȃ��j�w���̎��x�ł��@��B�Ȃ�Ă������āw���̉��l�x�̂������Ƃł���v�|�|�|�Ƃ̍����Ȏv��������Ă��܁@���A�������ӋC�E�����C�ɂȂ�A�̂Ԃ��Ă��܂��u�S�̓����v�𐧌䂷�邱�Ƃ��ł��@�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�i�Ƃ�������j
�@
�i�^�|�Q�R�|�X�j
�@���̏ꍇ�A�������v�҂����点�悤�Ɠw�߂Ȃ��Ȃ�A���̐l�͂������A�����̋ƐсE���т��ւ����ŁA�u�����͈̂��v�Ƃ������z�Ɏ����Ĉꐶ���I���邵���Ȃ��B
�@�������A���̔��ɁA�����́u�{���v�𐳂����v�҂��A�\�X�iָָ�j�[������Ȃ�A���̂悤�ȁu�O�d�́���̔ے聄�̎��o�v�������Ƃ��ł���B�����|�|�|
�P�D�u���̎��v�Ǝv�����́A�^�̎��ł͂Ȃ��B�u���̎��Ǝv�����v�ɂ͖{���u�����������v�̂ŁA���g�Ǝ��̊������͖����B����́A�u���̓��̐g�̎��v������P�ƂŌ���A�Í��̌��̔@����R�Ƃ��Ă���A�Â܂肩���������̋@�B�̔@�����̂ł����Ȃ��B
�@�w���̎��x������P�ƂŌ���A�܂��Ɏ��[���������̔@�����̂ɉ߂��Ȃ��B
�@����́A�u�����A�����v�Ǝv���̂͑�ԈႢ�ł���B�u���̎��v�͐^�̎��A�^�̍s��̂ł͂Ȃ��B���͉��̎�̂ɉ߂��Ȃ��B
�Q�D�m���ɑ������t�������A�����̍��Y�͌��X�͎��̂��́i���L�j�ł͂Ȃ��B�i���͂������u�^�̏��L�ҁ������̑n����v�ɕԊ҂����ɉ߂��Ȃ��B�j
�R�D��t�s�ׁi���́u�^�̏��L�ҁv�ւ̕Ԋҍs�ׁj�́A�u���̎��v�̍s�ׂł͂Ȃ��B
���̂Ȃ�A��ɂ͎����������̂ŁA�u���̓��̐g�̎��v������P�ƂŌ���A�u���̎��v�͎��[���������̔@�����̂ɉ߂��Ȃ�����ł���B���͂����u�^���̍s�ҁv���u���̎��v��ʂ��Ċ������A�s�ׂ��ĉ����������Ƃ���сA���ӂ������ł���B
�u���̎��v�͉������Ă��Ȃ��B���͉������Ă��Ȃ��B�k�����R�l
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�O�j
�k�����R�|�|�|�A���A�u���s�i����~�哱�̍s�ׁ������̍s�ׁj�v�ɂ��āA�B�̂悤�Ɂu���͉������Ă��Ȃ��v�ƌ������Ƃ͋�����Ȃ��B�������̂悤�Ɍ����Ȃ�A����͐ӔC����̔ڗ�Ȍ�������ƂȂ�A���������������ɑ��Ă��܂��A�S�R���Ȃ��悤�Ƃ��Ȃ��A�ǐS�̖�Ⴢ������낵���l�Ԑ����`�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�����c�́A���X�ɂ��āA���������_����U�肩�����āA���Ȃ𐳓������悤�Ƃ���B
�@�܂��A�^�}�X�I�i�r���I�j�Ȑl�ԁi�O�͎Q�Ɓj�́A���������u�Ԉ������@���ґz�@�v�ɓ�������ŁA�߂̏������瓦��悤�Ƃ�����̂ł���B�^�^�l�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�P�j
�@���ꂪ���o�I�u�[���v�ɂ���āu���遖��ӎ��v��ے肷��v�ҁA�����A�[���ۉ�ӎ��̈��ł���B
�@�^���ȏC�s�҂́A�i�{����̂悤�ȁj�u��t�s�ׁv�̏ꍇ�݂̂Ȃ炸�A�u���K��ݗ^�����ꍇ�v�ɂ��u�D�G�ȋƐт�B�������ꍇ�v�ɂ��u���ł���z�{�s�ׂ������ꍇ�v�ɂ��u���ł���P�s�������ꍇ�v���X�ɂ��A�ϋɓI�ɂ����K�p���A�u�[���v�ɂ���āu�O�d�̉�̊ϔO�v��ے肷��v�҂�����悤�ɓw�߂˂Ȃ�Ȃ��B�i�����łȂ���A�u����������A����������v�Ƃ������遖��ӎ�����剻�������ŁA�����ӎ��ɓ��邱�Ƃ͌����ł͕s�\�ɂȂ��Ă��܂��B�j
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�Q�j
�i�C�j�u���△��ӎ��v�ɂ���
�@�u���△��ӎ��v�Ƃ́A���������o�̒q���ɂ���āA�u�䎩�Ɛ��v�̎v�O���ł��������ɐ����閳��̈ӎ��ł���B�����A�u���△��ӎ��v�Ƃ́|�|�|
�P�D�i�u��v���v�Ƃ������Ƃ������̂Łj�u��v���ӎ������A����ł���B
�Q�D�i�u��v���v�Ƃ������Ƃ������̂Łj����₱����u���̉�v�̂��́i���L�j�Ƃ��A�u���̉�v�̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ��v��Ȃ��B
�R�D�i�u��v���v�Ƃ������Ƃ������̂Łj�u���̉�v���s�ׂ��Ă���Ƃ��A�u���̉�v���s�ׂ��@�Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ��v�킸�ɁA���X���S�ōs�ׂ���B
�@�|�|�|���������u�O�d�́����䁄�̏�ԁv�ɋ���ӎ��ł���B
�@���̈ӎ��́A�C�s�҂��i�A�j�́u�[���ۉ�ӎ��v�́u��̔ے�v���X�Ɉ�w�A�O�ꂵ�Đ[�߂����ɗ�������ė���ӎ��ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�R�j
�@�C�s�҂��u�䖳�������ґz�v�ɐ�S���A���ꂪ�[�܂������ɂ́A�u��v���B�̂ɉ�L��v�Ƃ�����i�K�A���̍ŏ��̕����ł���u��v���v�Ƃ����u�������̏��v��B�f���ׂ��A���̂悤�ɐ������v�҂���B
�@�����|�|�|�u��v���v�Ƃ��������́A�u�����Ɏ������L��v�ƍ��o���āA�u���́v�ŏ���Ɂu���v�����Ƃ����v�l�v�����Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B���́u���v�����Ƃ����v�l�́v�ɂ��u�����͖����v�̂�����A�u�s���̐^��v�̓��������Ɏv�l�������c�܂�Ă���킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A�u���v�����Ƃ����v�l�́v������A�������z�̌��˂��ċP���Ă���@���A�^��i�������j�̗͂Ɋ��S�Ɉˑ����ď��߂Ċ����\�ɂȂ��Ă�����̂ɉ߂��Ȃ��B�]���āA�������g�̗͂Ŏv�l�������Ă���悤�Ɏv���̂́A�����ȍ��o�ɉ߂��Ȃ��|�|�|�ƁB
�@���̂悤�ɁA�����́|�|�|���v�l�̖͂��������|�|�|�ɂ��āA�{���ɐ[���ґz���邱�Ƃ��ł��悤�ɂȂ�ƁA�����Ɓu�䎩�Ɛ��̎v�l���G�O���v�O���x���̔ϔY�v����~����B
�@���ꂪ���������o�ɂ��u����i����v�ʁj�v�̈ӎ���ԁA�����u���△��ӎ��v�ł���B�k�����S�E�T�l
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�S�j
�k�����S�|�|�|�T�����̍��ۓI�ȕ��y�E�[�֊����ő����̋Ɛт��c������ؑ�ٔ��m�́A�u���S�Ƃ������Ɓv�i�p�앶�Ɂj�Ȃǐ��X�̒����ɂ����āA���S�E����̋��n�����@���̌��̋ɒv�ł���A�Ƃ̗�������B�������A�{�u�́A�����@�̕s��ꌳ�̗�I���B�W�����ւ̖v���A�y�ѐ^��̌������������@���̋ɖk�̑̌��ł���A�Ƃ̗�������B���̗��ꂩ��́A����E���S�̋��n�́A���̈����O�̃��x���ƈʒu�t������B�ڍׂ͎��͈ȉ��B�^�^�l�l
�k�����T�|�|�|�u���△��ӎ��v�́u���@���I���x���̈ӎ��v�ł���B
�@���̂Ȃ�A���̈ӎ��̎��ɂ́u�����́��L���X�g����M���Ă���v�Ƃ��u�����́�������M���Ă���v�Ƃ��u�����́����_������M���Ă���v�Ƃ��u�����́��C�X��������M���Ă���v�Ƃ��u�����́��q���h�D�|����M���Ă���v���X�Ƃ͌����Č���Ȃ����A�l�������Ȃ�����ł���B���̂悤�Ɂu���́A���́c�v�Ǝ��Ȏ咣����u���遖��ӎ��v��������ԁA���ꂪ���△��ӎ��ł���B�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�T�j
�@�u���������ґz�v�Ɋ���Ă��Ȃ����S�҂́A�u�v�l��~�v�Ƃ��u�v����Łv�Ȃǂƕ����ƁA�u����ł͎v�l�͂������Ȃ��āA�n���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̋��������B
�@�������A�u���������ґz�v�͖O�������A�u�����L�鑶�݁���b�q��������v�Ɉӎ����W�����čs����@�ł���B����́A�u�������W���v�̉��Ŏv�l���~����ƁA��̏��������������E�����A��̐�m�b���_�U�������A�^�̉b�q�������o������y�낪���������B
�@���̎��ɂ́A�i�O�X�͂ŏڐ������j�r���I�Í��S�����C���̊�������~���Ă��܂��̂ŁA�Ԉ��I�����u�����C�������������O�ʂɏo�ė��邱�ƂɂȂ�B
�@����āA�������u���△��ӎ��v�́|�|�|���g�����I�h���△��ӎ����|�|�|�ƌĂԂׂ����̂Ȃ̂ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�U�j
�@�]���āA���̈ӎ����o�����鎞�ɂ́A���̎҂͌����Ĕn���ɂȂ邱�Ƃ������ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��B���ݐ����ӎ��́i�s�q�Ő����ȁj�u�������v�̌̂ɁA���̎҂ɂ͉s�����ρE���@�́E��I���m�́E��I����͓��X�̏��\�͂���������悤�ɂȂ�B�i�����A�����ł́u����v�́A�����~���́u�~���v�ɓ�����A�S�̖��������Ӗ�����B�����ă^�}�X�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�j
�@�������A�u�������W���v�������A�������̈Ӗ������������A�ӎ����U��������Ԃ̂܂܁u�v�l��~�v�����悤�Ƃ���Ȃ�A����́u�^�}�X�I�i�r���I�j�Ȏv�l��~�v�A�ӑĂȂ����̎v�l��~�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȍ`�Ŏv�l��~���s���Ȃ�A�r���I�œݏd�Ȕg�������債�A���m�̈Í��͐[���Ȃ�A�������i�s�Łj�����傷�����ƂȂ�B�i������ґz�A����Ɏ�����B���Ă̑T�m�͐S���ׂ��ł���B�j
�@�܂��ƂɁA�u���������o�̎v�l��~�v�Ɓu�U���ӑĂȎv�l��~�v�Ƃ́A���Ĕ�Ȃ���̂ł���B���𐳂����i�݂����ƔM�]����҂́A�����Č����ė��҂��������A�����X�ꏏ�ɂ������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�V�j
�@�u���������o�̎v�l��~�v�𐬏A���A�u�i�����I�j���△��ӎ��v�ɒB���邽�߂ɂ́A���������W���́E�ґz�͂��K�v�ɂȂ�B
�@�u�[���ۉ�ӎ��v�̏ꍇ�ł���A������x�u�������v�҂���́v�̗L��҂Ȃ�A�����I�ɓ��Ȃ��邱�Ƃł���𐬏A���邱�Ƃ͑R���i� j������Ƃł͂Ȃ��B
�@�������A�u�����I���△��ӎ��v�ɎQ�����邽�߂ɂ́|�|�|���u�܊��������h���v���Ւf����قǂ́��|�|�|���������ӎ��W�����K�v�ɂȂ�B
�@�u�܊��v�i�Ꭸ�@��g�j�́u���o�E���o�E�k�o�E���o�E�G�o�v�̎h���ɋC������Ă��ẮA�u�s���̐^��v�Ɉӎ��������A�W�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@����́A���△��ӎ��ɒB���邽�߂ɂ́A�u�܊��Ƃ����嗤���痣�����邱�Ɓv������Ƃ��K�v�ɂȂ�B�k�����U�l
�k�����U�|�|�|�u���o�튯�����o�̑Ώۂ�����������āA���ȁi�^��j�����v�i�J�^�E�E�p�j�V���b�h��E�P�E�P�j�ƋL����Ă���ʂ�ł���B�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�W�j
�@�ꕔ�̃n�^�E���|�K�̍s�҂ȂǁA���̂̃R���f�B�V�������i�O�I�j�ɂ���C��z��߂���҂́A���̂����������̔����͂����F���̈��S��̌���ł���A�]���āA�u�����o�m�̍�p�v���������̌���ł���A�Ǝ咣����B
�@�������A�����T�t�́A���@�ᑠ��܁u���S�����v���ɂ����āA���̂悤�ȑ�؍��t�d���a���̌��t�����p���āA���̖��ɓ����Ă���B�����|�|�|�u�������A�����o�m�i�̍�p�j���ȂāA������Ƃ���Ȃ�A���B�}���L�|���e�B�i�ۖ��j��F���܂��Ɂw�@�́A������A��������A���f������A�m�����肳�����̂ł͂���܂���B���E���E�o�E�m���s�g����҂́A���E���E�o�E�m�����߂Ă���̂ł����āA�@�����߂Ă���̂ł͂���܂���x�k�����V�l�ƌ����͂����Ȃ��v�|�|�|�ƁB
�@�z�i���j�l�Ȑ�B�̌��t�������ɂ�����ŁA�����T�t�́u�g���S���N�����Ă��Ȃ��h�ʏ�l�̗��m�O�o�i��p�j�i���ꎩ�́A�����͕����̔����j�ƌ�����邱�ƂȂ���v�Ɛ����Ă���k�����W�l�B
�@
�i�^�|�Q�R�|�P�X�j
�k�����V�|�|�|�u�ۖ��o�v�s�v�c��E�̖@��Q�ƁB�����ł͒�����l���m�̖|��i�������Ɂj�ɋ������B�^�^�l�l
�k�����W�|�|�|�����ł́A�g���S���N�����Ă��Ȃ��h�Ƃ̏����t���ł��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B�����T�t�̌����Ƃ���^�ӂ́A���̒ʂ�ł���B�����A�u�䎩�Ɛ��v�̗��m�O�o��p�́u���]�t�����v�i�^�|�P�W�|�Q�Q�j�̔��e�ɑ����邩��A��������̂܂ܒ��B�ȁi�X�g���|�g�ȁj�����̌�����p�Ƒ�����̂͌�肾�A�Ǝw�E���Ă���̂ł���B
�@�܂�A�u���{����v�Ɓu�O�d�̉�̊ϔO�v�ɂ��u���]�v�������Ă��邱�Ƃ����O����Ȃ���A�Ƃ������Ƃł���B�^�^�l�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�O�j
�@�u�s���̐^��v�ɋ��������ӎ��W�����A�u��i���]�j�Ɏ����������v���Ƃ�[���[�����o����ƁA�u�]���ԗl�́v�i����͌܊�����̎h���������A���̏���I�ʂ��đ�]�玿�ɓ`�B����@�\��L����j���A�܊�����̎h�������u�d�v�łȂ����v�Ƃ��Ĉ����A�����ŏ����J�b�g���A��]�玿�ւ̏��`�B���~���Ă��܂��B
�@���̂悤�ȋ����W������������ƁA���]�̓��̂́A�{���̊��S�Ȉˑ����E���ɗ��܂�A�u�䎩�Ɛ��̓����v�����������Ď�ł��A�i���͌��ł��邱�ƂɓO���āj��X�Ƃ�����ԂɂȂ�B���ꂪ�u�S�͖ؐ̔@���v�ƌ�����u�ؐΑT�v�́u���������o�̎�Ái���j��ԁv�ł���B
�@�S�|�^�}�E�V�b�_�|���^�������̉��Ō����J�����Ƃ����̂��A�i�@��Ɍ��ւ��ϑz�����j�u��������X�Ƃ��ė����Ă����ԁv����{�Ƃ��A�g�S������Ɠ��l�̏�Ԃɂ����ґz�@�i�����u�ؐɔ䂷�閳�������ґz�@�v�j���痈�Ă���B
�@�܂��A�T�Ƃł́u�S���ŋp����A�Ύ�����������v�k�����X�l�ƌ����B
�@����́A�����W���Ō܊����Ւf�����ґz�ɓ���A�������Ή����M���Ƃ͊����Ȃ��i�͂��ł���j�A�Ƃ����܊����E��ڎw���i���_�͎����`�Ƃ�������E�܂����j�u�|�����v�ł���B������A�䖳���������o�����ґz�@�̗���̒����琶�܂ꂽ���t�ł���B�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�P�j
�k�����X�|�|�|���̗L���Ȉ��́A�����̎��l�A�m䤒߁i�W�U�S�`�X�O�S�j�̎������̌���ł���B���S��V�T�t�̈��u��Ɠ`������i�u�Ɍ��^�v��l�\�O���u���R�������v�̕]���Q�Ɓj�B���{�ł́A�D�c�M���ɂ��u�b�ю��Ă��ł��v�̐܂�A���̎��ɋ�������T�t���Ă��ł��̉Ή��̒��ɂ����Ă��בR����Ƃ��Ă��̋��⏥�����Ɠ`�����A�L���ɂȂ�B
�@�A���A���̋�����̂܂ܐ^�Ɏ�ׂ��ł͂Ȃ��B
�@������ґz���ł���҂́A�������܂Ă���Ă����R�Ƃ��Ă���A�Ɖ�����͍̂s���߂��ł���B�܂��A�吹�҂ł���A�\���˂ɗ�����B�őł��t�����Ă����C�̕����ŗz�C�ɔ���ł�����A�Ɖ�����̂��s���߂��ł���B�܂��A�吹�҂Ȃ�A�������������̒ɂ݂��l�Z�����P���ė��Ă����R�Ƃ��Ă�����A�Ǝv���̂͊ԈႢ�ł���B
�@���_�A�H�̗��E��A�j�����B�J���p�E�T�}�f�B�i�^�|�Q�S�|�P�V�ȉ��j�̎��ɂ́A���̊��o���痣�E����̂ŁA���̓I�ɋ�͊����Ȃ��Ȃ�B�������A���̈ӎ��ɖ߂�A���̊��o�����߂������ɂ́A�ɋ���������ė���B���̎��ɂ́A�����ĉΉ����������Ɗ����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@����́A�O���������̋�́A�܊������S�ɒ��z����قǂ̋���ȏW����ڎw����́u�S�ӋC�v�Ɖ�����ׂ��ł���B�����́A�u�g�S�E���v�Ȃ�ʁu�g�S�i�̌���ӎ��j����̗��E�v�ɂ��u�j�����B�J���p�E�T�}�f�B�v�ւ̖v����ڎw���u�C鮂����߂��|�����v�Ɖ����ׂ��ł���B�^�^�l�l�l�@
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�Q�j
�@�T�Ƃł́A�u�厀��ԁA�劈���O�v���́A�����ā|�|�|���厀�劈���|�|�|�ƌ����B
�@���]�̖�����������̂܂܂Ɏ��o���A���̐������{���̒��Ɋ��S�ɗ��܂邱�Ɓ|�|�|���ꂪ�u�厀�v�ł���B���̂Ȃ�A�u�������̎��o�v�ɏZ���邱�Ƃ́u��~�̎��Łv���Ӗ����邩��ł���B�����āA���̎��ɂ́A�i�^��ɑ���j���S�Ȉˑ����Ǝ�����������̂ŁA�u�s���̐^��v����i���]�j���E�x�z����悤�ɂȂ�A�^��̑傢�Ȃ銈�i�͂���j������i���]�j��ʂ��Č�������悤�ɂȂ�B�|�|�|���ꂪ�u�劈���O�v�ł���B
�@
�@�P�D�u��̖������v��[�����o���邱�ƂŁA�u�䎩�Ɛ��̓����v���~������B
�@�Q�D����ƁA�u�����L�鑶�݁v�̓������i��́j�O�ʂɏo�ė���悤�ɂȂ�B
�@
�@�|�|�|���̏��ԁi���̓����j�ɂ����A�@���̐^��������B
�@�����^�������ł́u�ɖ������S���o�āA�閧�����S�ɓ���v�Ƃ����`�Ő����i��C���u�閧�֑ɗ��\�Z�S�_�v�Q�Ɓj�B�������̎��o���ɂ߂��S�������ƂȂ�A�閧�����S�i�������Ȃ�������E�ɖv�������S�j�Ƃ������ʂ�������B���̔閧�����S�������S�|���ł���A���ł���A�^�̎O���i�T�}�f�B�j�ł���B
�@���̃S�|���ɓ��B����ɂ́A�N�ł���O�Ȃ��u���������o�̖@��v��ʂ�˂Ȃ�Ȃ��B
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�R�j
�@�A���A�i�u�劈���O�v�ׂ̈ɂ́u�厀�E�v�l��~�E����v�������d�v�ł���ƍl���āj�P���Ɂu���^���v��������A�ӎ��I�Ɏv�l���~�߂悤�Ƃ��āA�����l���Ȃ��悤�ɓw�߂�Ȃ�A�ד��Ɉ��Ă��܂��B���������ꍇ�̉߂��́A���̓_�ɂ���B
�@���ɁA�u���^���v�����邱�Ƃ́A�u����ԁv����������ɑz���i�C���|�W�j���A�v�������ׂĂ��邱�ƂɂȂ�B����āA���������u��̎v�l�v�i��������ɂ��t���ʎv�l�j���g���Ă���h���ƂɂȂ�A�u�厀�v�Ƃ͑S�R�����Ȃ��B����ł́u�^�}�X�I�i�r���I�j���ґz�v�ɓ]�����Ă��܂�����ƂȂ�B
�@���ɁA�u�v�l���~�߂悤�v�u�����l���Ȃ��悤�ɂ��悤�v�Ɠw�͂��邱�Ƃ��A���̂悤�Ɂu�v�l���Ă���v���ƂɂȂ�B����ł́��u���v����ԁv�̃C���|�W�����Ƃ����Ԉ�������B�W������ړI�Ƃ��āA����Ɉӎ��W�����邱�ƂɂȂ�B����āA������u�^�}�X�I�i�r���I�j���ґz�v�ɓ]���������ƂȂ�B
�@�O�������A�ӎ��W�����ׂ����̂́A������P���͂���������u�����̗L�鑶�݁v�ł���B
�@�����āA����ɑ��銮�S�Ȉˑ����E�������o����̂��A�䖳�����̎��o�ł���B
�@�������āA��̖������𐳂������o����g���ʂƂ��āh���R�Ɏv�l���B�f����A�v�l��~�́u����v�ɓ���A�u�厀�v�̏�Ԃɓ���A�u�ؐv�̔@����Ԃɓ���̂ł���B�@
�@���������������o�߁i�v���Z�X�j�܂��ɁA���ʂ���������ɃC���|�W����Ȃ�A�ד��ɗ����čs�����ƕK��ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�S�j
�@�Ƃ���ŁA�T�ƂŌ������́u�厀�劈�v�̓����́A�T�����ɗ��܂�Ȃ��|�|�|�����@���I�E���ՓI�ȓ������|�|�|�ł���B�Ⴆ�A���̓����̓L���X�g���̒��ɂ��N���ɕ\��Ă���B
�@���̂��Ƃ������ƊT�ς��Ă݂�B
�@�S�L��L���X�g�҂́u����Ȃ闝�z�v�́A���Ă̐����i���͔푢���j���S�m�S�\�Ȃ�V���ɂ���āu���ړ����v����邱�Ƃł���B����́A�L���X�g�҂͂��̊肢���u�i�V�������ړ������ČN�ՂȂ���j��̉��������܂��悤�Ɂv�u��S���i���̂܂܁j�V�ōs���Ă���悤�ɁA�n�ɂ��s���܂��悤�Ɂv�u���̖]�ނ悤�ɂł͂Ȃ��A��S�̂܂܂ɂȂ�܂��悤�Ɂv�Ƃ����F��ŕ\������B�i�u��̋F��v�̏ڍׂ́u���|�Q�U�|�P�X�v�ȉ��j
�@�������A����������ƁA�u�n�v�ɂ͌�S���s���Ă���Ƃ͌�����B
�@���̂Ȃ�A�u�l�Ԃ̉�~�v�Ɓu����̊����i�͂��炫�j�v�Ƃ́A�S�������������̂�����ł���i�V���K���e���l�ւ̎莆�T��17�ߎQ�ƁB���̐���̉���́A���|�S�|�T�ȉ��j�B
�@���̕ӂ�̎���́A�u�O�O�i�̓����c�v�ł���u���遖��ӎ��v���A�^��Ɉ�w�������������邱�ƂɈ���A�Ɨ�������Ηǂ��B�����āA���̓����́u�l�Ԃɂ͈��͈͂œ��~�i�ϔY�j��������Ƃ����e����Ă���v�Ɩł���B�i�^�|�P�Q�|�Q�P�A�Q�Q�j
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�T�j
�@�������Ƃ���ƁA�������ɁA�V���Ɛ��삪�A���̈��|�I�Ȍ�͂�f�ōs�g���āA�l�Ԃ̓��Ȃ��������I�Ɏx�z���悤�ƈӎu�����Ȃ�A���Ƃ��ȒP�ɁA�l�Ԃ̓��i��j�͐���̒��ړ������ɒu����邱�ƂɂȂ�A���̌��ʁA�߂ł����A�V���́i�����ʂ��Ắj���ړ�������������͂��ł���B�i�������������Ȏ�@��]�ގ҂��A�l�Ԃ̒��ɂ͂���ł��낤�B�j
�@�������A�������������I�ȕ��@���A�V���͑I���Ȃ���Ȃ��B
�@��������|�|�|�u�l�Ԃ̓��i��j���A����i��Łw�����̖{���x�����o���āA�V���i���̓C�G�Y�X�E�L���X�g�j�Ɏ������g��i��Ō��サ�A�i�V���ւ̈��̂Ɂj����i��Łu�厀�v��I�Ԃ悤�ɂȂ鎞������̂��A���������ĔE�ϋ����҂v�|�|�|�������������A�V���͑I���Ȃ���̂ł���B�����炱���A���̎����I�ȁu���v�Ɋ�Â��u����ƗZ���̓��v������i��Łu�͔͂Ƃ��ďے��I�Ɏ������v�Ƃ��āA�C�G�Y�X�E�L���X�g�͏\���˂ɕt�����̂ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�U�j
�@�C�G�Y�X�E�L���X�g���u����i������Y�ɂȂ������Ɓv���Ă߂��A����������I���b�Z�|�W���A�����ʂ��Ē��ς��A��̐[���[�����Ɋ�������L���X�g�҂́A�C�G�Y�X�E�L���X�g�̖͔͂ɕ���āA�������\���˂ɕt�����Ɓi���u��~�ŋp�̑厀�v�j���肤�悤�ɂȂ�B
�@����́A�L���X�g���ɂ�����u�\���ˁv�́|�|�|�����́u���v�i�䁁���]�j��V���ɑS�ʓI�Ɂu���シ��v���ƂŁA�u�䎩�Ɛ��̓����v�ł���u��~�v�����S�ɖŋp���A�V���������́u���v�ł���u�䁁���]�v�ړ������ĉ�����悤�ɁA�u��̑��āv���u�^��ł���V���v�Ɂu�z�{����v���Ƃ��Ӗ����Ă���B�i�u�l�̎q�v�����Y�ɂ���鎖�Ɓu���̎ցv�Ƃ̊W�ɂ��Ắu���|�P�P�|�U�R�v�ȉ��Q�Ɓj
�@�|�|�|�ȏ�̒ʂ�A�u�L���X�g�̏\���ˁv�Ɓu�����v�̃h���}�ɂ́A�u�厀�E�劈�v�̗��ꂪ�����ɏے��I�ɕ\������Ă���B����͖����Ȏ����ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�V�j
�@�Ƃ��낪�A�i���@�̐��������j���@�̐��ł́A�u�厀��ʂ��đ劈�ɓ���v�Ƃ����u���@���I�ȋ~���̕��ՓI�^���v�m�̍��_�ŕ����B���A�u�劈��ڎw������ŏ[���B�厀�͖��p�Ȃ�v�Ƌ���������c�������o������B
�@�������������c�͑�́A���̂悤�Ȏ�@�Ől�X��f�킷�B�����A�u���Ȃ��͓��ʂɑI��Ă���v�Ǝ����グ�č����S����������A�M�k���u�����̔����v�ɐ��킹�ėǂ��C���ɂ����A�����Ȕ��ȐS����������悤�ɗU������B�������āA���c�Ǝ��̊Ԉ�������`��A���t���čs���̂ł���B
�@�u��~��ŋp���Ȃ��Ƃ��~����v�Ƌ�������ƁA��~���u�y�v�ƌ��関�n�œ]�|�������o�ɓ����ł���҂����́A�ӊ쐝��A����������Ċ�сA���́u���������`�v�ɔ�т��Ă��܂��B
�@����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�������g�̉�~�̌̂ɁA���̈��r�Ȋ��U�Ɗ����������A����ƘA���E�������āA�ד��ւƗ����čs���A���Ƃ�[�߂錋�ʂɂȂ�̂ł���B�i����́u�ނ͗ނ��Ăԁv�����ł���B�j
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�W�j
�@����Ɋr�ׂāA�������@�����c�́A�M�k�Ɂu���������A�ˁ��A�������g���v�̎d���ɂ��ċ�����B�܂��A�����ʼns�q�ȁu���ȐS�i���ȗ́j�v���琬��������ŋ��炵�A���������P�������サ�čs���B�������āA�u�������F����ґz�v�u��荂���F����ґz�v���ł���悤�ɁA�M�k�������čs���B
�@���̂悤�Ȑ������v�z�Ɏx����ꂽ�u�������@���̓��v�́A�i�O�����ŗz���́A���ݓI�ȁj���Ȃ̓��X�ł���A�F��̓��X�ł���A���Ȓb���̓��X�ł���A�V���Ȓ���̓��X�ł���B
�@�܂�|�|�|����~�̒i�K�I���z��ڎw���A���̖ŋp��ڎw�����X���|�|�|�Ȃ̂ł���B
�@���̓��́A��~�Ƃ̐₦�ԂȂ������E�����̓��ł���B����āA�����ėe�Ղȓ��ł͂Ȃ��B�����炱���A��~���u�y�v�ƌ��āA�����������҂́A�����������D�܂Ȃ��̂ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�Q�X�j
�@�|�|�|�ȏ�̂��Ƃ��疾�炩�Ȓʂ�A�u�ǂ������^���������v����������A��̑傫�ȃ|�C���g�i�����N�}�|���j�́A���̌����ł���B�����|�|�|
�@�u���������o�̑厀����~�̖ŋp�v���m�肵�A����ɓ��铹���g��������Ɂh��������Ɛ������Ă�����̂́A�u�ǂ������v�ł���B
�@����A����Ɣ��ɁA�u�厀���~�̖ŋp�Ȃǂ͖��p�Ȃ�v�Ƃ��āA�����ے肵�A����ɓ��铹��S�R�����Ȃ����̂́A�u���������v�ł���B
�i�܂��A�ꌩ�u�厀�E��~�̖ŋp�v�������Ă���悤�ł��A���̎�i���u�ߌ��v�ł����āu�����v������Ă���ꍇ�́A�ד��ł���A�u���������v�ł���B�j
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�O�j
�@�u�䖳�����̑厀�v�������Ȃ��u���������v�̓T�^�����������Ă݂�B
�@�u�������z�����Ǝv���Ȃ����v�Ƃ��u����͑�������@���Ȃ聄�k�����P�O�l�ƕS���Տ����Ȃ����v�Ƃ��u����͑S�m�S�\�Ȃ聄�ƕS���Տ�����A�₪�ĕK���S�m�S�\�҂ɂȂ��v�Ƃ��u����͕��Ȃ聄�Ə�ɔ�䍂��Ȃ����v�Ƃ��u�w���Ɍ���Ă��܂����x�Ǝv������ł悢�B���ɓ��Ă���̂�����v���X�̋������A����ł���B
�@�������������ɁA�����l�A��т��҂́u�v���v�u��~�[��v�Ƃ̔���Ƃ�Ȃ��B
�@�����������������H����ƁA�m���Ɉꎞ�I�ɂ͋C�����ǂ��Ȃ�A���ł��ł���C�����ɂȂ�A�ϋɐ����o�ė��邵�A���C�ɂ��Ȃ�A�u�����v�����o�ė���悤�ɂȂ�B
�@�������A����ƕs���ɘA�����Ă���u�����������S�v�ł���u���遖��ӎ��v�̔�剻���s���ƂȂ�B����āA���̎�@�ɂ���ĉ�~�ł���ϔY�𐧌䂵�A���z���邱�Ƃ͕s�\�ł���B������肩�A����������@�ɂ���ďo�Ă����u�������ϋɐ��v�ɂ���āA�߈���݁X�Əd�ˍs�����Ԃ����������Ƃ������Ƃ͌����Ȃ��B
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�P�j
�k�����P�O�|�|�|�P���́u����o�`�v�Ɂu�䑦����v�Ƃ̕\��������B����́A�E�p�j�V���b�h�́u�����@�v�z�v��ʊp�x����\���������̂Ɖ����˂Ȃ�Ȃ��B�����A�u�䑦����v�́u��v�́u�^��v���A�u����v�́u���v��\���Ă���B
�@�������A�@���ŋ��ׂ������悤�Ɗ�ށu�������v�T�O�ɖ��m�Ȃ�҂��u�䑦����v�Ƃ������t������ƁA�u�����̑���͑��A����@���Ȃ�v�Ƃ����Ӗ����ƌ�����Ă��܂��B�����āA�M�k�����Ɂu����v�̈Ӗ��Łu���䑦������Ə����Ȃ����v�Ƌ����邱�ƂɂȂ�B
�@�����̖{����ق����A�u����v���u����v�Ǝv�����݁A�u���������o�̖@��v��ʂ炸�ɁA�l�]�|�̎�������Ēu�����܂܁A�u���̋��n�v�ɓ��낤�Ƃ���̂́A�܂��ƂɉG���i���j���܂����U�����ł���B���l�ҁX�����A���疳�p�Ȃ�s�ׂł���B
�@�m���ɁA��Ɏ����ʂ�A�u��v�́u����v�̕ω��g�ł���B���̈Ӗ��ł́u��A���A����v�ł���i��|���|���\�ȉ��j�B�������A�u�l���߁v��Ƃ��āu���]�t�����v�Y�������Ă���u��v�́u����v�ł���A���́u����v���u����v�Ȃ̂ł͂Ȓf���ĂȂ��B
�@���̗������҂́A�y�X�Ɂu�䑦����v�Ƃ��u�䑦�S�\�Җ�v�Ȃǂ̎����������邱�Ƃ͂Ȃ��B��������A�u�䖳�����v�̖@���ʂ邱�Ƃ����A�M�]���邩��ł���B�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�Q�j
�@�A���A�u���䑦������Ə�����v�Ƃ����悤�ȋ������A�v���X�ɓ����ꍇ�������킯�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�]��Ƀ��x���̒Ⴂ�҂����A�敪���^�}�X�I�i�r���I�j�œݏd���̏�Ȃ��g���̒��ɏZ�݁A�ӑĂ̏�ɁA�ے�I�E���ɓI�ȑz�O�ŋÂ�ł܂��Ă���A�w�ǖ�������Ԃɋ߂��悤�Ȏ҂����ɑ��ẮA�ꎞ�I�ȃJ���t���܂Ƃ��āA�ނ�̍����S���h�����āu���C�v���N�������A���M���������A�����̂��߂ɗ����オ�点��A�Ƃ������ʂ��A�m���ɗL��B
�@�������A���ɏ[���Ȋ������Ă���҂����A�������W���X�I�i�����I�j�Ȏ҂������A�������u�S�\�ҁv�Ǝv������A�u���z�v���Ǝv�����肷�邱�Ƃ́A�傫�ȍЂ��ƂȂ�B
�@���̂Ȃ�A�u�l�u�̓Ɨ�������栂��v�i�^�|�P�X�|�P�P�ȉ��j������Έ�ڗđR�A�u���遖��ӎ��v���L��܂܁A�����u���{����v��Ƃ����܂܁A�Ζ��i�ł��鎩���̍˔\�Ɗ��́j�������̂��̂Ƃ��ċ��ݏo���A���p���ė��v���グ��͏グ��قǁA�s�ׂ̈��������債�A���Ƃł��镉�����債�A��̕s�K�����債�Ă��܂�����ł���B
�@�Ⴆ�A�u������͂��l���ł���v�Ƃ��������c�̊Â��U���ɏ���āA�u���\�͊J���v�̃��|�K�ɓ����݁A���������C�s�ɖv������Ȃ�A���̎҂́A���������o�̏C����ς�ł��Ȃ��̂ŁA�J���������\�͂��u��~�̖����̂��߂Ɏg�������v�Ƃ����U�f�ɏP����Ɓi�����āA�q�ꂽ��̌R�c�̉e���͂ɂ��A�K�����������U�f�ɏP����j�A�K������ɕ����Ă��܂��A����ׂ���߂�Ƃ��H�ڂɊׂ�Ȃ��ł͂����Ȃ��B�k�����P�P�l
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�R�j
�k�����P�P�|�|�|�q���h�D�|���̒��ɂ́A�u���̓T�b�`�_�|�i���_�ł���v�Ɣ�䍂����@���L��B����͎������u�S�m�S�\�Ȃ�u���t�}�����̂��́v�Ǝv�����ގ�@�Ƃ͔����Ƀj���A���X�̈Ⴄ���̂ł���B���̓_�A���ӂ�v����B
�@�T�b�`�_�|�i���_�Ƃ́A�T�b�g�i�s�ł̎��݁j�E�`�b�g�i�����ӎ��j�E�A�|�i���_�i����@�x�j�̎O��̘A����ł���B�����āA�T�b�`�_�|�i���_�́A�q���h�D�|���ł́A�u���t�}�����\������s���̊�{�O�v�f�Ƃ����B
�@�����ŏd�v�ȓ_�́A���̃T�b�`�_�|�i���_�Ƃ������t�ɂ́A�u�S�m�v�Ƃ��u�S�\�v�Ƃ����T�O���g�Ӑ}�I�ɔr������Ă���h���Ƃł���B
�@�u���|�I�Ȋ���@�x�̒��Ł������݂遄�Ƃ��������ӎ��v�|�|�|���ꂪ�T�b�`�_�|�i���_�ł���B
�@�z�i���j�̔@���A���̌��t�̈Ӗ��𐳂�����������Ȃ�A�C�s�҂��������g���u���̓T�|�`�_�|�i���_�ł���v�Ǝv�O���Ă��A�ד��Ɉ��邱�Ƃ͂Ȃ��B���̂Ȃ�A�u�`�b�g�v�Ƃ����u�����ӎ��v�ɂ́A�ϔO�E�ϑz�E��s�E�s���s���E���O�E�����E�^�O���X�̎G�O�ł���u�ϔY�ӎ��v�͈�؊܂܂�Ȃ��̂ŁA�u���g�������ӎ��Ɗo�m����v���߂ɂ́A���g�̑��Ă̖ϔO���Y�킳���ς�̂ċ��邱�Ƃ��v������邩��ł���B
�@�܂�́A�u�����ӎ��i�`�b�g�j�v�̈��̒��ɁA�u�厀�v�̊T�O�����Ɋ܂܂�Ă���̂ł���B�i�ܘ_�u�`�b�g�v�𐳂��������Ȃ��҂́A�T���ė�I�����̑���ɗ�����B�j�^�^�l�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�S�j
�@�ȏ�Ŗ��炩�Ȓʂ�A���c�������āi���͒N�ɑ��Ă��j�u�厀���p�B�劈��{�ŗǂ��v�Ƃ������e�������Ă���ꍇ�A������������������l�Ԃɏ@���������鎑�i�͖����B
�@���̓_�A�������茩�����邱�Ƃ��K�v�ł���B
���u���������o�̑厀��v�Ƃ����u������̖{��v��ʂ邱�Ƃ��������A��~�̔�剻��������ҁ��|�|�|���������y�́A���̐����҂ł���A�ߐ[���҂ł���B
�@���������y�́A�L���X�g�̏\���˂Ӗ��E���p�ɂ��Ď��g���ւ��Ă���ɓ������̂ŁA�����ȋ��҂ł����Ȃ��B
�@���������y�́A��C�́u���g�����`�v�ɂ���u�����v�k�����P�Q�l�̋����Ӗ��E���p�ɂ��Ă��܂��ɓ������̂ŁA�O���ł���B
�@���������y�́A��C�́u�閧�֑ɗ��\�Z�S�_�v�̑��Z�S�u�ɖ������S�v�̋����Ӗ��E���p�ɂ��Ă��܂��ɓ������̂ŁA�j���҂ł���B�܂��A�u�ɖ������S�v��ʂ炸�Ɂu�閧�����S�v�ɓ��邱�Ƃ��ł���Ɛ����Ă���ɓ������̂ŁA���ȗ��여�Ɠ����̎҂ł���B
�@���������y�́A�N���V���i�́u�䂾���̊��ƂȂ�v�i�M�|�^11��33�߁j�i���̋�̏ڍׂ͐^�|�Q�Q�|�T�O�ȉ��j�̌��t�Ӗ��E���p�ɂ��Ă��܂��ɓ������̂ŁA�j�Z�̃O���̗ނł���A��I�ȍ��\�t�ł���B
�@���������y�́A�����T�t�́u�g�S�E���v�́u�E���v�Ӗ��E���p�ɂ��Ă��܂��ɓ������̂ŁA����i���j�ґz�҂ł���A�u�^�}�X�I�i�r���I�j�ґz�v���s�����シ��҂ł���A�q��킵�����ȋ\�Ԃɓh�ꂽ�҂ł���B
�@���������y�́A�q���h�D�|���̃T���j���|�V�i�����ҁj�́u�T���j���|�T�i�����j�v�Ӗ��E���p�ɂ��Ă��܂��ɓ������̂ŁA��~�ɓh�ꂽ��D�_�E�哐���ł���B�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�T�j
�k�����P�Q�|�|�|�u�����Ƃ́A�@���̑�߂ƏO���̐M�S��\���B�����̉e�A�O���̐S���Ɍ���������Ƃ��ЁA�s�҂̐S���A�悭����������������Ɩ��Â��B�v�i��C�u���g�����`�v���B���A�����ł́u�e�v�́u���ʁv�̈Ӗ��B�A���A�u�e�v���u���v�Ɠǂ݊����āA�����T�t�́u���@�ᑠ�v�w�C��O���x���́w�C��x�́u��v�ɔ䂷�邱�ƉB�j
�@�܂�A����@���̑厜�߁E��������O���̐M�S�̐S���ɏƎ˂���邱�Ƃ��u���v�ƌĂсA�M�҂́u�~���ƂȂ��������v�����̑�������悭�~�߂Ĕ��˂��邱�Ƃ��u���v�ƌĂԁA�Ƃ��������̂ł���B�i����@���̌������\�S�Ɏ~�߂Ȃ��ꍇ�́A╂Ő����~�߂悤�Ƃ��鎞�̂悤�ɁA���̖w�ǂ����Ă��܂��B�j
�@����́A�u�����v���\�S�ɐ������邽�߂ɂ́A�M�҂̐S���u�����~������v�i��~�����nj���j�Ƃ����u�������̖{���v�ɗ��܂邱�Ƃ��K�{�̏����ƂȂ�B
�@����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�O�������A���g�i��j�̖{�������́u���v�i���nj���j�Ǝ��o���邱�Ƃ����g�����Ɍq����̂ł����āA���̎��o�������ɁA���g�i��j�����@�����̂��̂��Ǝv�����Ƃ����g�����Ȃ̂ł͌����ĂȂ��B�{�́u���P�O�v�i�^�|�Q�R�|�R�P�j�Q�ƁB�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�U�j
�@�|�|�|�ȏ�A�ڍׂɌ������ė����ʂ�A�{���Ɂu���������o�̑厀��v��ʂ蔲�������Ƃ����u�������肢�v������҂������A�ד��Ɉ��邱�ƂȂ��A�^�������ɐ���������i�ނ��Ƃ��ł���B
�@�u���̋�����v��ʂ邱�Ƃ������A���̓�����T���A�u���K�̐ؕ��v�킸�ɁA�s�@�ɍ�����z���Ē��ɐN�����悤�Ƃ���҂́A�����ꖡ�Ƃ��Ĉ��ƈ��ʂ̌����������邱�ƕK��ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�V�j
�@�ł́A�����ň�x�A���ꖘ�̏����܂Ƃ߂Ă݂�B
�@�u���������o�̑厀��v��ʂ蔲���悤�Ƃ���C�s�҂̑O�ɂ́A�i���Ɍ����ʂ�j��Ɂu�l�̕ǁv�������͂������Ă���B
�@
�i�P�j�����́u�{���v���u�������v�ҁv�u�[���v���āA�u����v��ے肵�čs���ӎ����K�v�@�ł���B
�i�Q�j�P�Ɂu�v�l���Ȃ��v�悤�Ɂu�v�l�g����h�v���Ƃł́A�����āu����v�ɓ���Ȃ��B�@�i�u���́v�Ŋ撣�邱�Ƃ̌��E�ɂ��Ă͐^�|�V�|�W�A�^�|�P�O�|�P�O�ȉ��j
�i�R�j�܊��i�̎h���j���Ւf����قǂ́u����ȏW���́v���K�v�ł���B
�@�@�i�u���I�ؗ́v�ɂ��ẮA�^�|�P�O�|�R�O�j
�i�S�j��~���u�y�v�ƌ��Ȃ��Ő������u��v�ƌ��āA�厀�i��~�ŋp�j���肢�A��~�Ɠ����@����u���Ȃ̓��v��I�ю���čs���K�v���L��B�k�����P�R�l
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�W�j
�k�����P�R�|�|�|���̎l�ڂ̕ǂ��L���X�g���̗��ꂩ��\������Ɓ|�|�|�u�쐫�C�s�̓����u���҂͒N�ł��A���������g�̃Q�c�Z�}�l�̉�����ʂ�˂Ȃ�Ȃ��v�|�|�|�ƂȂ�B
�@�C�G�Y�X�E�L���X�g�͏\���˂Ɋ|����O�ɁA�Q�c�Z�}�l�̉��ɂ����āu����ɏ]���ȓ��v�Ɓu��i�~�j��ʂ����v�̗��҂̊Ԃɋ��܂�Ċ������A�җ�ɋꂵ�B�������A�ނ͋���ȋF����ґz��ʂ��Ă��̊����ɏ������A��~��ŋp���邱�Ƃ��ł����B
�@����Ɠ��l�ɁA�L���X�g�҂́A���g�̏\���˂̓��i��~�ŋp�E�厀����̓��j��i�ނ��߂ɁA���������g�̃Q�c�Z�}�l�̉����ɂ����ā|�|�|��~�ɐg��C���邩�A�͂��܂��A��~�̖ŋp��ڎw���Ē��z�̓����s�����|�|�|���̗��҂̋��ԂŊ������A��X�Ƌ�Y���Ȃ��ł͍ς܂���Ȃ��B����́u���Ȃ̓��v���s�����́u�s���̒ʉߋV��v�Ȃ̂ł���B
�@�����������n�ɗ��ƁA�u�C�G�Y�X�E�L���X�g���Q�c�Z�}�l�̉��ň���ꂵ�܂ꂽ�̂ŁA��X���g���g�e�l�ŗL�̃Q�c�Z�}�l�̉��h�ŋꂵ�ޕK�v�͂��͂�f���Ė����̂ł��v�Ƌ�����i�ꕔ�́j�L���X�g���̐��E�҂̍l�����Ԉ���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�B�ڍׂ́A���|�S�|�P�S�`�P�U���Q�ƁB�^�^�l�l�l
�@�@�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�R�X�j
�@�����̋������u�l�ǁv�͂ǂ���A�ȒP�ɂ͏��z��������̂ł͂Ȃ��B
�@���ł����Ɂu4)�̕ǁv�ɂ́A�����̎҂��T���Ă��܂��B��~�Ƃ̓�������ɂł��邪�̂ɁA���������������āA�u�厀���p�̓��v���s�����Ƃ��Ă��܂��̂ł���B
�@�������A�u�厀���p�v�Ƃ����l��������A�ǂꂾ���I���Ɂu���Ȑ������̘_���v��g�ݗ��ĂĂ��A����͎��ł����Ȃ��B���̂��Ƃ́A���ɋ�i�Ԃ��j�Ɍ��ė����ʂ�ł���B
�@�ł͔��Ɂ|�|�|�u�厀���p�v�Ƃ͍l�����A�e�Ɋp�A���P�Ɂu�厀�v���肤�|�|�|����ŗǂ��̂��ƌ����A�ܘ_�����ł͂Ȃ��B
�@�u�厀�v������Ă��A�ד��ɗ����邱�Ƃ͑傢�ɗL�蓾��B
�@�Ⴆ�A���Ȃ�q�X�e���|�C���ɁA���}�ɃS�|����_���čs���Z�C�Ȏ҂́A�ƁX�A4)�̕ǂ��T�����̂ł���B�ނ�́A�E�s�Ɂu��͕K���厀�ɓ���v�ƌ��ӂ���B�����܂ł͗ǂ��B�������A���̂��߂ɁA�u�̐g�̍r�s�v�Ə̂��āA�ߌ��Ȓf�H�����Đ��㎀����s���ɏo����A�������߂ɂȂ��Ē���������s���ɏo����A�f�R��ǂ��瓊�g���E������A�H��ŏĐg���E�����蓙�̋��ɑ���B���������s���́A�u�Ԉ�����`�̑厀�v�ł���B
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�O�j
�@�u�������`�̑厀�v��B������ɂ́A���́u�O�̈ӎ��v������Ƃ��K�v�ł���B
�@
�@���u�������厀�v�����̂��߂́u�O�v���v��
�@�i�A�j�[����q�ӎ��@
�@�i�C�j�i�u�����̗L�鑶�݁v�ւ́j��ΓI�M���@
�@�i�E�j�u��v�̖����n���i����̎哱���̈Ϗ��I�����E��ҁj
�@
�@�|�|�|���̎O�ł���B�k�����P�S�l
�@�ȉ��A�����������čs���B�@
�k�����P�S�|�|�|���́u�O�̈ӎ��v�́A�N�����ʂ�u�e�l�ŗL�̃Q�c�Z�}�l�̉��v�ł̗�I�����i��I�����j�ɏ������邽�߂́u�K�{�̎O�v���v�ł�����B�^�^�l�l�@
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�P�j
�i�A�j�[����q�ӎ��ɂ���
�@�u��q�ӎ��v�Ȃ����āu���������o���ґz�v�Ȃ��B
�@���̂Ȃ�A�u���������o���ґz�v�́u�^�̗�q�v�̐[���`������ł���B
�@�]���āA�u�����Ȃ閳�ׁv�̗͂���������悤�ɁA�u�^�̗�q�v�����̂��߂̘Z�v���̏[�����K�v�ł���i�^�|�P�Q�|�T�ȉ��j�B���ꂪ�u���������o���ґz�v���s����ł́u��{���̊�{�v�i����O��j�ł���B
�@�������A���������o�̒q���������͂Ł��U�����ł���A���̎҂͐^�̖������̎��o�ɓ��邱�Ƃ͌����Ăł��Ȃ��B�^�ɐ������[���u��̖��������ґz�v�ւ̎Q����]�ގ҂́A�������̕����ɓ�����|�|�|���i���g�́j�v�l�̖͂��������|�|�|�����[�����o����K�v���L��B
�@�����ā|�|�|�u�{���I�ɁA���g�ɂ́i����Ɨ��E���ˑ��́j�v�l�͈͂�ؔ�����Ă��Ȃ��̂ŁA�����̌̈ӎ����ꎩ�̂ɂ́A��q����͂��ґz����͂��A�{���I�ɔ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��v�|�|�|���̂悤�Ɂu�������̎��o�v���u��q���ґz�v�ɂ��y�ڂ��ēO�ꂷ��K�v���L��B
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�Q�j
�@����ǂ��A���̂悤�Ɏ��o�������Ȃ�A���̌��ʁ|�|�|�u�����́����͂Ł���q���ґz�����Ă���v�|�|�|�Ƃ����]�|�������o�E���ς���E�p�ł���B
�@�܂�A�u���͂ł͂Ȃ���q���ґz�v�����o�I�Ɏ��H���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B
�@��������ƁA�u�������A�������c�v�Ƃ����u��̋����A�������̗�q�s�ׁv�����ł��čs���A���R�Ȍ`�́u�݂͂̂Ȃ���q�v����������B
�@���������u��������q�ӎ��v�ɐi�ݓ���Ȃ�A���͂��O���킵���u�̐g�̍r�s�v�Ȃǂɓ˂��i�ޏՓ�����������ė��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@���������u�������`�́A���͂ł͂Ȃ���q�ӎ��v��[�߂čs���ƁA�u��q����ҁv�Ɓu��q����鎩���L�鑶�݁v�Ƃ̋�ʂ��A���X�ɕs�����ɂȂ�A�₪�ď��ł��čs���B
�@���������ߒ��̓r���ŁA�u�i�����I�j���△��ӎ��v���o������̂ł���B�k�����P�T�l
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�R�j
�k�����P�T�|�|�|�{�u�ł́u���△��ӎ��v���A�ɂ߂ē���ȁA�s����ňꎞ�I�Ȉӎ���ԁA�ƈʒu�t����B���̂Ȃ�A�������A�C�s�҂��j�����B�J���p�E�T�}�f�B�i���́j�ɓ��肷��Ȃ�A������u����̏�ԁv�Ə̂��邱�Ƃ͑��������Ȃ�����ł���B
�@�T�}�f�B�̌��̐^�����ɂ����ẮA�u�^��v�̈ӎ��̒��ɖv�����Ă���A�u�^��v�ƕs����̂̈ӎ��ɐZ���ċ���B�܂�A�u���v�Ƃ��Ắu��̈ӎ��v���L��̂ł���B
�@���̂悤�Ɍ���ƁA�u���△��ӎ��v�́A���̓�̏ꍇ�����Ɍ��肳���B�����|�|�|
�i�@�j�T�}�f�B�ɓ��钼�O�́u�������̎��o�v���ɂ܂�����Ԃł́u���䂪���ƂȂ��ĒE���@�@�@�����ԁv�Ɍ���Ȃ��ߐڂ������_�̈ӎ��@
�i�A�j�T�}�f�B����o�肵������́A�����I�����̈ӎ����[���ɉ���O�́A䩑R�����Ɓ@�@�@���������Ԃł̈ӎ��@
�@�|�|�|���̓�p�^�|���ł���B
�@�����A�������A�u����v�̊T�O���ƂĂ��L�������A���ẴT�}�f�B�̏�Ԃ����܂߂�A�Ƃ���Ȃ�A�i��ؑ�ٔ��m�̂悤�Ɂj�u����E���S�v��Ԃ��@���̋ɖk�̋��n�ƌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�������A�����͌����Ă��A�T�n�W���E�T�}�f�B�i���X�́j��B�������吹�҂Ɂu�̈ӎ��v�Ƃ��Ắu��̈ӎ��v�������ƌ���̂́A�����������Ƃ͌����Ȃ��B�ڍׂ́A�^�|�Q�T�|�P�O�ȉ��Q�ƁB�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�S�j
�i�C�j�i�u�����̗L�鑶�݁v�ւ́j��ΓI�M���ɂ���
�@�u�^�䁁��䁁�����@�g���^�@�v�ł���u�����L�鑶�݁v�ɑ���u��ΓI�M���v���Ȃ���A�u�䎩�Ɛ��̓����v����Â����A�������邱�Ƃ͌����Ăł��Ȃ��B
�@�u�����L��̑�ȑ��݁v��F�߂āA����ɐ�ΓI�M����u�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�I����ɗ��܂��Ĉ��S���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@����āA�䂪�u���́v�Ŏv�������炵�A�u���Ƃ����悤�v�Ƃ����ł���~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B��������ƁA�u�䎩�Ɛ��̓����v�������ɓ����āA�l�X�ȕs���E�S�z�E�^�O�E�s�����X�����o���ė���悤�ɂȂ�B
�@���������S�̓������~�߂�ɂ́|�|�|�u�����L�鑶�݁v���@���Ɉ̑�ŋ���ł���A�@���Ɋ����ȉb�q�ɖ����Ă��邩�A�ǂ�قnj��O��̔\�͂�L���Ă��邩���X�|�|�|��\�X�iָָ�j���@���|�|�|���u�����Ȃ閳�ׁv�ɔe�����L�遄�i�^�|�Q�|�Q�U�j�|�|�|�Ƃ����^������ڂ���炳�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@���ꂪ�o����A�����Ɓu�����L�鑶�݁v�ւ́u��ΓI�M���v���O���ė���͂��ł���B
�@�u��ΓI�M���v���O���Ă���A���͂ɂ��u��m�b�v�̊��������R�ɒ�~���āu����S�v�̐S���ɂȂ�A�����ƓK�ȍs�ׂ����o���ė���B
�@�z�i���j�̔@���A�u���Ώۂ̓��@��q�v�i�^�|�P�P�|�P�ȉ��j�ɐi�ݍs���u�������W���v�𑱂��čs�����ƂŁA�u�^�̗�q�E���������v�i�^�|�P�Q�|�T�ȉ��j�̌��ʂƂ��Ắu�����Ƃ��Ă̕����v�傳���čs�����Ƃ��K�v�ł���B
�i�u�^�̗�q�v�́u���������v�Ȃ��Ɂu�厀�A�厀�v�ƌ������Ă��ד��Ɋׂ邾���B�j
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�T�j
�i�E�j��̖����n���i��̎哱���̈Ϗ��I�����E��ҁj�ɂ���
�@�i�A�j�́u����Ȃ��[����q�ӎ��v�ƁA�i�C�j�́u��ΓI�M���v�Ɋ�Â����ƂŁA���߂āu��i���]�j�́i�^��ւ́j�����n���������n���������i�T���j���|�T�j�v�𐳂����s�����Ƃ��ł���B
�@�����Œ��ӂ��ׂ��_�́A�u��̕����v�ƌ������A����́A�S�~���̂Ă鎞�̂悤�ɁA���������Ď̂Ă邱�ƈӖ�������̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B
�@�����ł́u�������e�́v�́A�O�������u�����̗L��̑�ȑ��݁v�ɑ����́u���ぁ�Ϗ�����ҁv���Ӗ�����B
�@���M�Ȏ҂́A�u�l���߁v��Ƃ��Ȃ���A�u�O�d�̉�̊ϔO�v�ł���u���遖��ӎ��v���A�����̓��̂��哱���Ă���B�������A���������u�������哱���v��������āA�u�^��v�ɓ��̂̎哱���𖾂��n���A�Ϗ�����̂ł���B
�@����ƁA�䂪�u�^��v�Ɂu�a������v���Ƃɂ��A��̉��l�͔���I�ɑ��傷��B
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�U�j
�@���̌��ۂ́A�y��Ɖ��t�Ƃ�栂��邱�Ƃ��ł���B
�@�ǂ�Ȃɑf���炵���y����A���y�̍˔\�̖����҂����t����Ȃ�A�킵�����F�őt�ł��邱�Ƃ͂Ȃ��B����āA��������L���Ă��Ă���̎�������ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̖��킪�A���y�̋����̎�Ɉς˂��A�K�ɉ��t�����Ȃ�A����͖���{���̃p�t�H�|�}���X�����A�f���炵���P��������n�߂�B
�@����Ɠ��l�ɁA�䂪�u�s���̐^��v�ɑS�ʓI�ɈϏ�����A�哱���̌�オ�ׂ����ƁA��́u�s���̐^��v�́u�����̓���v�i�E�j�Ɉ�ς���B���̎��A��́A���̐g���̂܂܁A�u�s���̐^��v�́u�����}�́v�ɕω�����B�k�����P�U�l
�k�����P�U�|�|�|�A���A�����}�̂Ƃ��Ă̐��\�́A�ꗥ�ɓ����킯�ł͂Ȃ��B���S�Ȗ����n�����������A�u�����̓���Ɖ�������v�������L�����ꍇ�A���ꂼ��̌����}�̂Ƃ��Ă̐��\�ɂ͍��ق�������B���̂Ȃ�A�u�����}�́v�̐��\�����ʗ��̖@���̉��ɂ��邩��ł���B�����炱���A����v�z�����A���v�z�Ɋ�Â����s�ɂ���āA��ق̉ԁi���˔\�j���J�Ԃ����铹�����߂���̂ł���B�^�^�l�l
�@
�@
�i�^�|�Q�R�|�S�V�j
�@�z�i���j�̔@���A�^���ȏC�s�҂́A�u�[����q�ӎ��E��ΓI�M���E��̈Ϗ��v�Ƃ����O�v�����[�����āA�u�������`�̑厀�v���������A����ǂ��u���������o�̖@��v��ʂ蔲���čs���B
�@�Ō�ɁA�{�i�K��Ĉ��|�|�|
�@
�@�@�@�]����@�S���ɂ��i��~���j���@��~���@�@
�@
�@�|�|�|�ȏ�ŁA���@���̔ʎ�|�K�̗�q�ϖ@�̑�Z�i�K�̉�����I������B
�@�@�@�@
�@
|