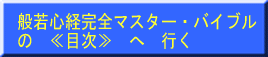【後篇】 「空の奥義」に達する瞑想法
−−−−(別名)大日空王主唯心法界経−−−
「前篇」の内容をマスタ−した方は、「叡智のヨ−ガ」の基礎が出来上がった方です。
そこで、いよいよ後篇では、般若ヨ−ガの「基本から奥義」までを一気に解説して行きます。
『第0章(額縁物語)』(準備中です。)
第一章 般若ヨ−ガの基本
(空−1−1)
よく仏教では「実体性がない」と言われますが、これは「存在性の否定」と同義ではありません。仏教の「無我」は「我の否定」であり、この「我」はア−トマンを指し、ア−トマンの原義は「主体・本体」です(前篇第三章参照)。従って、「ア−トマン」は「根本動因としての主体・本体」又は「主体・本体としての根本動因」を指す言葉だと理解すべきです。(こう考えると、霧が晴れたように分かるでしょう。)
「実体性」は仏教ジャ−ゴン(専門用語)で「自性」とも言います。「実体性・自性」、両者は同義異語です。つまり、「実体性が無い」と言っても「自性が無い」と言っても同じであり、両者とも「根本動因としての本体性(主体性)が無い」ことを意味します。「真の主体」を縮めて「真主体」と言うならば、「実体性が無い」とは「真主体性が無い」と言い換えることもできます。ですから「存在性が無い」というのとは意味が微妙に異なります。
<「実体性の欠如」とは「(本体たる)主(あるじ)の不在性」である>と表現すると良く分かるのではないでしょうか。まことに、「実体性が無い」という意味での「空」は、「我・主体・本体」としての主(あるじ)が「不在であること」を意味する言葉なのです。
(空−1−2)
「叡智のヨ−ガ」は「真の主体」を求め求めて理性(ブッディ)の力で「真の主体」を探究・瞑想して行く「理力行使のヨ−ガ」です。そして、「叡智のヨ−ガ」の中でも「仏法」として分化・特化した「最も強烈な叡智のヨ−ガ」こそが「プラジュニャ−・ヨ−ガ」即ち「般若ヨ−ガ」です。(「プラジュニャ−→パンニャ→般若」の経緯は●●頁、●●頁)
では早速、理性(ブッディ)を駆使する「般若ヨ−ガ」を実践してみましょう。
例えば−−−まず、あなたの右腕に意識を集中します。この右腕はあなたの真の主体と言えるでしょうか? どうですか? 「いいえ、違う」と、あなたの理性は答えるでしょう。
では、両腕の元である「胴体」はあなたの真の主体ですか? これも違うでしょう。
では、心臓は真の主体でしょうか? これも違うでしょう。では、脳味噌は真の主体でしょうか? しかし一体、脳味噌のどの細胞があなたを動かす「根本動因としての本体」なのでしょう? それとも、脳味噌全体、又は、頭部全体こそが、あなたを動かす真の本体なのでしょうか? もしそうならば、あなたは「首から上」それ自体単独でその「本体」を存続させられますか? できないのなら、頭部こそが「あなたの独立した真の主体・本体」だとは言えないでしょう。
では、あなたの意識はどうでしょう? これこそあなたの真の主体でしょうか。しかし、あなたの意識は実に脆弱なもので、眠くなれば朦朧として行き、消えてしまいます。それに、あなたの意識を意識として作動させている根本動因は何でしょう? 食べ物なしに意識を保ち続けられるでしょうか? できないでしょう。そうすると、食べ物こそがあなたの本体なのですか。いいえ、これも違うでしょう。
あなたの意識は、物言わぬ「心臓の鼓動」に支えられて存続しています。また、黙々と血液を浄化・濾過して「尿」を膀胱に送る作業をしている腎臓機能に支えられて、あなたは存続しています。その他、あなたの意識しない無数の素晴らしい人体機能の連繋プレ−によって、あなたの意識は支えられて、存在しています。
では、この素晴らしい人体システムをあなたが構築したのですか? あなたの意識は、自分の人体システムについて無知のまま、このシステムの上の乗っかっているだけではありませんか。ATGCの4種類の塩基配列による遺伝子プログラムの設計図を、あなたの意識が創造した事がありますか。超高層ビルディングの造形を目の前にして、「これは偶然の産物だ」と言い張るのは、実に奇妙であり、無知ではないでしょうか。
(空−1−3)
目を転じて、「風」について見てみましょう。風を風たらしめている「根本の動因」は何でしょう? 地球の自転でしょうか。太陽の光熱でしょうか。
では、地球の自転の根本の動因は何ですか? 太陽の光熱の根本の動因は何ですか。
重力や核力などの宇宙を形成する「四つの力」が有るとしたならば、「四つの力」をそれたらしめている根本の動因は何ですか? また、宇宙のビッグバンを起こさせたその根本の動因は何でしょう?
(空−1−4)
このように、改めて具(つぶさ)にクロ−ズ・アップして検証すると、「これが根本の動因としての本体だ」というものが全然見当たらないでしょう。この事実を仏教は「諸法無我」と表現します。(「諸法無我」は真理命題です。)
根本動因としての本体が見当たらないのにもかかわらず、森羅万象は見事なまでに精妙な法則と秩序を内奥に隠しながら、美しく活動しています。これが老荘思想で言うところの「無為自然」です。「無我の中の無為なる活動」です。
人間も、本来この「美しい無為の流れ」に融合して生きて行くべきではないでしょうか。
この「無為の流れ」に逆行するのが「人間の有為」です。
人間の身体を調べると、そこには「根本動因としての本体」が見当たりません。「無我(=主体なし)」というのが人間の特徴なのです。にもかかわらず、人間は自分の肉体を「主体」だと思い込んで「有為なる活動」をしています。よって、「無為の流れ」に逆行する「有為なる活動」の故に、つまり法則に反する動きの故に、その因果応報で「苦」に見舞われることになるのです。
そして、この因果応報による「苦厄」から脱却するための一つの方法が「仏法」であり、仏法の核心は、人の「有為なる活動」を滅却して行くための「叡智のヨ−ガ」です。
(空−1−5)
「叡智のヨ−ガ」とりわけ仏教に特化した叡智のヨ−ガが「般若ヨ−ガ」ですが、般若ヨ−ガは「意識の方向」を外から内へ、偶像から「真の神」へと転換する技法です。「見聞覚知」「喜怒哀楽」「憤慨・憎悪・落胆」等々の「上辺の私」の「営為」に忙しい時、その人の意識は真我に向いていません。これは丁度、眠っている時には「外界」を意識していないのと同じ、即ち「真我に対して意識が眠っているいる状態」と言えます。
<人は「真我に対して意識が眠っている状態の時」に悪事をする>−−−−− これが法です。
ところが、神聖な渇望心に燃えて「真我たる根本動因としての本体」を求め求めて般若ヨ−ガの「行」を行じると、「相対界の無常な営為」に従事していた自分の物的・肉的な姿が浮き彫りになり、それが「実にくだらないことだ」と感じられるようになります。
そして、「真我への集中度」が増して行くと、今度は逆に「表層の、物的な、外界の事柄に対して意識が眠っている状態」になり、「真我」という「内的な一事」にだけ意識が覚醒している状態になります。
(空−1−6)
尤も、いきなり四六時中、「真我」という「神聖な根本一事」にだけ意識を向け続けることは、凡人には到底不可能な芸当です。よって、焦ることなく、ボディ・ビルの筋力トレ−ニングと同じように、「内なる精神的な筋力」としての「集中力・瞑想力」を一歩一歩確実に向上させるような鍛練法を取るべきです。
では、その具体的な目安を挙げましょう。
毎朝十五分程度、般若ヨ−ガ行をして、「真我」を求め求める瞑想をする習慣付けをしましょう。それが或る程度習慣化したら、次は、夕方(又は晩)にも十五分程度、「真我」も求め求める般若ヨ−ガを行います。(本書の般若心経「真髄和訳」の読誦など)
こうして、朝夕二度の「般若ヨ−ガ行」が習慣化して来たら、今度はお昼にも、十五分程度の「般若ヨ−ガ行」を実践します。
これらが習慣化して来たら、今度は「十五分」を「五分ずつ」延長して行きます。
こうして、朝・昼・夕(晩)、日に三(四)度、三十分ずつ、般若ヨ−ガの瞑想行を行う習慣を身に付けたならば、急速に「煩悩・有為」は止(や)んで行くでしょう。
そうして、十年、二十年、三十年…という長い歳月をかけて、ゆっくりじっくり、般若ヨ−ガの実践に励むべきです。
もしも−−−<謹厳実直に、亀の如き速度で三十年間>−−−この「行」をやり通したならば、物凄い効果が出ることは確実です。ヘタな宗教団体に所属してドタバタとした人生を送るよりも遙かに有意義で、実りの多い霊性修行となること請け合いです。
そればかりか、次の転生にも計り知れないほどの「善い影響」が出て、恵まれた環境に生まれることになるでしょう。
また、もしも、毎日の地道な積み重ねにより「内なる精神的な筋力」即ち「集中力の深さと持続時間」が増大し、「真我への深い集中を連続して八時間ほど保つこと」ができるようになったなら、その時、ニルヴィカルパ・サマディの扉は開かれ、その人は聖者に変容します。
これが「個人の救い」であり、「悟り」というゴ−ルです。
(空−1−7)
般若ヨ−ガは、「四源罪」(前篇第三章第六節参照)の根っこを押さえてしまう手法なので、他のどんな手法よりも強烈・迅速に「悟り」に人を到らしめる瞑想技法です。但し、このヨ−ガを真に深く正しく実践するには、「自性/無自性」概念について、深く正しい理解を持つことが必須です。
そこで、次章以降、「自性/無自性」概念について、詳しく解説して行きます。
(後篇 第一章 終わり)
←←前ページに行く 次ページに行く→→
このページの最終更新日 2003/12/23
著作権について
■ ■ ■ ■ Copyright (c) 2003〜2012 Aomi Ryu All Rights Reserved ■ ■ ■ ■