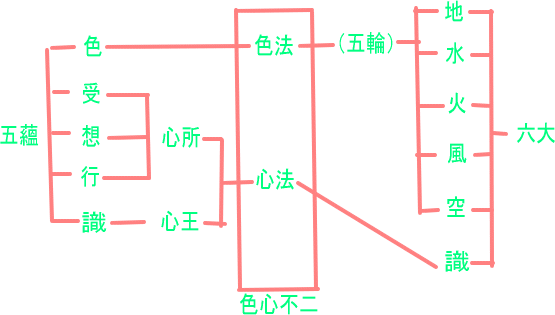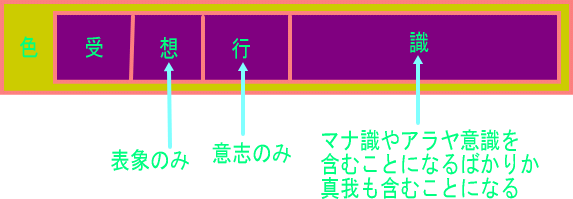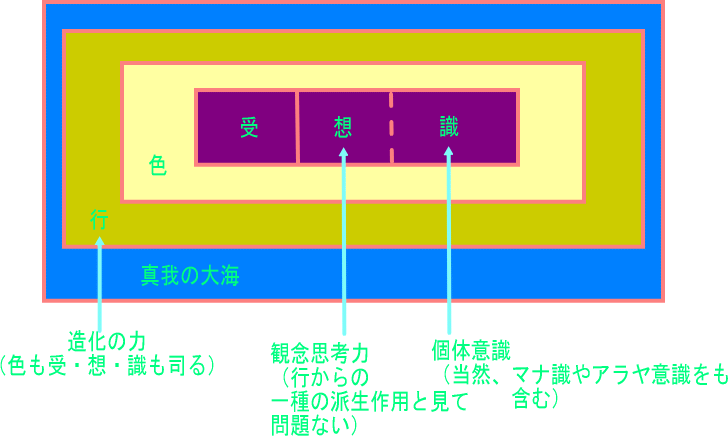亂僗僥僢僾係亃丂慡扨岅傪惓偟偔棟夝偡傞丂乮懕偒乯
乮嬻亅幍亅榋堦乯
乮嘦乯戞擇晹
丂丂乮彮乆挿偄偨傔丄戞擇晹傪峏偵鶣乣鶥偺嶰偮偵暘妱偟偰夝愢偟偰峴偒傑偡丅乯丂
乮鶣乯丂幧棙巕丂怓晄堎嬻丂嬻晄堎怓丅怓懄惀嬻丂嬻懄惀怓丅庴憐峴幆枓暅擛惀丅
乮鶤乯丂幧棙巕丂惀彅朄嬻憡丂晄惗晄柵丂晄岰晄忩丂晄憹晄尭丅
乮鶥乯丂惀屘嬻拞丂柍怓丂柍庴憐峴幆丂柍娽帹旲愩恎堄丅柍怓惡崄枴怗朄丅
丂丂丂丂柍娽奅丂擳帄柍堄幆奅丅柍柍柧丂枓柍柍柧恠丂擳帄柍榁巰丂枓柍榁巰恠丅
丂丂丂丂柍嬯廤柵摴丅柍抭枓柍摼丅
乮嬻亅幍亅榋擇乯
戞擇晹乮嘦乯亅鶣
乲娍栿斉偺斒庒怱宱暥偺榓栿乴
乮僀僴乯丂丂幧棙巕丂怓晄堎嬻丂嬻晄堎怓丅怓懄惀嬻丂嬻懄惀怓丅庴憐峴幆枓暅擛惀丅
丂丂彯丄乽柍帺惈乿偺梡岅傪巊傢偢偵丄夝偒傎偖偟偰栿弌偡傞偲丄師偺傛偆偵側傝傑偡丅
乮偙偙偱偼乯僔儍亅儕僾僩儔傛丄
丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼乽帺惈柍偒傕偺乿偲堎側傜側偄偟丄乽帺惈柍偒傕偺乿偼乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偲堎側傜側偄丅
丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼偙傟懄偪乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傞偟丄乽帺惈柍偒傕偺乿偑偙傟懄偪乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅
丂姶姱偵傛傞報徾偺姶庴乮偺応崌乯傕丄娤擮巚峫椡乮偺応崌乯傕丄乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡乮偺応崌乯傕丄屄懱堄幆乮偺応崌乯傕傑偨丄偙傟偲慡偔摨偠乮帠乯偱偁傞丅
丂
乮偙偙偱偼乯僔儍亅儕亅僾僩儔傛丅
丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼丄偦傟帺懱扨撈偱偼敪惗偡傞椡傕懚懕偡傞椡傕妶摦偡傞椡傕慡偔柍偄傕偺偲乮悺焲傕乯堎側傞傕偺偱偼側偄丅
丂偦傟帺懱扨撈偱偼敪惗偡傞椡傕懚懕偡傞椡傕妶摦偡傞椡傕慡偔柍偄傕偺偼丄乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偲乮悺焲傕乯堎側傞傕偺偱偼側偄丅
丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼丄偙傟懄偪丄偦傟帺懱扨撈偱偼敪惗偡傞椡傕懚懕偡傞椡傕妶摦偡傞椡傕慡偔柍偄傕偺偱偁傞丅傑偨丄偦傟帺懱扨撈偱偼敪惗偡傞椡傕懚懕偡傞椡傕妶摦偡傞椡傕慡偔柍偄傕偺偑丄偙傟懄偪丄乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅
丂姶姱偵傛傞報徾偺姶庴乮偺応崌乯傕丄娤擮巚峫椡乮偺応崌乯傕丄乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡乮偺応崌乯傕丄屄懱堄幆乮偺応崌乯傕傑偨丄偙傟偲慡偔摨偠乮帠乯偱偁傞丅
乮嬻亅幍亅榋嶰乯
丂亅亅亅埲忋偑丄娍栿宱揟偐傜偺榓栿偱偡丅
丂婛偵乽岅媊夝愅俋乿乮嬻亅幍亅屲巐乯偱怗傟偨捠傝丄斒庒怱宱偺娍栿幰偼乽嬻偵嶰媊桳傝乿偲偼擣幆偟偰偍傜偢丄乽嬻亖帺惈柍偒傕偺乿偲丄堦媊揑偵夝偟偰偄偨壜擻惈偑戝偱偡丅
丂偦傟屘丄瀽岅尨暥偼丄乽嬻偺嶰媊乿偵懳墳偟偨乽嶰抜偺揥奐宍乿偵側偭偰偄傞偺偵傕峉傜偢丄娍栿斉偱偼戝抇偵傕偦傟傪堦抜嶍偭偰丄嘆乽怓晄堎嬻乛嬻晄堎怓乿丂嘇乽怓懄惀嬻乛嬻懄惀怓乿偲偄偆乽擇抜傕偺乿偵偟偰偟傑偭偰偄傞傢偗偱偡丅
偟偐偟丄乽嬻偵偼擇枖偼嶰媊偑桳傞乿偺偱偡偐傜丄斒庒怱宱偺偙偺晹暘偼惀旕偲傕乽嶰抜偺揥奐宍乿偲偟偰棟夝偡傞昁梫偑桳傝傑偡丅
丂偦偙偱丄瀽岅尨暥傪師偵嫇偘丄偙傟傪榓栿偟偰峴偒傑偟傚偆丅
丂瀽岅偺惓偟偄斒庒怱宱偼乽嬻偺嶰媊乿偵墳偠偰乽嶰抜揥奐乿偵側偭偰偄傑偡丅
丂
乮嬻亅幍亅榋巐乯
乲瀽岅尨暥偺嶰抜揥奐宍乴丂乮乽嬻偺嶰媊乿丂嬻亅幍亅巐嶲徠乯
乲惓偟偄榓栿乴
乮戞堦抜乯丂儖亅僷儉丂僔儏亅僯儍僞亅丂丂丂丂丂丂亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅丂乮怓惀惈嬻乯
丂丂丂丂丂丂丂僔儏亅僯儍僞亅僀償傽丂儖亅僷儉丂丂丂亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅 乮惈嬻惀怓乯
乮戞擇抜乯丂儖亅僷亅儞丂僫丂僾儕僞僋丂僔儏亅僯儍僞亅丂亅亅亅亅亅亅亅亅丂乮怓晄堎嬻乯
丂丂丂丂丂丂丂僔儏亅僯儍僞亅儎亅丂僫丂僾儕僞僌丂儖亅僷儉丂亅亅亅亅亅亅亅 乮嬻晄堎怓乯
乮戞嶰抜乯丂儎僪丂儖亅僷儉丂僒亅丂僔儏亅僯儍僞亅丂亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅 乮怓懄惀嬻乯
丂丂丂丂丂丂丂儎亅丂僔儏亅僯儍僞亅丂僞僪丂儖亅僷儉丂亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅 乮嬻懄惀怓乯
丂
乮戞堦抜乯
丂丒乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傞丅丂丂亅亅亅亅亅乮怓惀惈嬻乯
丂丒乽帺惈柍偒傕偺乿偑丄幚偵乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅丂丂亅亅丂乮惈嬻惀怓乯
乮戞擇抜乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丒乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼丄乽戝擔嬻墹庡乿偺憡懳奅曄壔憡偲丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂堎側傞傕偺偱偼側偄丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亅亅亅亅亅亅丂丂乮怓晄堎嬻乯
丂丒乽戝擔嬻墹庡乿偺憡懳奅曄壔憡偲堎側傞傕偺偱偼側偄傕偺偑丄丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂亅亅亅亅亅亅丂乮嬻晄堎怓乯
乮戞嶰抜乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丒乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼丄乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傝側偑傜摨帪偵丄丂丂丂丂丂
丂丂丂丂乽乮帺惈桳傞乯戝擔嬻墹庡乿偺愨懳奅柍憡朄恎偱傕偁傞丅亅亅亅亅丂乮怓懄惀嬻乯
丂丒乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傝側偑傜摨帪偵丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂乽乮帺惈桳傞乯戝擔嬻墹庡乿偺愨懳奅柍憡朄恎偱傕偁傞傕偺偑丄丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亅亅亅亅亅丂乮嬻懄惀怓乯
丂
乮嬻亅幍亅榋屲乯
戞擇晹乮嘦乯亅鶣丂乲恀悜榓栿乴丂乮撉鎢梡乯
丂
丂僔儍亅儕僾僩儔傛丅偙偙偱偼丄
丂丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傞丅乽帺惈柍偒傕偺乿偑幚偵乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅乮偦偟偰傑偨乯
丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼乽戝擔嬻墹庡偺憡懳奅曄壔憡乿偲堎側傞傕偺偱偼側偄丅
丂乽戝擔嬻墹庡偺憡懳奅曄壔憡乿偲乮壗傜乯堎側傜側偄傕偺偑乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅乮偦偟偰傑偨乯
丂乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼丄乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傝側偑傜摨帪偵乽乮帺惈桳傞乯戝擔嬻墹庡偺愨懳奅柍憡朄恎乿偱傕偁傞丅乽帺惈柍偒傕偺乿偱偁傝側偑傜摨帪偵乽乮帺惈桳傞乯戝擔嬻墹庡偺愨懳奅柍憡朄恎乿偱傕偁傞傕偺偑丄乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偱偁傞丅
丂姶姱偵傛傞報徾偺姶庴乮偺応崌乯傕丄娤擮巚峫椡乮偺応崌乯傕丄乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡乮偺応崌乯傕丄屄懱堄幆乮偺応崌乯傕丄慡偔摨偠乮帠乯偱偁傞丅
丂
乮嬻亅幍亅榋榋乯
亙岅媊夝愅亜丂
戞擇晹乮嘦乯亅鶣丂
乲尨暥偺乴僀僴乮11乯丂丂幧棙巕乮12乯丂丂怓乮13乯晄堎嬻丂丂嬻晄堎怓丅丂怓懄惀嬻丂丂嬻懄惀怓丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庴乮14乯丂憐乮15乯丂峴乮16乯丂幆乮17乯丂枓暅擛惀乮18乯丅
乮嬻亅幍亅榋幍乯
乮11乯丂僀僴
丂乽崯張偱偼丄崯偺悽偵偍偄偰偼乿偺堄枴丅尨暥偱偼乽僀僴丄僔儍亅儕僾僩儔乿偲丄幧棙巕偺慜偵抲偐傟偰偄傑偡丅娾攇暥屔斉偱偼乽偙偺悽偵偍偄偰偼乿偲榓栿偝傟偰偄傑偡偑丄乽怓懄惀嬻乿偲偄偆晛曊恀棟偼抧媴忋偵尷傜傟偨帠偱偼偁傝傑偣傫両丂偁偺悽偱傕丄嶰愮戝愮悽奅偱傕捠梡偡傞恀棟側偺偱偡丅
丂傛偭偰丄乽僀僴乿傪乽偙偺悽乿偵尷掕偡傞栿暥偼懨摉偱偼偁傝傑偣傫丅巰屻丄楈奅偱斒庒儓亅僈偺峴傪偡傞偙偲傕廫暘壜擻側偺偱偡偐傜丄乽僀僴乿偼乽峴幰偺娽慜偺悽奅乿偺堄枴偵夝偡傋偒偱偡丅廬偭偰丄扨弮偵乽偙偙偱偼乿偲栿偡傋偒偱偟傚偆丅
丂彯丄乽恀悜榓栿乿偱偼乽僔儍亅儕僾僩儔傛丅偙偙偱偼乿偲偟偰丄瀽岅尨暥偲弴斣偑媡偵側偭偰偄傑偡丅偙傟偼丄楴鎢廳帇偺娤揰偐傜丄擔杮岅偺暥宆偵崌傢偣偨偨傔偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅榋敧乯
乮12乯丂幧棙巕
丂庍懜偺掜巕僔儍亅儕僾僩儔偺娍栿偱偡丅僔儍亅儕傪壒幨偟偰乽幧棙乿丅僾僩儔偼乽巕嫙乿偺堄枴側偺偱乽巕乿偲偟偰丄壒幨偲東栿傪崿崌偟偨娍栿偱偡丅
丂庍懜偺掜巕拞丄抦宐戞堦偲梍傟崅偄僔儍亅儕僾僩儔偵丄娤帺嵼曥嶧偑愢朄偟偰偄傞愝掕偱偡丅僔儍亅儕僾僩儔偼抦宐戞堦偱偟偨偑丄枹偩乽懐変乿傪挻墇偟偰偼偄側偄偑屘偵丄戝屽偵摓傟側偄傑傑偱嫃傑偟偨丅斵偺傛偆偵丄抦宐偵偼挿偗偰偼偄傞傕偺偺丄乽懐変乿傪蹇偐偟偰偟傑偆応崌丄偦傟偼帺偢偲乽彫尗偟偄抦宐亖嗦抭乿偵懧偟偰偟傑偆婋尟傪泂傫偱偄傑偡丅
丂偦傟屘丄僔儍亅儕僾僩儔偑乽懐変偺榞撪偵棷傑偭偰偄傞彫尗偟偄抦宐傪幪偰嫀偭偰亀姰慡媶嬌塨抭亁偵寢崌丒杤擖丒婣擖偱偒傞傛偆偵乿偲丄娤帺嵼曥嶧偑恊偟偔乽恀偺塨抭乿傪庼偗偰偄傞応柺偲偄偆晳戜愝掕偱偡丅
丂偦傕偦傕丄斒庒儓亅僈偼丄忋崻偺幰丄忋媺幰偺儓亅僈偲埵抲晅偗傜傟傑偡丅壗屘側傜丄偙偺儓亅僈偼楈惈廋峴偺拞偱丄嵟傕崅搙丒惛柇側傕偺偩偐傜偱偡丅杮摉偵偙傟傪怺偔幚慔偱偒傟偽丄懄恎惉暓乮亖僯儖償傿僇儖僷丒僒儅僨傿傊偺擖掕乯乮慜曆戞屲復嶲徠乯傪払惉偱偒傑偡丅
丂亅亅亅偱偼丄斒庒儓亅僈傪乽拞崻偺幰乿偑幚慔偡傞偙偲偼偱偒傞偱偟傚偆偐丠
丂栜榑丄拞崻偺恖偑乽斒庒怱宱乿傪撉鎢偟偰埆偄偙偲偼堦偮傕偁傝傑偣傫丅岠壥揑側廋峴朄偵側傝傑偡丅偟偐偟丄拞崻偺恖偼丄廤拞椡偑晄廩暘偱偁傝丄撪揑嬝椡乮仛堦亅廫亅嶰廫仛乯偑庛偄偺偱丄偳偆偟偰傕斚擸偵傛偭偰堄幆偑嶶棎偟偰偟傑偄丄巚偆傛偆偵斒庒儓亅僈偵廤拞偱偒側偄偼偢偱偡丅偲偼偄偊丄帺暘偺乮楈揑乯廤拞椡晄懌傪帺妎偟丄尓嫊偵偦偺岦忋偵搘傔傞側傜偽丄忩壔偺懍搙傕帺偢偲懍傑偭偰峴偒傑偡丅曽朄偼嵟崅偵惓偟偄偺偱偡偐傜丅
丂亅亅亅偱偼丄偙傟傪乽壓崻偺幰乿偑幚慔偡傞偙偲偼偱偒傞偱偟傚偆偐丠
丂壓崻偺恖偼丄斚擸偺夣妝偵怱扗傢傟偰偍傝丄乽撦廳側攇摦乿偲乽戺偭偨堄幆乿傪帩偭偰偄傞偺偱丄恄惞側帠暱偵懳偟偰丄婎杮揑偵偼乽嫅愨斀墳傪書偔乿傕偺偱偡丅傛偭偰丄乽斒庒怱宱乿傪撉鎢偡傞婥偵側傜偢丄柍棟偵撉鎢偡傞側傜偦傟偼嬯捝偵姶偠丄偝偭傁傝摢偵擖傜偢丄暥復偺拞恎傪攃埇偡傞偙偲傕丄偦偺堄枴偵廤拞偡傞偙偲傕偱偒側偄偱偟傚偆丅廬偭偰丄壵棫偮偽偐傝偱丄掱側偔乽怱宱乿傪搳偘幪偰傞偟偐側偄偱偟傚偆丅廬偭偰丄懠偺扨弮側儅儞僩儔峴側偳丄懠偺庤抜傪島偠傞傋偒偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅榋嬨乯
乮13乯丂怓
丂儖亅僷偺娍栿岅偑乽怓乿偱偡丅儖亅僷偼丄晛捠偼乽暔幙乿傪堄枴偟傑偡偑丄尩枾偵偼丄傕偭偲峀偄奣擮偱偡丅暔幙揑偲尵偊傞乽桳宍側傞傕偺慡斒乿傪娷傓奣擮偱偡丅
丂暿尵偡傞偲乽暔偲宍乿傪娷傔偨奣擮偱偡丅塮憸傕梲墛傕僆亅儘儔傕柌傕乽宍桳傞傕偺乿側偺偱丄儖亅僷偵娷傑傟傑偡丅傑偨丄乽嬻婥乿偼栚偵尒偊傑偣傫偑丄晽偺掞峈摍偺怗姶偱乽暔偑桳傞乿偲暘偐傞偺偱丄儖亅僷偵娷傑傟傑偡丅乮柍榑丄朄懃側偳偺棟朄偼娷傑側偄丅乯
丂偙偆峫偊偰峴偔偲丄乽暔乿偲偼壗偐丄栤戣偲側傝傑偡丅
丂尰戙暔棟妛偱偼丄乽暔幙偲偼壗偐乿偲偄偆媈栤傪撍偒媗傔偰丄乽暔幙偺慺乿傑偱扝傝拝偙偆偲偟偰偄傑偡丅嵟弶偼乽尨巕乿傪敪尒偟偰偙傟偑乽暔幙偺慺乿偩偲巚偄傑偟偨偑丄嵍偵旕偢丅偙傟偼乽揹巕丒梲巕丒拞惈巕乿偵暘夝偱偒丄偙傟傕峏偵暘夝偱偒丄乽梲巕丒拞惈巕乿偼昐庬椶埲忋偺僴僪儘儞乮嫮棻巕懓乯偵暘夝偱偒丄乽僴僪儘儞乿偼峏偵僶儕僆儞乮廳棻巕孮乯偲儊僜儞乮拞娫巕亖寉棻巕孮乯偵暘夝偱偒丄偦傟傕峏偵丄傾僢僾丒僟僂儞丒僗僩儗儞僕側偳悢庬椶偺僋僅亅僋偵傑偱暘夝偱偒傞偟丄偦偺懠丄揹巕丒儈儏亅棻巕丒僯儏亅僩儕僲側偳偺儗僾僩儞乮寉棻巕懓乯傕懚嵼偡傞丄偲暘偐偭偰棃傑偟偨丅乮媫懍側恑曕偱偡丅乯
丂偦傟偽偐傝偐丄揹帴椡傗廳椡傗妀椡傗庛偄椡側偳偺乽巐偮偺椡乿傪乽攠夘偡傞棻巕乿偲偟偰丄岝巕丄僌儔價僩儞丄僌亅儖僆儞丄僂傿亅僋儃僜儞側偳偺懚嵼偑岅傜傟傑偡丅
丂偮傑傝丄乽怓乿偵擖傜側偄偲巚傢傟偰偄偨廳椡側偳偑丄幚偼乽怓乿偵擖傞丄偲暘偐偭偰棃偨傢偗偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅幍廫乯
丂偟偐偟丄斒庒怱宱偺夝庍忋丄栤戣偲側傞偺偼丄暔棟妛偱偼側偔丄偙偙偱巊傢傟偰偄傞乽儖亅僷乮怓乯乿傪乽屲錧偺榞撪乿偵尷掕偟偰撉傓偐斲偐丄偲偄偆崙岅忋偺栤戣偱偡丅
丂乽屲錧偺榞撪尷掕愢乿傪嵦傞側傜偽丄乽屲錧亖屄変亖擏懱恎乿側偺偱乽偙偙偱偺儖亅僷乿偼乽擏懱傪宍嶌偭偰偄傞暔幙慡斒乿偩偗偵尷傜傟傞偙偲偵側傝傑偡丅
丂乽恀悜榓栿乿乮嬻亅幍亅榋屲乯偱偼亅亅亅亙乮屄変傪宍嶌偭偰偄傞乯暔幙偼亜亅亅亅偲栿弌偟偰偄傞傛偆偵丄偙偺乽屲錧偺榞撪尷掕愢乿偑惓夝偱偡丅
丂丂
乮嬻亅幍亅幍堦乯
丂堦曽丄乽屲錧偺榞傪庢傝暐偭偨堦斒柦戣愢乿傪嵦傞側傜偽丄偙偙偱偺乽儖亅僷乮怓乯乿偼慡悽奅丒慡塅拡丒嶰愮戝愮悽奅偺乽暔偲宍偲塮憸乿慡晹傪幩掱偵擖傟偨奣擮偲峫偊傞偙偲偵側傝傑偡丅娾攇暥屔斉偱偼偙偙偱偺乽儖亅僷乿傪乽偍傛偦暔幙揑尰徾偼乣乿偲榓栿偟偰偄傞偺偱丄傑偝偟偔偙偙偱偺乽怓乿傪堦斒柦戣偲偟偰夝庍偟偰偄傑偡丅
丂偟偐偟丄乽屲錧乿偺夝愢乮乽岅媊夝愅俉乿嬻亅幍亅屲廫乯偱傕柧傜偐偵偟偨捠傝丄愭偢嵟弶偵亅亅亅亙乽屲錧亖屄変乿傪宍嶌偭偰偄傞暔幙孮憤偰偼柍帺惈側傝亜亅亅亅偲娕攋偡傞偺偑丄惓偟偄弴彉偱偡丅偙偺抜奒傪摜傑偢偵丄偄偒側傝乽朄柍変亖彅朄柍帺惈乿傪娕攋偟偨丄偲愰尵偟偨傜塕偵側傝傑偡丅
丂暥柆傪尒偰傕丄屻偵乽庴憐峴幆乿偑棃偰偄傞偺偩偐傜丄偙偺乽怓乿偑乽屲錧偺堦偮乿偲偟偰岅傜傟偰偄傞偺偼丄壩傪尒傞傛傝柧傜偐側帠偱偡丅
丂偱偼丄暓嫵妛幰偨偪偼丄壗屘偙偙偺乽儖亅僷乮怓乯乿傪乽堦斒柦戣乿偲偟偰栿偡偺偱偟傚偆偐丠
丂偦傟偼丄乽怓懄惀嬻乿偲偄偆堦愡偩偗偑庢傝弌偝傟偰丄偙偺巐暥帤偑扨撈偱梡偄傜傟傞偙偲偑懡偄偐傜偱偡丅妋偐偵丄乽怓懄惀嬻乛嬻懄惀怓乿偺懳嬪偩偗庢傝弌偡側傜偽丄乽堦斒揑恀棟柦戣乿偲偟偰丄偙偺乽怓乿傪堦斒壔偟偰夝庍偟偰椙偄偟丄偦偆偡傋偒偱偟傚偆丅
丂偟偐偟丄傂偲搙乽斒庒怱宱乿偺暥柆偺棳傟偺拞偵慻傒崬傑傟偨側傜偽丄慜屻偺暥柆偵傛偭偰乽堄枴偑尷掕偝傟傞乿偺偼梋傝偵傕摉慠偺帠偩偲尵偊傑偡丅
丂偙偺堦愡偩偗丄乽堦斒揑恀棟柦戣乿傪弎傋偰偄傞丄偲嫮曎偟偰丄尐偵椡傪擖傟偰栿偡偺偼戝娫堘偄偱偡丅暥柆傪柍帇偟偨堎忢峴摦偲尵偊傑偟傚偆丅
丂亅亅亅埲忋丄偙偙偱偺乽怓乿偼丄乽屲錧亖屄変乿偺榞撪偺乽怓乿偺堄枴偱偡丅
丂廬偭偰丄偙偙偱偺乽怓乿偼丄乽屄変傪宍嶌偭偰偄傞暔幙乿偲栿偡偺偑揔愗偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅幍擇乯
乮14乯丂庴
丂償僃亅僟僫亅偺娍栿偱偡丅屄変乮屲錧乯偺屲偮偺姶妎婍姱乮亖帇妎丒挳妎丒歬妎丒枴妎丒怗妎乯乮亖姶姱乯傪捠偟偰丄乮嬯丒妝丒晄嬯丒晄妝側偳彅庬偺乯乽報徾乿傪庴偗傞偙偲乮亖庴偗傞嶌梡偺乯偙偲偱偡丅娾攇暥屔斉偼乽姶妎乿偲榓栿偟偰偄傑偡丅
丂偟偐偟丄乮嬻亅幍亅榋屲偺乯乽恀悜榓栿乿偱偼亅亅亅亙姶姱偵傛傞報徾偺姶庴亜亅亅亅偲栿偟偰偄傑偡丅棟桼偼師偺捠傝偱偡丅
丂扨偵乽姶妎乿偲栿偡偲丄奜奅偐傜偺巋寖傪姶偠傞摥偒慡斒傪娷傓帠偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偟偐偟丄暓嫵偼晹攈暓嫵埲棃丄偙偺曈偵娭偟偰偼旝柇丒惛柇側嬫暿傪偟偰丄慇嵶側偙偩傢傝傪尒偣偰偄傑偡丅
丂嬶懱揑偵偼丄廫擇場墢偺乮戞榋巟乯乽怗乿傪丄乽庴乿偺堦曕庤慜偺抜奒偲懆偊偰丄姶妎婍姱偑奜奅偲愙怗偟丄偦傟傪抦妎偡傞偙偲傪乽怗乿偲屇傫偱偄傑偡丅偦偟偰丄師偺廫擇場墢偺乮戞幍巟乯乽庴乿傪丄乽怗乿傪尨場偲偟偨乽師偺嶌梡乿懄偪丄姶妎婍姱偑奜奅偲愙怗偟丄偦傟傪抦妎偟偨偙偲偱庴偗傞報徾偺姶庴傪乽庴乿偲屇傫偱偄傑偡丅偦偟偰丄偦偺姶庴偟偨報徾傪尨場偲偟偨乽師偺嶌梡乿偱丄岲偒丒寵偄摍偺岲傒偑宍惉偝傟丄偙傟傪乽垽乿乮戞敧巟乯偲屇傫偱偄傞偺偱偡丅乮徻嵶偼乽岅媊夝愅31乿嬻亅幍亅仛昐榋廫巐埲壓仛乯
丂偮傑傝丄乽巋寖偵懳偡傞岲傒偺慖暿堄幆乮亖垽乯乿偑摥偔埲慜偺嶌梡偱丄彯妿偮丄奜奅偲姶妎婍姱偑愙怗偡傞乽扨側傞暔棟揑丒尨弶揑側抦妎嶌梡乮亖怗乯乿傪娷傑偢偵丄偦偺屻偺嶌梡傪乽庴乿偲屇傇傢偗偱偡丅
丂傛偭偰丄奜奅偐傜偺巋寖慡斒傪娷傓乽姶妎乿偲偄偆栿偼峀偒偵幐偟偰偄傞丄偲尵偊傑偡丅壛偊偰丄尰戙偱偼乽暈偺僙儞僗乮姶妎乯偑椙偄乿側偳尵偆梡朄傕桳傞偺偱丄乽姶妎乿偺岅傪巊偆偲丄擇廳偺堄枴偱峀偒偵幐偟丄晄揔愗偱偡丅
丂廬偭偰丄乽姶妎婍姱傪捠偟偰報徾傪姶庴偡傞偙偲乮嶌梡乯乿丄棯偟偰乽姶姱偵傛傞報徾偺姶庴乮嶌梡乯乿偲栿偡偺偑憡摉偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅幍嶰乯
丂栟傕丄乽偳偺摴丄屲錧偺慡晹傪柍帺惈乿偲巃傝幪偰傞偺偩偐傜丄偦偺乽斲掕乿偼峀偄曽偑揙掙揑斲掕偲尵偊傞偐傜丄乽姶妎乿偲偄偆栿偺曽偑椙偄丄偲偄偆堄尒傕偁傞偱偟傚偆丅
丂偟偐偟丄廳梫側偺偼丄斒庒儓亅僈偺幚慔偱偡丅乽姶妎偵偼帺惈偑柍偄乿偲偄偆応崌偲乽姶姱偵傛傞報徾偺姶庴偵偼帺惈偑柍偄乿偲尵偆偺偱偼丄尵楈偺揰偱岠壥偑堘偄傑偡丅
丂敊慠偲偟偨斲掕傛傝傕丄峣傝崬傫偩斲掕偺曽偑嫮偄岠壥偑桳傝傑偡丅
丂
丂彯丄乽姶姱偵傛傞報徾偺姶庴乿偼乮彮偟嵱偄偨昞尰偱乯乽亀夣乛晄夣亁偺姶庴乿偲尵偭偰傕堄枴揑偵偼戝懱摨偠偱偡丅傛偭偰亅亅亅亙乽夣乛晄夣乿偺姶庴亜亅亅亅偲尵偭偨曽偑擛幚偵僀儊亅僕偱偒傞恖偼丄偙偺尵偄曽傪巊偭偰乽峴乿偠偰傕戝夁側偄偱偟傚偆丅
丂
乮嬻亅幍亅幍巐乯
乮15乯丂憐
丂僒儞僕儏僯儍亅偺娍栿偱偡丅僕儏僯儍亅乮抦傞乯偲偄偆摦帉偵僒儞偲偄偆愙摢帿傪晅偟偨彈惈柤帉偱偡丅僒儞偵偼乽廫慡偵乿偲偄偆堄枴傕偁傝傑偡偑丄偙偺応崌偼乽崌偆乿偲偐乽堦弿偵丒嫟偵乿偲偄偆堄枴偱偡丅乽柤憐乿偲偄偆娍栿偑恀媊偵嬤偄偱偟傚偆丅
丂暓嫵帿揟偺亀憐亁偺崁偱偼丄乽堄幆丄擣幆丄棟夝丄椆抦丄娤擮丄昞徾乿側偳偲愢柧偝傟偰偄傑偡偑丄乽堄幆乿偲尵偭偨傜娫堘偄偱偡丅乮乽岅媊夝愅17丏幆乿嬻亅幍亅仛昐幍埲壓乯
丂娾攇暥屔斉偱偼乽昞徾乿偲榓栿偟偰偄傑偡丅偟偐偟丄乮嬻亅幍亅榋屲偺乯乽恀悜榓栿乿偱偼亅亅亅亙娤擮巚峫椡亜亅亅亅偲栿弌偟偰偄傑偡丅棟桼偼師偺捠傝偱偡丅
丂愭偢丄乽昞徾乿偲偄偆尵梩帺懱偑暘偐傝偵偔偄偺偱丄嵋憐朄偱巊梡偡傞尵梩偵偦偖傢側偄丄偲偄偆帠偑嫇偘傜傟傑偡丅揘妛梡岅傪柍棟偵棟夝偟傛偆偲偟偰傕丄寢嬊惉岟偣偢偵丄儅僀儞僪偺媃榑乮偗傠傫乯偵娮傞婋尟惈偑嬌傔偰戝偩偲尵偊傑偡丅傑偨丄乽昞徾乿偵偼乽奜揑側僔儞儃儖乮徾挜暔乯乿偺堄枴傕桳傞偺偱丄偙偆偟偨乽暿偺堄枴乿傪傕娷傓擄夝岅傪懺乆乮傢偞傢偞乯巊偆偵偼丄偦傟側傝偺乽懠偵戙傢傝摼側偄嫮偄棟桼乿偑昁梫偱偡偑丄偦傫側傕偺偼堦偮傕側偄丄偲尵偊傑偡丅
丂傛偭偰丄乽怱宱乿偺僒儞僕儏僯儍亅傪乽昞徾乿偲栿偡傋偒偱偼偁傝傑偣傫丅
丂
乮嬻亅幍亅幍屲乯
丂乽怱宱乿偺僒儞僕儏僯儍亅偼丄償僃亅僟僫亅乮乽庴乿亖姶姱偵傛傞報徾偺姶庴乯偺屻偵棃傞傕偺偱偡丅偮傑傝丄屲姶偱乽怗丒庴乿偟偨偙偲傪尨場偲偟偰丄乽偦傟偵崌傢偣偰丄偦傟偲嫟偵乮亖僒儞乯抦傞偙偲乮亖僕儏僯儍亅乯乿傪堄枴偟傑偡丅偮傑傝丄岅尮揑偵偼亅亅亅
亙乽庴乿偵傛偭偰宍嶌傜傟偨乽娤擮乿亜亅亅亅傪堄枴偡傞傢偗偱偡丅
乮場傒偵丄嶰廳嬯偺僿儗儞丒働儔亅偼丄挶乆傪尒側偄傑傑偵栍栚偵側傝傑偟偨偑丄挶乆偺娤擮傪帩偭偰偄傑偟偨丅壗屘側傜丄桯懱棧扙偟偰嶰廳嬯偐傜夝曻偝傟丄偍壴敤偺挶乆傪幚嵺偵乽尒偨乿偐傜偱偡丅偙傟偼斵彈偑帺揱偵婰偟偰偄傞帠偱偡丅偙偺傛偆偵乽庴乿偼丄擏懱恎偺偦傟偵尷傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅乯
丂偟偐偟丄乽娤擮乿偼乽奜奅偲偺愙怗乿偵傛傞乽忣曬偺僀儞僾僢僩乮擖椡乯乿偩偗偱惉棫偡傞傕偺偲傕尵偊傑偣傫丅偦偆偟偨摼偨忣曬傪乽摢偺拞乿偱乽漵偹孞傝夞偡巚峫嶌梡乿偺寢壥丄怴偨偵嶌傜傟崅傔傜傟偨乽巚擮乿傕乽娤擮乿偲尵偊傑偡丅
丂偙偺傛偆偵摯嶡偟偰峴偔偲丄偦傕偦傕乽娤擮乿偲偼壗偐丄栤戣偵側傝傑偡丅
丂僨僇儖僩偼乽変巚偆丅屘偵変桳傝乿偲尵偄丄乽帺変偺娤擮乿偼乽巚峫偺嶻暔乿偱偁傞丄偲摯嶡偟傑偟偨丅傑偙偲偵偦偺捠傝偱丄乽娤擮乿偲乽巚峫嶌梡乿偼晄壜暘偺傕偺偱偡丅
丂傛偭偰丄乽僒儞僕儏僯儍亅乿偺杮幙傪尵偄摉偰偨榓栿偲偟偰偼丄乽娤擮乮巚擮乯偲巚峫嶌梡乮椡乯乿傪懄嵗偵憐婲偱偒傞尵梩偑椙偄偲尵偊傑偡丅偦偙偱亅亅亅亙娤擮巚峫椡亜亅亅亅偲偄偆尵梩乮怴偟偄憿岅乯偵側偭偨傢偗偱偡丅
乲斒庒儓亅僈嵋憐峴偵偍偄偰丄乽娤擮巚峫椡偵偼帺惈偑柍偄乿偲偄偆乽尵楈乿偼幚偵嫮椡偱偡丅乽昞徾偵帺惈偑柍偄乿偲昐枩曊彞偊偰傕杦偳壗傕婲偙傜側偄偺偲斾妑偡傟偽丄偙偺乽榓栿乿偑擛壗偵妀怱傪撍偄偰偄傞偐暘偐傞偱偟傚偆丅
丂傑偨丄乽娤擮巚峫椡乿偲擣幆偡傞偲丄僒儞僕儏僯儍亅偺乽僒儞乿偵偼丄峏偵怺偄堄枴偑塀偝傟偰偄偨偙偲傪抦傞偙偲偵側傝傑偡丅懄偪丄乽娤擮巚峫椡乿偼乽柍帺惈乿側偺偱乽帺椡乿偱摥偔傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅戝擔嬻墹庡偺屼椡偑桳偭偰丄巒傔偰摥偔嶌梡偲尵偊傑偡丅
丂乽庡偺屼椡偱丄庡偲嫟偵乮僒儞乯抦傞偙偲乮僕儏僯儍亅乯乿亅亅亅偙傟偧丄僒儞僕儏僯儍亅乮娤擮巚峫椡乯偩偲傕尵偊傞傢偗偱偡丅乴
丂
乮嬻亅幍亅幍榋乯
乮16乯丂峴
丂僒儞僗僇亅儔偺娍栿偱偡丅廬棃丄乽峴乿偺栿偲偟偰偼乽堄巙丄宍惉椡乿側偳偺栿岅偑採埬偝傟偰偄傑偡丅娾攇暥屔斉偼乽堄巙乿偲榓栿偟偰偄傑偡乮彯丄乽堄巙揑宍惉椡乿偲偡傟偽峏偵恀媊偵嬤偯偔偲偺拹偑晅偝傟偰偄傑偡乯丅
丂偟偐偟丄乮嬻亅幍亅榋屲偺乯乽恀悜榓栿乿偱偼亅亅亅
亙乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡亜亅亅亅偲栿弌偟偰偄傑偡丅棟桼偼師偺捠傝偱偡丅
丂僒儞偼丄乽堦弿偵丒棫攈乮廫慡乯偵乿側偳傪堄枴偡傞愙摢帿丅僗僇亅儔偼乽摦帉僇儔丂丂乮嶌傞丄堊偡丄宍惉偡傞丄峔惉偡傞丄惉廇偝偣傞丄幚峴丒棜峴偡傞丄尠偡丄帵偡丄摍乆乯乿偺柤帉宍偱偡丅乮愙摢帿僒儞偲寢崌偡傞偲丄娫偵乽僗乿偑擖傞乯
丂偙傟偱暘偐傞捠傝丄僒儞僗僇亅儔偼偲偰傕懡媊揑偱峀偄奣擮偱偡偑丄偙偺尵梩偑巜偟帵偡偦偺惛悜偼亅亅亅亙乽埥傞庬偺姰惉宍乿偵岦偐偆乽憿惉偺摦偒乿亜亅亅亅偲尵偊傑偡丅
丂椺偊偽丄怉暔傪惗挿偝偣傞傕偺乮椡乯傕丄壴傪嶇偐偣丄幚傪惉傜偣傞椡傕丄摦暔偺嶻棏傗弌嶻傗惉挿傪巌傞椡傕丄憤偰僒儞僗僇亅儔偲尵偊傑偡丅
丂傑偨丄斒庒怱宱偺乽屲錧乮恖娫偺屄変乯乿偺榞撪偵尷掕偟偨堄枴偺僒儞僗僇亅儔偱傕丄恖偺恎挿傪怢偽偡椡傕丄敮偺栄傪惗傗偡椡傕丄嶤傝彎傪帺慠帯桙偝偣傞椡傕奆丄僒儞僗僇亅儔偲尵偊傑偡丅
丂傑偨丄塣摦慖庤偑嬝擏傪晅偗傛偆偲偟偰乽嬝僩儗乿偡傞応崌丄乽嬝僩儗偟傛偆乿偲偡傞堄巙丒堄梸傕僒儞僗僇亅儔偱偁傝丄傑偨丄嬝僩儗偺巋寖傪庴偗偰丄懝彎偟偨嬝擏慇堐傪慜傛傝乽懢偔偡傞乿傛偆偵摥偔惗懱嶌梡傕僒儞僗僇亅儔偱偡丅傑偨丄彈惈偑擠怭偟偨嵺偵丄偦偺戀帣傪擔偵擔偵惉挿偝偣傞嶌梡傕僒儞僗僇亅儔偱偡丅
丂偙偺傛偆偵嬶偵尒偰棃傞偲丄僒儞僗僇亅儔傪乽堄巙乿偲偐乽堄巙揑宍惉椡乿偲栿偡偺偼丄嫹偒偵幐偟偰晄揔愗偩偲暘偐傞偱偟傚偆丅偟偐偟丄偦偆偐偲尵偭偰丄乽宍惉椡乿偲尵偆偩偗偱偼拪徾揑夁偓偰丄壗偐敊慠偲偟夁偓丄僺儞偲棃側偄偱偟傚偆丅偱偼丄偳偆栿偡偐丅
丂崱尒偨捠傝丄僒儞僗僇亅儔偺杮幙偼丄堄梸柺丄媦傃丄惗懱柺偱偺乽埥傞庬偺惉廇丄枖偼姰惉宍偵岦偐偆憿惉偺摦偒乿偱偡丅
丂傛偭偰亅亅亅亙乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡亜亅亅亅偲偄偆栿岅偵側傞傢偗偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅幍幍乯
丂偙傟偱暘偐傞捠傝丄乽僒儞僗僇亅儔乿偺乽僒儞乿偼乽棫攈偵丄廫慡偵乿偺堄枴偱偁傝丄塸岅偺乽僼儖乮full乯乿偵摉偨傞堄枴偱偡丅乽堦弿偵丄嫟偵乿偺堄枴偱偼偁傝傑偣傫丅
丂偦偟偰丄惉廇乮姰惉乯偟偨傕偺偑乽曵夡乿偟偰峴偔偙偲傪僒儞僗僇亅儔偲偼尵偄傑偣傫丅乽姰惉暔偺曵夡尰徾乿偼乽僒儞僗僇亅儔偺掆巭丒徚柵乿傪堄枴偡傞偲棟夝偝傟傑偡丅
丂偙偺揰偺擣幆偼乮屻弎偡傞乽彅峴柍忢乿傪棟夝偡傞忋偱乯偲偰傕廳梫偱偡丅
丂椺偊偽丄撁偘摢偵側偭偨恖偼丄敮偺栄傪嶌傞乽栄崻乿偱婡擻偡傞僒儞僗僇亅儔乮惗懱揑憿惉椡乯偑丄傕偼傗柍偔側偭偰偟傑偭偨偙偲傪堄枴偟傑偡丅乮埥偄偼丄懱撪偺僒儞僗僇亅儔偑栄崻偵揱傢傜側偔側偭偨丄偲尒傞帠傕偱偒傑偡丅乯
丂傑偨丄擼堨寣偱塃敿恎偑晄悘偵側偭偰偟傑偭偨応崌丄塃敿恎偺嶤傝彎偼帺慠帯桙偡傞偺偱丄塃敿恎偵傕僒儞僗僇亅儔乮惗懱揑憿惉椡乯偼摥偄偰偄傞偲尵偊傑偡丅偟偐偟丄塃敿恎傪帺暘偺堄巙偱摦偐偟偰乽壗偐傪嶌傞乿偙偲偼偱偒側偄偺偱丄塃敿恎偵偼堄巙揑側憿惉椡乮僒儞僗僇亅儔乯偼揱払偟側偄忬懺偲尵偊傑偡丅
丂
乮嬻亅幍亅幍敧乯
丂偲偙傠偱丄堄梸揑憿惉椡偼乽乮屄恖揑乯憂憿椡乿偲尵偄姺偊偰擣幆偡傞偙偲傕壜擻偱偡丅傑偨丄惗懱揑憿惉椡偼乽乮屲錧偺斖埻偺乯憿壔椡乿偲尵偄姺偊偰擣幆偡傞偙偲傕壜擻偱偡丅丂傛偭偰丄師偺傛偆偵尵偄姺偊偰傕乽妀怱乿偼偟偭偐傝墴偝偊偰偄傞帠偵側傝傑偡丅
丂
丂丂乽乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡乿丂丂亖丂丂乽乮屄恖偺斖埻偺乯憂憿椡偲憿壔椡乿
丂
丂偙偆偟偨棟夝傪傕偲偵丄乽乮屄恖揑乯憂憿椡偵偼帺惈偑柍偄乿偲帺妎偡傞廋楤偼丄乽娤擮巚峫椡偵帺惈偑柍偄乿偲偄偆帺妎偺廋楤偲暲傫偱丄斲丄偦傟埲忋偵嫮楏側斒庒儓亅僈偵側傝傑偡丅
丂巆擮側偑傜丄戝曽偺恖娫偼亅亅亅乽憂憿椡偼帺椡偱偁傞亖帺暘偺憂憿椡偵偼帺惈偑桳傞乿亅亅亅傛偆側偮傕傝偵側偭偰偄傞傕偺偱偡丅偦傟屘丄帺暘偺憂憿椡傪帺暘彑庤偵巊梡偟偰偄傞偺偱偡丅
丂乽恖巙偺撈棫憶摦偺歡偊乿乮慜曆戞巐復乯偺拞偱偼丄恖娫偺乽巐尮嵾乿偺乽嘇崻杮搻庢乿偼乽愇桘偺搻庢乿偵歡偊傞帠偑偱偒傑偟偨丅
丂偙偺乽愇桘偺搻庢乿偼丄崻尮揑偵偼乽乮屄恖偺斖埻偺乯憂憿椡乮僒儞僗僇亅儔乯偺搻庢乿偲尵偊傑偡丅
丂娾攇暥屔斉偺傛偆偵丄僒儞僗僇亅儔傪乽堄巙乿偲栿偡乮廬棃偺捠愢乯偺棫応偵棫偮偲丄偙偺乽崻杮搻庢乿偺杮幙偑乽堄巙偺搻庢乿偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偄丄傑偙偲偵僩儞僠儞僇儞側棟夝偵側偭偰偟傑偄傑偡丅乽堄巙乿偼搻傔側偄偐傜偱偡丅乮傛偭偰丄偙偺揰偐傜傕丄乽堄巙乿偲栿偡捠愢偑擛壗偵晄揔愗偱偁傞偐偑暘偐傞偱偟傚偆丅乯
丂
乮嬻亅幍亅幍嬨乯
丂恀寱偵丄恀寱偵亅亅亅亙乽堄梸揑憿惉椡亖屄恖揑憂憿椡乿偼柍帺惈側傝亜亅亅亅偲帺妎偡傞峴偵椼傓側傜偽亅亅亅亙帺暘偺拞偵偦傟偱傕棳擖偟偰偄傞乽僒儞僗僇亅儔乿偼丄戝擔嬻墹庡偺傕偺偱偁偭偰丄帺暘偺傕偺偱偼側偄亜亅亅亅偲偄偆帺妎偵栚妎傔丄偦偺帺妎偺拞偵堄幆偑棷傑傞乮廧偡傞乯傛偆偵側傞偱偟傚偆丅
丂偦偆偡傞偲丄僀僌僫僠僆丒僨丒儘儓儔偺乽楈惈抌楙朄乿偺捀揰偵埵抲偡傞乽垽偵払偡傞娤憐朄乿乮嬻亅榋亅堦埲壓乯偺丄偦偺拞偺捀揰偵埵抲偡傞乽戞巐梫揰乿偺嵋憐偵捈寢偟偰峴偒傑偡丅
丂偙偺揰傪儘亅儅朄峜偵愢柧偟偰偁偘傟偽丄儘亅儅朄峜偑暓嫵傪乽尒壓偘傞偙偲乿偼擇搙偲柍偔側傞偱偟傚偆丅
乲彟偰丄儘亅儅朄峜儓僴僱丒僷僂儘擇悽偼僀僞儕傾恖僕儍亅僫儕僗僩偺奺庬偺杮幙揑側幙栤偵懳偟偰庤巻偱夞摎傪偟偨帠偑桳傝傑偡丅乽婓朷偺斷傪奐偔乿乮摨朁幧乯乮慮栰埢巕丒嶰塝庨栧嫟栿乯嶲徠丅偦偺拞偱丄暓嫵偵懳偡傞堦尒夝傪斺業偟傑偟偨偑丄偦偺尒夝偑愺偄暓嫵棟夝偵婎偯偔僉儕僗僩嫵桪埵娤偩偭偨偨傔丄乽暓嫵傪尒壓偘偰偄傞乿偲悽奅偺暓嫵奅偐傜斸敾偝傟偨偙偲偑桳傝傑偡丅乴
丂
乮嬻亅幍亅敧廫乯
丂偲偙傠偱丄乽恀偺暓嫵乿偱偁傞偙偲傪尒暘偗傞婎弨偲偟偰丄乽嶰曮報乿乮偦偺嫵偊偑恀棟偱偁傞帠傪昞偡嶰偮偺報乯偑堦斒偵嫇偘傜偰偄傑偡丅偦傟偑乽嘆彅峴柍忢丂嘇彅朄柍変乮亖柍帺惈乯丂嘊煾炏庘惷乮煾炏偼庘惷丒戝暯埨嫬偱偁傞偲偄偆帠乯乿偱偡丅偙偺嶰恀棟偑惓偟偔愢朄偝傟偰偄傞応崌丄偦偺愢朄偺乽恀偺峴堊庡懱乿偼擛棃偱偁傞乮扐偟丄擛棃傛傝乽帺惈桳傞戝擔嬻墹庡乿偲夝偟偨曽偑堦憌惓妋乯丄偲尵傢傟傑偡丅傑偙偲偵丄偦偺捠傝偱偡丅
丂偙偺乽嘆彅峴柍忢乿偺乽彅峴乿偺乽峴乿偼乽僒儞僗僇亅儔偺娍栿乿偱偡丅
丂偱偼丄偙偺乽彅峴乿偲偼丄壗傪堄枴偡傞偺偱偟傚偆偐丠
丂偙偺乽岅媊夝愅16丏峴乿偺朻摢偐傜丄捠愢傪斸敾偟乽峴乮亖僒儞僗僇亅儔乯傪亀堄巙亁偲榓栿偡傞帠側偐傟乿偲拲堄偟偰棃傑偟偨丅偦偟偰丄惓偟偔偼乽乮惗懱揑丒堄梸揑乯憿惉椡乿枖偼乽乮屄恖偺斖埻偺乯憂憿椡偲憿壔椡乿偲榓栿偡傋偒丄偲巜揈偟偰棃傑偟偨丅
丂扐偟丄偙偺榓栿偼丄朞偔枠傕乽斒庒怱宱乿撪偺乽乮慜屻偺暥柆偵傛偭偰堄枴偺尷掕傪庴偗偨乯僒儞僗僇亅儔乿偺榓栿偱偡丅
丂偦傟偵妑傋丄乽嶰曮報乿偺乽彅峴柍忢乿偺乽僒儞僗僇亅儔乮峴乯乿偼乽堦斒揑恀棟柦戣乿側偺偱丄偙偺応崌丄僒儞僗僇亅儔偺堄枴偼乽屲錧乮恖娫偺屄変乯乿偺榞偵惂栺偝傟傞偙偲偼堦愗桳傝傑偣傫丅
丂傛偭偰丄乽彅峴柍忢乿偺乽僒儞僗僇亅儔乮峴乯乿偼僔儞僾儖偵亅亅亅亙憿壔椡亜亅亅亅偲栿偡傋偒偱偡丅扤偺丠丂旈枾庡偺偱偡丅
丂偡傞偲丄乽彅峴柍忢乿偺恀媊偼亅亅亅
丂亅亅亅偙偆側傝傑偡乮仛嬻亅榋亅擇廫嶲徠仛乯丅
佱佱佱佱丂乽彅峴柍忢乿偺恀媊丂佲佲佲佲
乮憡懳奅儗儀儖偺乯偡傋偰偺憿壔椡偼忢側傜偢丄偄偮偐昁偢徚柵偡傞傕偺側傝丅
戝擔嬻墹庡偺屼椡乮憿壔椡乯柍偔偟偰丄枩暔柍偟丅偟偐偟丄偦偺屼椡傕忢側傜偢丅
庡偼乮枩暔堐帩偺乯楯椡傪堷偒忋偘丄巭傔偰偟傑偆帪傕桳傞丅偦偺帪丄擛壗丠
丂偙傟傪岞埬壔偡傞偲亅亅亅亙弌椡慡徚柵帪丄擛壗丠亜亅亅亅偲側傝傑偟傚偆丅乮乽弌椡乿偵偮偄偰偼屻曆戞屲復嶲徠乯
丂庍懜偼擏懱偺巰傪寎偊傞偵摉偨傝丄帺暘偺巰偡傜傕嫵偊偺戣嵽偵偟偰乽憡懳奅丄宍帶壓儗儀儖乿偺憿壔椡乮偨傞弌椡乯偑姰慡掆巭偟偰偟傑偭偨帪偺帠傪嵋憐偟側偝偄丄偦偆偟偰丄杮嫃偺愨懳奅偵廧偡傞戝擔嬻墹庡偺埵憡乮懚嵼懺條乯偵偙偦堄幆傪崌傢偣側偝偄丄偲嫵偊傜傟偨偺偱偡丅
丂傑偙偲偵丄彅朄乮枩暔枩徾乯傪惗傒弌偟丄壓巟偊偟偰偄傞乽憿壔椡乿偑徚柵偡傟偽丄彅朄傕徚偊傑偡丅僼僅亅僗偲僷儚亅偺擇暘朄乮屻曆戞屲復乯偱尵偊偽丄憿壔椡偼僷儚亅乮弌椡乯偵摉偨傞偺偱丄偄偮偐偼徚柵偟丄僼僅亅僗乮晄惗偺抲椡乯偩偗偑巆傝傑偡丅
丂偙偺傛偆偵怺偔摯嶡偡傞偲亅亅亅亙乽彅峴柍忢乿偼丄乽彅朄柍帺惈乿乽煾炏庘惷乿偺恀棟傪傕撪曪偟偨乽暓嫵偺恀悜拞偺恀悜偺恀棟乿偱偁傞亜亅亅亅偲暘偐傞偱偟傚偆丅
丂
乮嬻亅幍亅敧堦乯
丂偲偙傠偑丄擔杮暓嫵奅偺捠愢偼亅亅亅亙乽彅峴柍忢乿偲偼乽偁傜備傞尰徾偼曄壔偟偰傗傓偙偲偑側偄偙偲乿傪堄枴偡傞亜亅亅亅偲偄偆棫応偱偡丅乽僶僂僢僟乿乮彫妛娰乯偺拞偱傕丄嶰巬攷巑偼儘僂僜僋偺墛偺斾歡傪弌偟偰丄彅峴柍忢偲偼丄堦弖偨傝偲傕摨偠墛偼柍偄偲偄偆恀棟傪昞偡傕偺偲夝偟偨偄偲婰偟偰偄傑偡丅乮暥屔斉乽僶僂僢僟乿丂侾俉侽暸乯
丂壗偲偄偆斶偟傓傋偒尰忬偐丅庡傛丄擔杮偺暓嫵奅偺嶴忬傪偳偆偐偍媬偄壓偝偄丅
丂栟傕丄乽彅朄乮憡懳奅偺奺庬偺懚嵼乯偼堦弖偨傝偲傕摨偠傕偺偱偼側偄乿偲丄捠愢傪慞堄偵夝偡傞側傜丄乽尰戙検巕椡妛乿偵偍偗傞懚嵼偺梙傜偓摍乆傪巜偟偰偄傞丄偲棟夝偡傞帠傕晄壜擻偱偼側偄偱偟傚偆丅偟偐偟丄庍懜偑掜巕偵嫵偊傛偆偲偟偰偄偨恀棟偑丄検巕椡妛偺偦傟偱側偄帠偼柧敀偱偡丅庍懜偑揱庼偟偨偐偭偨偺偼亅亅乽帺惈桳傞懚嵼傊偺嵋憐朄乿亅亅偵懠側傜側偄偼偢偩偐傜偱偡丅
丂嵞搙妋擣偡傞偲亅亅亅乽僒儞僗僇亅儔乮峴乯乿偲偼丄乽偦傟乿傪乽偦傟乿偨傜偟傔偰偄傞乽椡乮憿壔椡乯乿傪堄枴偟傑偡丅嶰巬攷巑偺乽儘僂僜僋偺墛偺斾歡乿偱尵偊偽丄榅傪榅偨傜偟傔偰偄傞椡丄巁慺傪巁慺偨傜偟傔偰偄傞椡丄擱從嶌梡傪擱從嶌梡偨傜偟傔偰偄傞椡丄墛傪墛偨傜偟傔偰偄傞椡側偳偑乽僒儞僗僇亅儔乿側偺偱偡丅墛偦傟帺懱傪乽僒儞僗僇亅儔乿偺斾歡偵偡傞偺偼丄偱偡偐傜懨摉偱偼偁傝傑偣傫丅墛偼僒儞僗僇亅儔偑摥偄偨寢壥偺巔偱偡丅
乮擩傠丄姼偊偰尵偆側傜丄乽墛乿偵歡偊傞傛傝偼丄僒儞僗僇亅儔偼宐傒偺崻杮偲偟偰偺乽懢梲偺擬慄丒岝慄乿偵歡偊偨曽偑椙偄偱偟傚偆丅乯
丂擔杮偺暓嫵妛幰偼丄恀偺嵋憐廋峴偺偨傔偵乽昐帪娫傗愮帪娫乿傪旓傗偦偆偲偡傞帠偼寛偟偰偟傑偣傫丅壗屘側傜丄偦傫側壣偑桳偭偨傜乽杮傪撉傫偱丄妛栤偟丄抦幆傪憹傗偦偆乿偲偡傞偐傜偱偡丅偦偆傗偭偰丄惓偟偄嵋憐椡傪楤惉偟側偄傑傑暓朄傪愢偔偐傜丄偙偆偄偆僀儞僠僉夝庍偵側傞傢偗偱偡丅斒庒怱宱偺乽僒儞僗僇亅儔乿傪乽堄巙乿偲栿偟丄弾柉傪柍抦偺戝奀偱塲偑偣偨傑傑丄暯婥側婄偱嫃傞偺偼椙偄帠偱偼偁傝傑偣傫丅
丂妛幰彅巵偺栆徣傪朷傓強埲偱偡丅乮埲忋偼丄垽偺曏丄寈嶔偲棟夝偟偰壓偝偄丅乯
丂
乮嬻亅幍亅敧擇乯
丂壖偵崱丄桪廏側暓嫵搆偑僉儕僗僩嫵搆偵岦偐偭偰丄師偺傛偆側幙栤傪偟偨偲偟傑偡丅
乽恄偼揤抧傪憂憿偟恖娫傪憂憿偟偨偲尵偄傑偡偑丄恄偼偦偺憿壔椡傪丄塱懕揑丒峆媣揑偵峴巊偟懕偗偰丄寛偟偰巭傔傞偙偲偑柍偄偲丄偁側偨曽偼偍峫偊偱偡偐丠丂恄條傕亀偍媥傒亁偡傞偙偲偑偁傞偲偼峫偊傑偣傫偐丅埨懅擔偵亀屼嬈傪媥傑傟偨亁偲偄偆惞彂偺婰弎偼丄慡柺揑偱偼側偄偵偟傠丄埥傞掱搙偺丂亀恄偺憿壔椡偺掆巭亁丂偺徾挜偲尒傞偙偲傕偱偒傞偺偱偼偁傝傑偣傫偐乿丂偲丅
丂偦偟偰丄僀僌僫僠僆偺乽垽偵払偡傞娤憐朄乿乮屻曆戞榋復乯偵偮偄偰岅傝崌偄丄偦偆偟偰丄暓嫵偺乽彅峴柍忢乿偵偮偄偰偺乮偙偙偱帵偟偨杮摉偺乯恀媊傪揱偊傞側傜偽丄僉儕僗僩嫵搆偼丄暓嫵偺墱怺偝偵姶扱偟丄垹慠偲側傞帠偱偟傚偆丅
丂偗傟偳傕丄廬棃偺捠愢偺傛偆偵乽彅峴柍忢偲偼偁傜備傞尰徾偼曄壔偟偰傗傓偙偲側偟丄偲偄偆堄枴乿偲偄偆埫嬸側傞尒夝傪宖偘偰僉儕僗僩幰偵岅傝偐偗傞側傜丄乽偁偭丄偦偆丅偦傟偑亀嶰曮報亁側偺偱偡偐乿偲曉摎偝傟傞偩偗偱丄尒壓偝傟丄垼傟偵巚傢傟傞偺偑僆僠偱偟傚偆丅
丂
乮嬻亅幍亅敧嶰乯
乮17乯丂幆
丂丂償傿僕儏僯儍亅僫偺娍栿偱偡丅僕儏僯儍亅乮抦傞乯偲偄偆摦帉偵丂乽償傿乿偲偄偆愙摢帿傪晅偟偨拞惈柤帉偱偡丅偙偺愙摢帿乽償傿乿偵偼丂乽暘妱偟偰丄屄暿偵丄偽傜偽傜偵乿側偳偺堄枴偑偁傝傑偡丅
丂傛偭偰丄乽償傿僕儏僯儍乕僫乿偼堦斒揑偵偼乽帠棟曎暿堄幆乿傪巜偡尵梩偩偲尵偊傑偡丅擔杮岅偺乽暘偐傞乿偵乽暘乿偺帤傪摉偰傞偺偲嫟捠偺姶妎偱偡丅偮傑傝丄償傿僕儏僯儍亅僫偼丄乽暘偐傞傕偺乮庡懱亖堄幆乯偲丄暘偐偭偨傕偺乮幆暿屻偺抦幆乯乿偺椉曽傪娷傔偨奣擮偱偡丅
丂偙偺乽暘偐偭偨傕偺乮幆暿屻偺抦幆乯乿偑乽悽懎抦乿偱偡丅傛偭偰丄償傿僕儏僯儍亅僫傪戲嶳妉摼偡傞偲丄悽抦偵挿偗偨幰偲側傝傑偡丅
丂偟偐偟丄悽抦偵挿偗偰峴偔偦偺愭偵乽屽傝乿偑偁傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偙偺帠偼婛偵丄乽斒庒攇梾枿懡乿傪乽抦宐偺姰惉乿偲栿偡偙偲側偐傟丄偲巜揈偟偨張偱岅偭偨摴棟偱偡偟丄偙偺屻偺乽岅媊夝愅30乿乮嬻亅幍亅仛屲廫嬨埲壓乯偱傕捝楏偵巜揈偡傞梊掕偱偡丅
丂亙悽抦偵挿偗偰峴偔偦偺愭偵乽屽傝乿偑偁傞傢偗偱偼側偄亜偲偄偆摴棟偼丄婛偵愄偐傜暓嫵偱偼丄償傿僕儏僯儍亅僫傪乽暘暿抭乿偲娍栿偟偨忋偱亅亅亅
亙暘暿抭傪幪偰偰乽柍暘暿抭乿偵摓傞偙偲偙偦乽屽傝乿偱偁傞亜亅亅亅偲丄孞傝曉偟愢偐傟偰偄傞偙偲偱偡丅
丂偙偺乽柍暘暿抭乿偙偦丄愙摢帿償傿傪嶍彍偟偨乽僕儏僯儍亅乮摦帉偺柤帉梡朄乯乿偲屇偽傟傞傕偺偱偁傝丄傑偨乽僾儔僕儏僯儍亅乮斒庒乯乿偲屇偽傟傞乽杮抧偺塨抭乮媶嬌塨抭乯乿側偺偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅敧巐乯
丂埲忋偑丄乽償傿僕儏僯儍亅僫偵偮偄偰偺堦斒榑乿偱偁傝丄乽幆乿傪惓偟偔棟夝偡傞忋偱偺乽婎慴偲側傞戝慜採乿偱偡丅偙偺揰傪偟偭偐傝墴偝偊偰偍偗偽丄償傿僕儏僯儍亅僫偵偮偄偰僋儕傾亅側棟夝偑帩偰傞偼偢偱偡丅
丂偲偼尵偊丄巆擮側帠偵丄暓嫵奅偱偼愄偐傜丄乽幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偺夝庍傪弰偭偰彅愢偑棎棫偟丄崿棎偟偨忬嫷偵偁傝傑偡丅傛偭偰丄偦偺崿棎偺尨場傪漃乮僄僌乯傝弌偟丄崿棎傪廔懅偝偣偰峴偒傑偟傚偆丅
丂愭掱偺乽償傿僕儏僯儍亅僫偵偮偄偰偺堦斒榑乿傪摜傑偊偮偮丄斒庒怱宱偺暥柆拞偺乽償傿僕儏僯儍亅僫乿傪偳偆懆偊丄偳偆榓栿偡傋偒偐丄峫偊偰傒傑偟傚偆丅
丂娾攇暥屔斉偱偼丄償傿僕儏僯儍亅僫傪乽抦幆乿偲栿偟偰偄傑偡丅
丂偟偐偟丄乮嬻亅幍亅榋屲偺乯乽恀悜榓栿乿偱偼亅亅亅亙屄懱堄幆亜亅亅亅偲栿弌偟偰偄傑偡丅
丂摨偠乽償傿僕儏僯儍亅僫乿側偺偵丄偳偆偟偰偙偆偟偨戝偒側妘偨傝偑惗偠傞偺偱偟傚偆偐丠
丂堦尵偱尵偊偽亅亅亅亙乽償傿乿傪愺偔庢傞偐丄怺偔庢傞偐丄偺嵎亜亅亅亅偲尵偊傑偡丅
丂廬棃偺捠愢偼丄乽償傿乿傪乽愺偔夝庍乿偟偰丄乽暔帠傪暘暿丒曎暿偡傞堄幆乿偲棟夝偟偰偄傑偡丅偙偙偐傜乽抦幆乿偲偄偆栿偑弌傑偡丅壗屘側傜丄乽抦幆乿偵偼乽抦妎堄幆乿乮摦揑堄幆乯偺堄枴傕偁傞丄偲帿彂偵嵹偭偰偄傞偐傜偱偡丅
丂偟偐偟丄堦斒恖偑擔忢揑偵乽抦幆乿偲尵偆応崌丄乽抦妎堄幆乿偺堄枴偱巊偆偙偲偼杦偳側偄偱偟傚偆丅晛捠丄乽抦幆乿偲尵偆偲丄乽幆暿屻偺抦幆亖婰壇偲偟偰偺抦幆乿乮惷懺乯偟偐堄枴偟傑偣傫丅偙偺揰偱丄乽抦幆乿偲偄偆栿岅偼晄揔愗偩偲尵偊傑偡丅乮乽昞徾乿偲摨偠偔丄晛抜巊傢側偄尵梩丄偦傟傕儅僀儞僪偺嫮偄尵梩傪巊偭偰斒庒儓亅僈傪偟傛偆偲偟偰傕丄偆傑偔峴偒傑偣傫丅乯
丂
乮嬻亅幍亅敧屲乯
丂偱偼丄乽抦幆乿偲栿偝偢乽抦妎堄幆乿偲栿偟偰偼偳偆偐丅偙傟側傜偽丄償傿僕儏僯儍亅僫偼丄屲姶偐傜擖偭偰棃傞巋寖忣曬傪乽乮曎暿偟偰乯抦妎偡傞堄幆乿偲丄捈偖暘偐偭偰椙偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂偟偐偟丄偦偆偼栤壆偑壓傠偝側偄偺偱偡丅
丂乽抦妎堄幆乿偲栿偟偰偟傑偆偲丄乽偱偼丄婰壇側偳偺妉摼偟偨抦幆偼丄屲錧偺偳傟偵懏偡傞偺偐丠乿偲偄偆媈栤偵摎偊傜傟側偔側偭偰偟傑偆偐傜偱偡丅
丂偮傑傝丄壗偲偟偰傕乽抦幆乿偲榓栿偟偰丄乽嘆抦妎堄幆丂嘇婰壇側偳偺乮惷懺揑乯抦幆乿丄偙偺擇庬椶傪嫟偵娷傓尵梩偵偡傞昁梫偑桳傞傢偗偱偡丅
丂偦偆偄偆傢偗偱丄帿彂偵彂偄偰偁傞埲忋丄乽抦幆乿偵偼乽抦妎堄幆偺堄枴傕偁傞乿偲偄偆榑棟傪弢偵偟偰乽償傿僕儏僯儍亅僫乿傪乽抦幆乿偲栿偟偰傕丄柍抦側弾柉側傜壗偲偐閤偣傞偱偟傚偆丅偟偐偟丄恀寱偵斒庒儓亅僈傪幚慔偟傛偆偲偡傞峴幰偵懳偟偰丄偙偺栿岅偱偼慡慠捠梡偟傑偣傫丅
丂娾攇暥屔斉偺傛偆偵丄乽憐仺昞徾乿乽幆仺抦幆乿偲栿偟偰偟傑偆偲丄乽偱偼丄婰壇側偳偺惷懺揑抦幆傪堷偭挘傝弌偟偰丄漵偹孞傝夞偟丄拪徾揑丒棟擮揑巚峫傪偡傞嶌梡偼丄屲錧偺壗張偵懏偡傞偺偐丠乿丂栤戣偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
丂傕偟傕丄偦傟偼乽憐亖昞徾乿偵懏偡傞偲尵偆側傜偽丄乽偦傟側傜丄昞徾偲栿偝偢丄娤擮巚峫椡偲栿偟偨曽偑椙偄偱偼側偄偐乿偲偄偆偙偲偵側傞偱偟傚偆丅
丂傑偨丄傕偟傕丄偦傟偼乽幆亖抦幆乿偵懏偡傞偲尵偆側傜偽丄乽偱偼丄嘆抦妎堄幆丂嘇婰壇側偳偺惷懺揑抦幆丂偺堄枴偟偐側偄亀抦幆亁偺栿岅偱偼嫹夁偓傞偺偱偼側偄偐乿偲偄偆偙偲偵側傞傢偗偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅敧榋乯
丂偱偼丄偳偆栿偣偽惓偟偄偺偱偟傚偆偐丠丂幚偼丄懡偔偺暓嫵妛幰傕傛偔暘偐傜側偄張側偺偩偲尵偊傑偡丅斵傜偼幚偺張丄偙偺栤戣偵偼崲榝偟丄崿棎偟側偑傜丄堦墳丄堦庬偺乽摝偘乿偲偟偰乽抦幆乿偲栿偟偰偄傞偵夁偓側偄丄偲昡偣傑偟傚偆丅
丂偗傟偳傕丄僀儞僠僉傪曻抲偟偰抲偔傢偗偵偼峴偐側偄偺偱丄峏偵塻偔撍偭崬傫偱峴偒傑偟傚偆丅
丂乽屲錧乿偵娭偟偰偼丄擔杮偺暓嫵妛幰偺廬棃偺捠愢偼乽枩暔枩徾乿憤偰偑乽屲錧乿乮惓偟偔偼屲廜乯乮亖屲偮偺梫慺乯偱峔惉偝傟偰偄傞丄偲偡傞尒曽偱偡乮娾攇暥屔斉傕偙偺愢傪嵦傝傑偡乯丅偙偆偟偨乽昑尒乿傪恊愗偵恾幃壔偟偰壓偝偭偨傕偺偑丄乽斒庒怱宱島媊乿乮崅恄妎徃挊丂妏愳暥屔乯偺擇仜屲暸偵婰嵹偝傟偰偄傑偡乮戞擇島偺拲俀乯丅乮扐偟丄妵屖晅偗偺尵梩偼巹偺曗懌偱偡丅乯
丂
乮乽怓乿傪嵟弶偐傜堦斒壔偟偰偄傑偡乯
丂
丂
乮嬻亅幍亅敧幍乯
丂偙偺恾偺壗張偑娫堘偭偰偄傞偐偑暘偐傟偽丄乽斒庒怱宱乿偺乽屲錧偺亙幆亜乿偺恀媊傪夛摼偟偨偲尵偊傑偡丅偦偟偰丄偦傟偑暘偐傟偽丄乽幆乿傪乽抦幆乿偲偼寛偟偰栿偝偢丄乽屄懱堄幆乿偲榓栿偡傞偙偲偵側傞偱偟傚偆丅
丂偙偺恾偱丄惓偟偔棟夝偡傋偒堦斣偺億僀儞僩偼丄乽怓怱晄擇乿偲偄偆尵梩偱偡丅
丂揤戜廆戞榋慶偺扻慠乮偨傫偹傫乯偼丄乽廫晄擇栧乿偺嵟弶偵乽怓怱晄擇乿傪嫇偘丄乽怱傪忢廧偲偄傆帠偼丄杴惞摨懱偵偟偰丄怓怱晄擇側傞堦怱朄奅傪偟傔偡側傝乿偲愢柧偟偰偄傑偡丅
丂慜乆傛傝丄枩暔枩徾偼乽柍帺惈懚嵼偲帺惈桳傞懚嵼偲偺崿惉懱乿偱偁傞丄偲愗乆偲愢偄偰棃偨捠傝丄偙偺摴棟偑暘偐傟偽丄乽怓怱晄擇乿偺乽怓乿偼乽柍帺惈懚嵼乿偺戙昞慖庤偱偁傝丄乽怱乿偼乽帺惈桳傞懚嵼乿傪堄枴偡傞丄偲梕堈偵暘偐傞偼偢偱偡丅
丂偙偙偱偺乽怱乿偼丄乽恖娫偺屄変偺怱乿偺堄枴偱偼抐偠偰偁傝傑偣傫丅朞偔枠傕丄乽恀変亖瀽亖戝変乿偺怱傪堄枴偟傑偡丅偙傟偼丄扻慠偺乽堦怱朄奅乿偺岅偱傕暘偐傞偱偟傚偆丅
丂偲偡傞偲丄怱墹乮偟傫偺偆乯偼丄乮懡媊揑側梡朄偑桳傞偗傟偳偙偙偱偼乯乽恀変乿傪堄枴偡傞丄偲夝偡傋偒偱偡丅偮傑傝丄懺乆乮傢偞傢偞晦乯乽怱墹乿偲偄偆梡岅傪巊偆偺偼乽怱擻乿偵捠偠傞偐傜偱偁傝丄乽強乿偼庴摦懺丄乽擻乿偼擻摦懺傪堄枴偡傞偲尒傞傋偒偱偡丅
丂傛偭偰丄乽怱墹乮擻乯乿偼乽怱傪摦偐偡恀偺庡懱乿傪巜偟丄乽怱強乿偼乽怱墹偵傛偭偰摦偐偝傟傞怱偺摥偒乮怱偺彅條憡乯乿傪巜偡丄偲夝偡傋偒偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅敧敧乯
丂偝偰丄偦偆偡傞偲丄乽屲錧偺幆乿偲乽榋戝偺幆乿偵丂乽戝変亖怱墹乿傪娷傔傞偐斲偐丄偲偄偆帠偑戝栤戣偲側偭偰棃傑偡丅
丂乽枩暔枩徾偼屲錧乮偺屲梫慺乯偱弌棃偰偄傞乿偲偄偆乮廬棃偺尃埿桳傞乯捠愢偐傜偡傞偲丄乽屲錧偺幆乿偺拞偵乽戝変亖恀変亖怱墹乿傪娷傔傞偟偐偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄偙傟偼杮摉偵杮摉偵娫敳偗側尒夝偩偲尵偊傑偡丅
丂乽屲錧偺幆乿偺尨岅偼乽償傿僕儏僯儍亅僫乿偱偡丅偦傟側偺偵廬棃偺捠愢偼丄偙偺償傿僕儏僯儍亅僫偵乽僕儏僯儍亅乮戝変偺堄枴乯乿傪娷傔傞偲庡挘偟偰偄傞帠偵側傝傑偡丅嵟憗丄嫸婥偺嵐懣偱偟傚偆丅壗偺偨傔偵丄乽暘棧乿傪堄枴偡傞乽償傿乿偑晅偄偰偄傞偺偐丄慡慠暘偐偭偰偄側偄徹嫆偱偡丅
乮栜榑丄乽償傿僕儏僯儍亅僫偺堦斒榑乿偱夝愢偟偨捠傝丄乽戝変亖杮抧偺塨抭乿偲嬫暿偡傞偨傔偵乽償傿乿偑晅偗傜傟偰偄傞偺偱偡丅乯
丂乽屲錧偼憤偰柍帺惈乿偱偡丅偙傟偼斒庒怱宱夝愢偺戞堦晹偱徻愢偟偨捠傝偱偡丅
丂枩暔摨條丄恖娫傕乽帺惈桳傞懚嵼乿偲乽柍帺惈懚嵼乿偺崿惉懱偱偡丅偮傑傝丄恖娫偼恀変偲屄変乮屲錧乯偺崿惉懱偱偡丅乮慜曆戞嶰復乯
丂偙傟偱乽枩暔枩徾偼屲錧偱弌棃偰偄傞乿偲偄偆捠愢偑丄偦傕偦傕栚拑嬯拑偱偁偭偨帠偑丄壩傪尒傞傛傝柧傜偐偵側偭偨偱偟傚偆丅乮乽岅媊夝愅俉丏屲錧乿嬻亅幍亅屲廫埲壓乯
丂
乮嬻亅幍亅敧嬨乯
丂亅亅亅埲忋丄栚拑嬯拑側捠愢偼丄乽屲錧偺幆乿傪乽抦幆乿偲榓栿偡傞堦曽偱丄偙偺乽幆乿偵乽怱墹亖恀変乿偲偄偆嵟怺偺堄枴傪傕娷傔偰偟傑偭偨乽幾尒乿偱偟偐偁傝傑偣傫丅
丂偮傑傝丄乽償傿僕儏僯儍亅僫乮幆乯乿偺乽償傿乿傪乽暔帠傪暘暿偡傞乿偲偄偆愺偄堄枴偵夝偟偰丄惃偄丄乽僕儏僯儍亅乮恀変乯乿傪娷傔偰偟傑偆娫堘偄傪斊偟偰偄傑偡丅
丂
乮嬻亅幍亅嬨廫乯
丂堦曽丄乽償傿乿傪杮棃揑側怺偄堄枴偱懆偊傞応崌丄乽屲錧偺幆乿偼丄乽恀変乿偲偼弒暿偝傟傑偡丅乮偙偺弒暿偺偨傔偵偙偦乽償傿乿偑晅偄偰偄傞偺偱偡偐傜丅乯
丂偮傑傝丄偙偺乽償傿乿偼丄乽恀変偲偼暘棧偟偨乿偲偄偆堄枴偩偲夝偟傑偡丅
丂廬偭偰丄償傿僕儏僯儍亅僫偼亅亅亅亙乽恀変偲暘棧偟偨堄幆乿懄偪乽屄懱堄幆乿亜亅亅亅偺堄枴偵側傝傑偡丅
丂偱偼丄棟夝偺曋媂偺偨傔丄乽愺偄償傿愢乮捠愢乯乿偲乽怺偄償傿愢乮恀愢乯乿偲偺堎摨偵偮偄偰丄娙扨偵乮朞偔枠僀儊亅僕揑偵乯恾帵偟偰偍偒傑偟傚偆丅
丂
乣乣乣乣乲愺偄償傿愢乴乣乣乣乣乣乣
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂
丂丂仸 丂儅僫幆偼丄柊偭偰偄傞帪偵傕妶摦偟偰偄傞怺偄巚峫堄幆偺偙偲丅
丂丂丂丂丂傾儔儎幆偼丄夁嫀悽偐傜堷偒宲偄偩孫廗側偳丄柍堄幆撪偵強憼偝傟偰偄傞傕偺丅
丂
丂
乣乣乣乣乣乣乲怺偄償傿愢乴乣乣乣乣乣乣
丂
丂丂
丂
乮嬻亅幍亅嬨堦乯
丂乽愺偄償傿愢乿偩偲丄乽変偺娤擮乿傗乽巐尮嵾乿偼丄慡晹乽幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偺摥偒丄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
丂堦曽乽怺偄償傿愢乿偱偼丄姼偊偰柍棟偵偱傕嬫暘偗偡傞側傜偽丄乽変乮懐変乯偺娤擮乿偲乽巐尮嵾偺撪偺嶰偮乿乮嘇崻杮嶖岆丂嘊崻杮変梸丂嘋崻杮搻庢乯偼丄乽娤擮巚峫椡乮憐乯乿偵懏偡傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偟偰丄乽巐尮嵾乿偺乽嘆崻杮夁幐乿偺傒偑乽屄懱堄幆乮幆乯乿偑斊偡夁幐偲尵偊傑偟傚偆丅扐偟丄乽娤擮巚峫椡乮憐乯乿偲乽屄偺堄幆乮幆乯乿偺嫬奅偼晄暘柧偲尵偊傑偡丅
丂傑偨丄乽愺偄償傿愢乿偩偲丄乽桞幆攈乿偺峫偊偼弌岥柍偟偺柪楬偵擖傝崬傫偱偟傑偄傑偡丅椺偊偽丄桞幆攈偼乽幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偺拞偵乽尒傞幰乮庡懱乯亖尒暘乿偲乽尒傜傟傞暔乮懳徾乯亖憡暘乿偑崿嵼偟偰偄傞丄偲峫偊傑偡丅偙傟偩偗側傜傑偩儅僔偱偡偑丄偦傟傪峏偵嵶暘壔偟偰丄乽尒傞幰乮庡懱乯乿傪峏偵墱怺偔偱乽尒傞幰乿偑嫃偰丄偦傟傪峏偵乽尒傞幰乿偑嫃傞乧偲峫偊巒傔傞偲丄廔傢傝偑柍偔側偭偰偟傑偄丄夝寛偑晅偐側偄帠懺偵娮偭偰偟傑偄傑偡丅乮柍尷嬀憸尰徾偺傛偆偵乯
丂偟偐偟丄乽怺偄償傿愢乿偩偲丄乽恀偵尒傞幰乮恀庡懱乯乿偼恀変偺傒丄偲暘偐傝傑偡丅偙傟偱偍偟傑偄偱偡丅
丂傑偨丄乽愺偄償傿愢乿偩偲丄乽楈嵃斲掕愢乿偵孹偄偰偟傑偄傑偡丅壗屘側傜丄柍抦側傞暓嫵搆偼乽暓嫵偼柍変傪愢偔丅偙傟偼楈嵃傪斲掕偟偨堄枴偱偁傞乿偲暯婥偱尵偭偨傝丄埥偄偼丄彮乆儅僔側幰偱傕丄乽庍懜偼楈嵃偺懚斲偵偮偄偰亙柍婰乮亖摎偊側偄偙偲乯亜傪捠偟偨偺偱丄恀偺暓嫵偼楈嵃偺懚嵼偵偮偒丄峬掕傕斲掕傕偟側偄乿偲尵偆偐傜偱偡丅乮偲偙傠偑丄偙偆尵偆幰偵尷偭偰丄撪怱偱偼楈嵃偺懚嵼傪斲掕偟偰偄傞偙偲偑懡偄丅乯
丂偟偐偟丄埥傞掱搙崅偄嵋憐偑弌棃傞傛偆偵側傞偲丄楈嵃偺懚嵼偼柧妋偵抦妎偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅乮椺偊偽丄敀塀慣巘側偳傕偦偆偱偁偭偨傛偆偵乯桯懱棧扙傕帺妎偱偒傑偡丅
丂偙偺傛偆偵丄惓偟偄嵋憐儓亅僈偵惛恑偟丄埥傞掱搙偺払惉傪摼偨幰偼丄昁偢楈嵃偺懚嵼傪峬掕偟傑偡丅
丂乽怺偄償傿愢乿偐傜偡傞偲丄乽屄揑側楈嵃乿傕乽帺惈桳傞懚嵼偲柍帺惈懚嵼乿偲偺崿惉懱偲娤傑偡丅廬偭偰亅亅亅
亙乽屄揑側楈嵃乿偺乽屄揑晹暘乿偺傒偑乽柍帺惈亖柍変乿亜亅亅亅偲偄偆擣幆偵側傝傑偡丅偙傟偑乽楈嵃乿偺惓偟偄幚憡丒恀棟偱偡丅
丂
乮嬻亅幍亅嬨擇乯
丂嵟屻偵丄暓嫵偺廫擇場墢乮嬻亅幍亅仛仛仛乯偺弴斣傪墴偝偊偰偍偔傋偒偱偡丅
丂偦偺戞嶰巟偺乽幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偼丄戞巐巟偺乽柤怓乿乮暔幙揑丒擏懱揑側屄懱恎乯偺慜偵抲偐傟丄乽屄懱恎偺尨場乿偲埵抲晅偗傜傟偰偄傑偡丅偙偺偙偲偼丄乽幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偑乽暔幙揑屄懱恎埲慜偺懚嵼亖屄懱揑側楈嵃乿乮楈懱偲偟偰偺屄偺堄幆乯偲偟偰桳傞偙偲傪憐掕偟偨傕偺丄偲尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅
丂傑偨丄乽幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偺慜偵乽峴乿偑抲偐傟偰偄傞揰傕廳梫偱偡丅
丂亅亅亅埲忋偺彅揰偐傜丄乽屲錧偺幆乮償傿僕儏僯儍亅僫乯乿偼丄乽屄懱堄幆乿偲棟夝偡傞偺偑嵟傕揔愗偲尵偊傑偡丅
丂
乮嬻亅幍亅嬨嶰乯
乮18乯丂枓暅擛惀
丂僄償傽儉丒僄亅償傽偺娍栿岅丅僄償傽儉偼丂乽偙偺傛偆偵丄偙偺擛偔丄摨條偵乿丂偺堄枴丅娍栿偺乽擛惀乿偵摉偨傝傑偡丅
丂僄亅償傽偼丄乽慡偔乿丂偺堄枴丅娍栿偺乽枓暅乿乮乣傕傑偨乯偵摉偨傝傑偡丅
丂丂
乮埲忋偱丂乽怱宱偺戞擇晹偺鶣乿丂偺晹暘偺夝愢傪廔椆偟傑偡丅乯
丂
丂
丂
仼仼慜儁乕僕偵峴偔丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂師儁乕僕偵峴偔仺仺丂
偙偺儁乕僕偺嵟廔峏怴擔丂俀侽侽俆乛俀乛侾俉
挊嶌尃偵偮偄偰
丂丂丂仭丂仭丂仭丂仭丂丂Copyright 乮c乯 2003乣2012 Aomi Ryu All Rights Reserved丂仭丂仭丂仭丂仭丂丂
儔儀儖彅峴柍忢