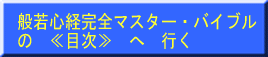【ステップ4】 全単語を正しく理解する (続き)
(空-七-百二十六)
(Ⅲ)第三部
(少々長いため、第三部を更にⅰ、ⅱの二つに分割して解説して行きます。)
(ⅰ) 以無所得故 菩提薩捶 依般若波羅蜜故 心無●礙。
無●礙故 無有恐怖 遠離〔一切〕顛倒夢想 究竟涅槃。
三世諸仏 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三貘三菩提。
(ⅱ) 故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒 是無上咒 是無等等咒 能除一切苦
真実不虚故。説般若波羅蜜多咒 即説咒曰
掲帝 掲帝 波羅掲帝 波羅僧掲帝 菩提僧莎訶
般若波羅蜜多心経
(空-七-百二十七)
第三部(Ⅲ)-ⅰ
以無所得故 菩提薩捶 依般若波羅蜜故 心無●礙。
無●礙故 無有恐怖 遠離〔一切〕顛倒夢想 究竟涅槃。
三世諸仏 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三貘三菩提。第三部(Ⅲ)-ⅰ 〔真髄和訳〕(読誦用)
<梵語原文に沿って訳す>
それ故に、「(個としての)獲得(一切)無し」(との一事)を以て、「悟りへの発心堅固な勇者」たる者、完全究極叡智に依拠して「覆うもの無き心」に住むのである。
心を覆うもの、絶無となるが故に、(物事に)恐怖することも無く、転倒した謬見(一切)を超脱して、遂に涅槃に入定するのである。
(また、過去・現在・未来の)三世の何処(どこ)にでも御座(おわ)します諸々の仏陀たちも皆、完全究極叡智に依拠して(いるが故に)、「無上の真正・無欠・覚醒境」という正覚(さとり)を円(まど)かに現前させているのである。
(空-七-百二十八)
<語義解析>
第三部(Ⅲ)-ⅰ
(空-七-百二十九)
以無所得故(34) 菩提薩捶(35) 依般若波羅蜜故(36) 心無●礙(37)
無●礙故(38) 無有恐怖 遠離〔一切〕顛倒夢想(39) 究竟涅槃(40)
三世諸仏(41) 依般若波羅蜜多故(36) 得阿耨多羅三貘三菩提(42)
●は「(罫-ト)」の字(ケイ)が入ります。
(34) 以無所得故
「得る所無きを以ての故に」と読み下します。梵語原文は「タスマ-ド(=それ故) アプラ-プティトヴァ-ド(=無獲得なので)」となっています。
「アプラ-プティトヴァ-ド」は、直前の「無智亦無得」の「得(プラ-プティフ)」に否定辞の「ア」を付け、語尾に「トヴァ-ド(=なので、を以て)」を付けた形です。
一つ前の「得(プラ-プティフ)」は、「経験知の個的獲得」即ち「個的レベルの知る働き」に限定された「(狭義の)獲得」を意味しています。(「語義解析33」参照)
一方、一旦文章を切って、改めて言い直している「アプラ-プティトヴァ-ド」は「知る働き」に限定されない(一般的な意味の)獲得を意味しています。
つまり、「是故空中 無色」から「無智亦無得」までの文章全部、即ち「五蘊・十八処・十二因縁・四諦・智と得」全部を引っくるめて、「そうした個的レベルでの一般的な獲得というものは無い故に(それを以て)、」と否定して、ここで総括しているのです。
よって、「真髄和訳」では---<それ故に、「(個としての)獲得(一切)無し」(との一事)を以て>---と訳出しています。
岩波文庫版の註三一では、「この語は(…)無い方が分り易い」としていますが、勿論、このコメントは間違いであり、こうした「総括」は有った方がずっと良いと言えます。(「得」の意味を取り違えた時にのみ、無い方が分かり易い文章に見えてしまうのです。)
尚、漢訳文だけで読誦していると、「無智亦無得 以無所得故」の二句を繋げて、「得る所無きを以ての故に、智も無く得も無い」と読んでしまう間違いを犯しやすいです。
しかし、梵語原文では、この両者を繋げて読むことはできません。何故なら、両者の間には「タスマ-ド(それ故に)」の語があり、「無智亦無得」で一旦文章を区切り、その上でアプラ-プティトヴァ-ド(無獲得を以て)と言っているからです。
(空-七-百三十)
(35) 菩提薩捶(の梵語原文の表現)
原文は「ボディ-サットヴァ-ナ-ム」となっていて、語尾の格変化をどう解釈するかが、問題となります。(「ナ-ム」は「~の」という「属格」を表します。属格の「属」は所属の「属」です。)
岩波文庫版では、「諸の求道者“の”智慧の完成に安んじて、人は、心を覆われることなく住している」と和訳しています。とても残念な事ですが、これは「錯乱した訳文」と言うしかないでしょう。
この文章を読んで、この意味が分かる者はどうかしています。また、こうした「意味不明な和訳」を通説にしている人々もどうかしています。この訳文の通りであるならば、人は、どうやって、他者である「求道者の智慧の完成」に安んじるようにすれば良いのでしょう? そればかりか、この訳文に拠れば、「人は(皆)『求道者の智慧の完成』に安んじて『心を覆われることなく』住している」ことになり、だとすると、最早修行は無用であるし、般若心経も、般若ヨ-ガも、仏教自体も全部無用、という事になりかねません。
訳者は、果たして、自分のこの「口語訳文」を使用して日々「般若心経」を読誦した経験が有るでしょうか? 毎日、この(錯乱した)口語訳で読誦すれば、程なくして「魂がノ-」と叫び始めるはずなのですが。
まことに、直前まで「個的獲得は無い」と言って来ておきながら、突如「菩薩“の”完全究極叡智」というように、「究極叡智」を「菩薩が所有している」ような格語尾を取る、というのは、文脈の流れからして如何にもおかしい、と分かるでしょう。
よって、文脈の内容からして、語尾の「ナ-ム」は「絶対属格」と解さねば駄目です。
「絶対属格」とは、単独で成立する「絶対句」を作る格語尾で、通常「現在分詞」と共に用いられます。では、その「現在分詞」が記述されていないのは何故でしょうか?
答えは、「アス(存在する・~に属している)」(英語の「BE動詞」に当たる)の現在分詞は、余りに自明なので省略しているから、と解すべきです。
それ故、絶対属格と解すると、ここは「菩薩に属している時は」或いは「菩薩に属する、その者は」という意味になります。つまり、「菩薩」とは「選ばれし者」のグル-プなのであり、「このグル-プに所属している時には」というニュアンスが正解です。
従って、「真髄和訳」で示した通り---<悟りへの発心堅固な勇者“たる”者>---という訳になります。(菩薩については「語義解析5」空-七-三二以下)
(空-七-百三十一)
(36) 依般若波羅蜜多故
般若波羅蜜多については「語義解析3~4」参照。漢訳文を直訳すると「完全究極叡智に依るが故に」となります。
この「依るが故に」に当たるのが、梵語原文の「アシュリトヤ」です。アシュリトヤは、「動詞シュリ 」(に依存する、に結び付けられる)の絶対分詞です。
絶対分詞は、同一の動作主(この場合「菩薩たる者」)が行う複数の行為の内、先行する動詞を表し、「~して(~する)」「~してから(~する)」という意味で使われます。
原文では「アシュトヤ」の直後に「ヴィハラティ(住む)」という動詞が来ているので、「完全究極叡智にアシュトヤして、何処何処に住む」という文になります。
アシュトヤは、漢訳文のように「依るが故に」とも訳せますが、具体的には「プラジュニャ-・パ-ラミタ-・ヨ-ガ(「完全究極叡智」への帰入行)」の実践を意味します。
よって、「真髄和訳」では---<に依拠して>---と訳出しています。
尚、漢訳文では「依るが故に心に●礙無し」として、原文の「住む」という動詞を(自明の事として)省略しています。一方、岩波文庫版の和訳では「住している」という訳になっています。
では何故、文庫版は「住“している”」と「現在進行形」で訳しているのでしょう?
それは「ヴィハラティ」が現在分詞の形だからです。けれども、中学生ならいざ知らず、「現在分詞=現在進行形」のワンパタ-ンで訳していればそれで良いというものではありません。ここでの現在分詞「ヴィハラティ」は、先行する「アシュリトヤ」という絶対分詞との「同時性」を表すものに他なりません。つまり、ここの文章は、「全面的に依存することで、その時(同時)に、~に住む」(そして遂には涅槃に入定する)という「一般法理、ダルマ(理法)」を表わしているのです。
よって、「真髄和訳」のように---<住むのである>---との訳が正解です。
(空-七-百三十二)
(37) 心無●礙
「心に●(罫-ト)礙(けいげ)なし」と読み下します。原文は「ア・チッタ-ヴァラナハ」です。「チッタ」が「心」、「ア-ヴァラナ」が「覆うもの」の意味。「ア」は否定辞。
(空-七-百二十七の)「真髄和訳」では---<覆うもの無き心に(住む…)>---と訳出しています。
人によっては、語頭に否定辞「ア」が来ているので、「覆う心」が「無い」と思う者も居るかも知れません。しかし、例えば、「無い〔枕+カヴァ-〕」となっていたら、枕が無いことになるでしょうか。否。枕自体の否定にはなりません。これと同じ道理です。
この漢訳である「●(罫-ト)」は、網の目を表す「四 」に、土を盛って土地の区切りを表す「圭」で出来た言葉で、「網で覆った仕切り」を意味します。「礙」は石で遮る意味で、その旁の「疑」は、人が立ち止まることを表しています。
よって、「●(罫-ト)礙」で「覆い遮る仕切り」の意味になります。
---では何故、「般若=プラジュニャ-=究極叡智」に全面的に依存・結合すると、心が厚い雲に覆われることなく、「晴天の蒼穹」のようになるのでしょうか?
既に、心経の「第二部」部分の解説で明らかにした通り、「意識を大日空王主の絶対界空無相」に合わせると、「中観の境地」(有相にして無相/無相にして有相)に近付きます。そうすると、「有相なるもの」は「夢・幻」の如きものに過ぎないと看破できるようになり、「有相なるもの」がどうであろうと、それに一喜一憂することなく、一々左右される事がなくなります。
「大日空王主の絶対界空無相」は「荘厳なる光の海」であり、「完璧、完全なる存在」です。この「完璧なるもの」に心を合わせると、その「完全性」が心に流入し、心は喜びで満たされます。
その反対に、「不完全なもの」(有相なるもの、特に、下界の邪悪な波動、憎らしい悪人など)に心を合わせると、その「不完全性」が流入し、心は憤懣・怒り・嫉妬・憎悪等々、様々な暗黒の雲、即ち「●礙」で満たされてしまいます。
従って、真の瞑想とは、今、其処で、不完全な「有相世界の鳥網」から抜け出て、意識を大空へ飛翔させることだとも言えます。
(空-七-百三十三)
(38) 無●礙故
チッタ-ヴァラナ・ナ-スティヴァ-ドの漢訳。ナ-スティヴァ-ドは、「何も無い(=絶無な)ので」という意味。
よって、(空-七-百二十七の)「真髄和訳」の通り---<心を覆うもの、絶無となるが故に>---との訳になります。
(空-七-百三十四)
(39) 無有恐怖 遠離〔一切〕顛倒夢想
アトラスト-・ヴィパルヤ-サ-ティクラ-ント-の漢訳。
「ア」は否定辞。トラスト-は「驚かされること、恐怖すること」の意味。よって、「恐怖なく」の意味。
ヴィパルヤ-サ-は「転倒、ひっくり返ること、ひっくり返った間違った考え・謬(びゅう)見」を意味します。これに、「アティ・クラーントー」という言葉が「連声」で連結しています。
梵語に詳しい方(匿名希望)の解説によれば、
<アティ(ati)は、程度的にも領域的にも「超(超過・超越)」を意味する接頭辞。「クラーンタ」は語根√kram(歩む・歩を運ぶ)の過去受動分詞。よって、「アティクラーンタ(ati+kra-nta)」では、「踏み越えられた・踏み越えた」(語根が自動詞なので能動化もありうる)、更には「超克された・超克した」の意味となる・・・> とのことです。
確かに、萩原雲来の辞書の「アティクラム(atikram)」の項をみると、「通り過ぐ、超ゆ、跨ぐ、横切る、逸す、<従>を過ぎる、凌駕す、(・・・)超出、超度、勝 」などの訳が当てられています。
従って、「ヴィパルヤーサー + アティクランタ」で、「転倒した誤見を超脱して」の意味になります。
漢文訳では、「アティクラーンタ」の訳に、「厭離」の類義語としての「遠離」を持ってきており、「ヴィパルヤーサー」を「転倒夢想」と訳しています。「一切」の語が括弧書きで付加されています。
以上により、(空-七-百二十七の)「真髄和訳」の通り---<(物事に)恐怖することも無く、転倒した謬見(一切)を超脱して>---という訳になります。
【※注意>>>---以前は、この部分を下記のように梵語を解釈ミスして解説していましたことを衷心よりお詫び申し上げます。(空-七-百三十五)
---------
(「無有恐怖 遠離〔一切〕転倒夢想」は)アトラスト-・ヴィパルヤ-サ-ティ・クラ-ント-の漢訳。「ア」は否定辞。トラスト-は「驚かされること、恐怖すること」の意味。ヴィパルヤ-サ-は「転倒、ひっくり返ること、ひっくり返った間違った考え・謬見」を意味します。これに行為・動作を表す「ティ」が付き、「転倒した見方をすること(漢訳では、転倒した夢想)」の意味になります。クラ-ント-(クラーンドー)は「悲嘆・憂悶」の意味。
これで分かる通り、原文の否定辞は「ア」一つだけです。つまり、ア(否定辞)×(トラスト-+ヴィパルヤ-サ-ティ+クラ-ント-)という構文になっています。これを漢訳では、「恐怖有ること無く、転倒した夢想を遠離して」と訳し、否定辞「ア」を「無有と遠離」という二つの否定的な動詞として訳出しています。その一方で、漢訳では「クラ-ント-」が訳されていません。しかし、原文は「ヴィパルヤ-サ-ティ+クラ-ント-」で格限定複合語になっており、前分(前半分)が原因を表す「具格」の働きをする複合語です。従って、正しくは、「転倒した見方をすることによる悲憂悩悶(ひうのうもん)」という意味であり、寧ろ後分の「クラ-ント-」の方が比重が重いのです。(否定対象の絞り込み) この部分は、「般若=究極叡智」に結合・帰入する瞑想行に励むならば、やがて心は晴れやかとなり、どんな「悲嘆・憂悶」も必ずや雲散霧消してしまう、という「約束」を含んだ説法になっています。
-----------
梵語に非常に詳しい方(匿名希望)からご教授を賜り、上記の以前の解説は梵語文法的に無理があるということで、謹んで本文のように訂正致します。
すなわち、「a-trasto」 は、そこに格語尾が付いていますから、もう次の語とは切れているため、「否定辞のa」が「ヴィパルヤーサーティクラントー」に掛かる解釈はできないということです。
★ただし、『叡智(般若)のヨーガの実践』という見地からすると、原文に忠実な翻訳として、「心を覆うもの、絶無となるが故に、(物事に)恐怖することも無く、転倒した謬見(一切)を超脱して、(そうして)遂に涅槃に入定するのである。」
という文言で瞑想するよりも、前の真髄和訳文言
「心を覆うもの、絶無となるが故に、(物事に)恐怖することも無く(なり)、転倒した見方をすることから来る悲憂悩悶(ひうのうもん)も絶無となり、(そうして)遂に涅槃に入定するのである。」
という文言で瞑想した方が、否定対象の絞り込みがされているので、瞑想効果は強くなるという面があるとも言えます。その意味で、以前の真髄和訳で読誦瞑想しても悪い効果というのは一切ありませんので、その点は、ご安心下さい。(常に「意味と効果を重視」しての実践を勧めているので、ご安心下さい。)
ただ、そうはいうものの、「転倒した謬見一切を超脱して」という箇所に力が込められれば、原文通りの方が、「勢いがある」とも言えます。
とまれ、ここは、あくまでも般若心経の原典を尊重した形で、正式な日本語翻訳という形を提示すべきなので、本文のように訂正致します。
------<<<注終了】
(40) 究竟涅槃
ニシタニルヴァ-ナハの漢訳。ニシタは「位する、極まる、終(つい)に到着する」などの意味。涅槃とは、悪業(の生産状態)から完全に解脱した境地・境界のことを意味します。ニルヴィカルパ・サマディ-(前篇第五章参照)と同義と解して大過ありません。(但し、「諸行無常」で触れたように「無自性存在群」を全部引き上げ、消滅させた状態をも表します。)
「サマディ(定)無くして、涅槃への到達無し」。故に「涅槃に着く」と言うより「涅槃に入定する」と言った方が適切です。
よって、「真髄和訳」の通り---<(そうして)遂に涅槃に入定するのである>---との訳になります。
(空-七-百三十六)
(41) 三世諸仏
トリヤドヴァ・ヴヤヴァスティタ-ハ・サルヴァ・ブッダ-ハの漢訳。トリヤドヴァは「三世(過去・現在・未来)」の意味。サルヴァは「一切の」、ブッダ-ハは「仏陀(覚者)たちは(複数形)」の意味です。
漢訳では「ヴヤヴァスティタ-ハ(有る・存在する)」が省略されています。これは、スタ-(=英語のスタンドの語源でもある言葉)にヴヤヴァをくっつけた形の言葉です。「ヴヤヴァ」はその前に「三世」が置かれているので、「そのどれにも」というニュアンスになります。
よって、(空-七-百二十七の)「真髄和訳」の通り---<(また、過去・現在・未来の)三世の何処(どこ)にでも御座(おわ)します諸々の仏陀たちも皆、>---という訳になります。
(空-七-百三十七)
(42) 得阿耨多羅三貘三菩提
「得」はアビサムブッダ-ハの漢訳です。しかし、「得た」という漢字の選択は適切ではありません。心経の「第二部」部分で詳説した通り、「個的に得る」事など無いのですから。この点、原文の心経の制作者はよく弁えており、「得る」という動詞は使わず、「ブドゥ(目覚める)」という動詞の派生語を使っています。
即ち、語頭に「アビサム」を付け、動詞を過去受動分詞にして「アビサムブッダ-ハ」とし、単に「目覚めた」というよりも、その完結形として、「覚醒し切っている」という動詞を使用しています。
「アビ」は「前面に」の意味。つまり「現前」ということ。ここでの「サム」は「全く・完全に・欠ける処無く・全面的に」の意味。
よって、アビサムブッダ-ハは「さとり(本覚)を欠ける処無く、現前させた」状態を指す言葉と解すべきです。
阿耨多羅三貘三菩提は、アヌッタラ-ム・サムヤクサンボ-ディムを、翻訳せずにそのまま漢字で音写したものです。「ア」は否定辞。「ヌッタラ-ム」は「これより上の」という意味です。故に、アヌッタラ-ムで「無上の・至上の」という意味。「サムヤク」は「真正な」という意味。「サン」は「平等な」という意味もありますが、ここでは「全面的に何処も欠ける処無く、完全な」の意味であり、「ボ-ディム」は「悟り・目覚め・覚醒境・本覚・正覚」の意味です。
従来より「アヌッタラ-ム・サムヤクサンボ-ディム」は、色々な形で漢訳されて来ました。例えば、「無上正等覚」とか「無上正真道」とか「無上正遍智」とか「無上等正覚」とか「無上正等正覚」等々の訳が当てられています。
しかし、どれも日本人にはピンと来る訳語ではないでしょう。
原語を素直に日本語に翻訳するならば、「無上の、真正・無欠・覚醒境」となります。
よって、(空-七-百二十七の)「真髄和訳」では---
<「無上の真正・無欠・覚醒境」という正覚(さとり)を円(まど)かに現前させているのである>---と訳出しています。
(空-七-百三十八)
第三部(Ⅲ)-ⅱ
故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒 是無上咒 是無等等咒 能除一切苦
真実不虚故。説般若波羅蜜多咒 即説咒曰
掲帝 掲帝 波羅掲帝 波羅僧掲帝 菩提僧莎訶
般若波羅蜜多心経
第三部(Ⅲ)-ⅱ 〔真髄和訳〕 (読誦用)
<梵語原文に沿って訳す>
故に、(人は)知るべきである---完全究極叡智の偉大な真言を。偉大な明智から出た真言を。無上の真言を。無比なる真言を。
総ての苦しみを鎮める(ことができる)、空虚に非(あら)ざるが故に真実の、「完全究極叡智」に関して説かれた真言を。
それは即ち---
求法 弘法 貫徹ぐ法 貫徹全ぐ法(時) 神覚あれ
guho guho kantetsuguho kantetsuzenguho(ji) sinkakuare
(ア) ここに、「完全究極叡智」の「心髄」(についてのお経)を終える。
(イ) ここに、「完全究極叡智」たる「心(唯心法界)」(についてのお経)を終える。
〔 ア・イ は掛け詞 〕
(空-七-百三十九)
<語義解析>
第三部(Ⅲ)-ⅱ(空-七-百四十)
故知(43) 般若波羅蜜多 是大神咒(44) 是大明咒 是無上咒 是無等等咒(45)
能除一切苦(46) 真実不虚故(47)
説般若波羅蜜多咒(48) 即説咒曰(49)
掲帝 掲帝 波羅掲帝 波羅僧掲帝 菩提僧莎訶(50)
般若波羅蜜多心経(51)
(43) 故知
「故に知るべし」と読み下します。原文は「タスマ-ジ(故に)ジュニャ-タヴヤム(知るべき)」です。ジュニャ-タヴヤムは、動詞「知る(ジュニャ-)」の未来受動分詞。「~(為さ)れるべき」という意味を表します。
よって、直訳すると「(以下に示す)マントラが知られるべき」という意味になります。そしてこれを翻訳する時は、一般三人称を使って「人は知るべきである、(以下に示す)マントラを」という構文になります。
尚、ここで使われている「梵語の原文の構文」は次の通りです。
人は知るべきである---
①「完全究極叡智」の偉大な真言を。
②偉大な明智から出た真言を。
③無上の真言を。
④無比なる真言を。
⑤総ての苦しみを鎮める(ことができる) (⑦の「真言を」に掛かる)
⑥虚に非(アラ)ざるが故に真実の (⑦の「真言を」に掛かる)
⑦「完全究極叡智」に関して説かれた真言を。
(空-七-百四十一)
(44) 般若波羅蜜多 是大神咒
原文は「プラジュニャ-パ-ラミタ-・マハ-マントロ」です。マハ-は「偉大な、大いなる」という意味。マントラは「思念する(ための)器」が原義で、「特定思念」「特定の意識作用」を喚起する機能を持つ「言葉」を指します。漢訳では「マントラ=神咒」という表現になっています。「咒」は「呪」と同じ。よって、「神咒」で「神通力の有る呪文」という意味になります。
ところで、岩波文庫版の読み下し文のように、「般若波羅蜜多は是れ大神咒なり」と読むと、変な意味になってしまいます。
本当は梵語原文に即して「(故に知るべし)般若波羅蜜多、是の大神咒を」と読み下したい処なのですが、漢文の構文は梵語原文とは少々異なるのです。
漢訳文の「故知・般若波羅蜜多」---これは<般若波羅蜜多咒の「咒」を省略した形>---です! 直ぐ後に「是大神咒」とあるので、この省略は暗黙の了解事項です。簡潔を旨とする漢語らしい表現法です。
従って、「漢訳文の構文」は、次のようになっています。
故に知るべし---
①般若波羅蜜多の真言、是れは、偉大な真言なり、と。
②是れ、偉大な明智から出た真言なり、と。
③是れ、無上の真言なり、と。
④是れ、無比なる真言なり、と。
⑤(この真言は)総ての苦しみを取り除くことができる、と。
⑥真実にして虚に非(アラ)ざるが故に (⑤に掛かる)
(「知るべし」は、ここで一端区切りとなる。)
「完全究極叡智」の真言を説く。即ち、説いて曰く---と続きます。
★「真髄和訳」では、梵語の原文の方に忠実に翻訳しています。
(空-七-百四十二)
(45) 是大明咒 是無上咒 是無等等咒
大明咒は、マハ-ヴィドヤ-マントロ-の漢訳。ヴィドヤ-については「語義解析30」で詳説した通りです。「悟り」の意味ではありませんので要注意です。よって、「ヴィドヤ-マントラ」には「聡明な通暁状態から生み出された真言」というニュアンスが有ります。「真髄和訳」では---<明智から出た真言>---と訳出しています。
無上咒は、アヌッタラマントロ-の漢訳。「ウッタラ」が「これより上の」という意味なので、それに否定辞の「ア」が付いて、「無上の」という意味になります。
無等等咒は、アサマサマ・マントラの漢訳。「サマ」は「等しい」の意味。
よって、この一節では---「無上・無比の大真言」即ち「真言の中でも最高・最強の大真言」をこれから汝に伝授しよう---という前置きです。
---ところで、では、本当に「心経」最後の「ガテ-(…)」以下は「無上・無比(最高・最強)の大真言なのでしょうか???」、これが大問題になります。
「南無妙法蓮華経」マントラで悟りに到ろうとする日蓮宗信徒は、南無妙法蓮華経という真言が無上・最高のマントラと考えるため、心経のマントラを至高のマントラと断言している般若心経の読誦を忌避します。また、「南無阿弥陀仏マントラ」で往生を願う念仏宗派では、南無阿弥陀仏マントラこそ最高真言と考えるので、阿弥陀仏をも空と断じる般若心経の読誦を忌避するのが普通です。
さて、結論を先に言うと、心経の「ガテ-(…)」以下のマントラは、その意味内容からして、元々のそれは「無上・無比、最高・最強の大真言」であったと信じて良い、と言えます。こう評価できるその理由は、後の「語義解析50」で解説致します。
但し、「元々のそれは」と条件を付けましたが、日本に般若心経が伝来し、言葉の意味もよく分からないまま、単なる呪文として「ガテ-、ガテ-(…)」と唱える方法では、マントラの法力は激減してしまいます。何故なら、マントラの法力はこの言霊を音声にして発する人の「意念と不可分」なので、意味が分からない呪文ならばそれを言う人の意念も漠然としたものにしかならないからです。従って、明確な神聖意念を伴わない「無意味な呪文」を唱えるぐらいならば、いっその事、日本語マントラである南無妙法蓮華経や南無阿弥陀仏マントラを唱える方が、法力はずっと上だと言えます。
「外国語の真言」を意味不明のまま「未開人のおまじないレベル」で唱える事はやめましょう。マントラは「(高い)思念(波動)を入れた器」なので、意味を正確に把握しながら唱える必要が有ります。
そして、「ガテ-」以下のマントラは、後述するように、原語の意念レベルでは、確かに「最高・最強の大真言」だと言えるので(語義解析50参照)、それにふさわしい<最強の言霊の日本語>で翻訳されなければ駄目です。日本語を母語にする者は、そうした「最強の言霊の日本語訳マントラ」で唱える時に限り、心経が持つ本来の「最強の法力と効果」を享受できるのです。
(空-七-百四十三)
(46) 能除一切苦
サルヴァ・ドゥフカ・プラシャマナ-ハの漢訳。サルヴァは「一切の、総ての」という意味。 ドゥフカは「苦しみ」。 プラシャマナ-ハは「(苦しみを)鎮める」という(マントラに掛かる)形容詞です。
(空-七-百四十四)
(47) 真実不虚故
サティヤム アミトフヤドヴァ-トの漢訳。サティヤムは「真実の、真正な、正しい」という(マントラに掛かる)形容詞。
アミトフヤドヴァ-トで「虚偽(うそ)・空虚ではないので」という意味。
漢訳文の流れからすると、「真実不虚故」は「能除」に掛かる、と読むのが自然です。尤も、「⑥(この真言は)虚偽でない故に真実である、と」と読めない事もありません。
しかし、梵語原文は、「この真言は苦を鎮める」とか「この真言は真実である」とは決して読めません。飽く迄も「苦を鎮める真言」「真実の真言」という構文になっています。
また、もう一つの可能性として、「サティヤム」を副詞と見ることもできないわけではありません。この場合は、「うそではないので本当に(…)説かれた真言」というように(真言ではなく)「説かれた(ウクト)」に掛かることになります。
しかし、心経制作者がここで「本当に説かれた云々」という言い方をするとは考えられません。何故なら、「心経」全体が「本当に説かれた事」という状況設定なのですから。
よって、やはり「サティヤム」は形容詞と解し、「真実の真言」と読むべきです。
それに、「心経」で「真実の真言」と念を押すのには、それなりの背景が有った、と言うべきです。インドという国は、古代から「意味不明のインチキで嘘っ八なマントラ」が多数存在する風土だからです。現代でも、インドのスポ-ツ「カバディ」は、「カバディ」という空虚・無意味なマントラを言い続けて競技しなければなりません。(こうした行為は霊的に見ると、すごく「良くない事」です。言霊を大切にする日本人たる者、「カバディ」を輸入して行う場合は、「カバディ」という空虚・無意味なマントラを何としても忌避すべきです。どうしてもやりたい場合は、英語の「ハイア-<higher>」など、意義深い言葉に置き換えるべきです。また、「神の名」を用いると妄りに連発してその神聖を穢すことになるので宜しくありません。)
(空-七-百四十五)
(48) 説般若波羅蜜多咒
プラジュニャ-パ-ラミタ-ヤ-ム ウクト- マントラハの漢訳。漢訳文の構造では「『完全究極叡智』の真言を説く」となっています。
しかし、梵語原文は「(知るべきである)『完全究極叡智』に関して説かれた真言を」となっています。
ウクト-(ウクタ)は、ヴァチャ vac (言う、説く)の過去受動分詞なので、「説かれた」という意味になります。
(空-七-百四十六)
(49) 即説咒曰
タド(それは) ヤタ-(この様なもの)の漢訳です。
(空-七-百四十七)
(50) 掲帝 掲帝 波羅掲帝 波羅僧掲帝 菩提僧莎訶
梵語原文の「ガテ- ガテ- パ-ラガテ- パ-ラサンガテ- ボ-ディ スヴァ-ハ-」を、漢字でそのまま「音写」したものです。翻訳せずに、原文そのままの「呪文」として扱っています。
従来、「この真言の決定的な訳出は不可能」と考えられて来ました。このマントラは神聖なものとして翻訳しない、という扱いでした。
しかし、「意味不明の呪文に何某か不思議な力が有る」と考えて、マントラを唱えるべきではない事は、前述した通りです(語義解析47参照)。それでは単なる「呪文信仰」に堕して、幼稚極まりない信仰になってしまいます。(「それでも良い」という人に対しては「どうぞ、お好きなように」と言うしかありませんが。)
マントラは、語義から言っても「意念の器」であり、「特定の神聖な高い思念」を喚起するための道具としての機能が有る以上、意味を分かって唱えなければ無意味です。
---では、「心経」最後の「この大真言」は、どんな意味の言葉なのでしょうか?
★ガテ-は、「行く」という動詞「gam 」(英語の「go」に当たる)の過去受動分詞形が処格(於格とも言う)変化したものが少々訛ったものです。「行った時に」とか「行ってしまった時に」という意味です。(呼格形にも見えますが、呼格と解するのが間違いである事は後述します。)
★パ-ラは、「果てまで、(遙か)彼方まで、究極まで、きわまで、とことん、徹底的に」 という意味です。
★サンは、「遍く、完全に、余す処無く、欠ける処無く、全部」という意味です。
★ボ-ディは、「さとり」という意味です。
★スヴァ-ハ-は、祈祷の終わりに用いる締めの言葉で、「幸あれ」とか「祝福あれ」という意味です。
(空-七-百四十八)
以上が、逐語解説ですが、この「無比の大真言」を真に理解するには、もう一点、どうしても押さえておかねばならない事が有ります。それは「何故、これが<無比の大真言>なのか??」---という問題です。
これに関する答えは、次の通りです。即ち---「心経最後の大真言」は、そもそも「総ての真言を生み出す、その母体、根っこの部分」を言語化・マントラ化したものであるが故に---「無比の真言」と言われるのである、と。
これはどういう意味でしょうか。
そもそも、総ての真言(マントラ)は「神聖な思念」を喚起する機能を持つ言葉です。何故なら、そうした機能を持つ「神聖な言葉」をマントラと呼ぶからです。
そして、その「神聖な文言」によって喚起される「神聖な思念」には、様々な内容・種類が有るものの、それらの真言は総て「聖なる渇仰心」(神仏や菩提を求める心)に基づく思念であるし、聖なる渇仰心の一部分がクロ-ズ・アップされて言語化されたものであるために、そのどれもが「聖なる渇仰心」の1バリエ-ション(一へんげ)だと言えるのです。
つまり、各種のマントラはどれも皆「聖なる渇仰心」の部分的な変化相であるし、その多様なアスペクト(局面・切り口)に過ぎない、と言えるわけです。(★二-五-七以下)
「心経」最後の「大真言」を教えた者(又は、心経制作者)は、この事を完全に見抜いていました。
よって、聖なる渇仰心(発菩提心)“それ自体(=一部分ではなく全体)”を言語化したマントラならば、それは即ち「マントラの王にしてマントラの母」「無上、無比の大真言」になる、という道理を知っていたのです。
従って---
「心経」最後の「大真言」は---
<言語化された「聖なる渇仰心(菩提心)」そのもの(=総体)>---なのです。
それ故に「全真言の母」であり、「無上・無比、最高最強の大真言」なのです。
---以上の「奥義」をしっかり押さえれば、「大真言」に珍妙な和訳を付ける愚行・茶番はもはや無くなるでしょう。
(空-七-百四十九)
岩波文庫版では、参考扱いで、大真言を次のように和訳しています。
<往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に全く往ける者よ、さとりよ、幸あれ>---と。
この日本語訳は有名ですが、この訳の短所は、「者」という言葉を入れている点、及び、ガテ-を呼格と解している点だと指摘できます。紀野博士は「註」の中で「完全な智慧を女性的原理とみなして呼びかけたのであろう」と推測なさっておられます。「往ってしまった完全な智慧の女神様よ」と解した上での翻訳なのでしょうか…。
とまれ、どんなに頭をひねっても、ガテ-を呼格(呼びかけの形の言葉)と解したまま、まともな意味を成り立たせようとするのは無理、と知らねばなりません。
また、紀野博士は「完全な智慧の女神様よ」の意味で「往ける者よ」と「者よ」と訳しているのか、又は、釈尊を指して「完全な智慧の女神と一体となった全知者よ」と解して訳しているのか、又は、精進する修道者の個体の意味で「往ける者よ」と訳しているのでしょうか。この翻訳だけでは判別できません。
何れにしろ、「心経」は、「無~、無~」と「個体の自性」を否定するに留まらず、「個体の有相」までも否定して行く至高の経典です。よって、「者」という言葉を使って「個体性」を連想させてしまうのは、「締め」の大真言としては不適当です。
(空-七-百五十)
また、マックス・ミュラ-博士は、ガテ-が「行く」の過去受動分詞形ということで、これを「ゴ-ン(gone)」と英訳し、「行ってしまった=到達してしまった」という意味に解釈しました。イエズス・キリストの(祈るものは)「既に得たものと思いなさい」という言葉と合わせて、マントラで「到達した、到達した」と口に出していれば、やがては本当に到達するはず、という解釈だと言えましょう(言葉による先取り)。
しかし、「聖霊による内的な保証」(「神の許可」とも言えます)を未だ受けていない時点で、無理やり「既に得たものと思い込む」のは、正しい修行法ではありません。
日本人の中には、このミュラ-解釈の流れを引き継いで、「大真言」を「悟っちゃった、悟っちゃった、バンザ-イ」という意味だとか「わかっちゃった、わかっちゃった、仏様の御心が(有り難うございま~す)」という意味だと、真顔で説法する者まで居ます。
「悟った、悟った」と強弁していれば、最短・最速で悟りに到るとでも言うのでしょうか? 「神を知ってしまった」と常に強弁していれば、最短・最速で「神を本当に知るに到る」ことができるとでも言うのでしょうか。 ---そんなわけはありません。
(空-七-百五十一)
先程示した通り、心経の大真言は「聖なる渇仰心そのもの」を言語化したものです。
よって、「ガテ-」は「(無形・無相の)聖なる渇仰心の動きそれ自体」を表しています。
「聖なる渇仰心一乗の流れに乗った時」「この聖なる流れからはずれないで進んで行った時」「神ながらの道のまにまに行った時」---やがて人は遂にゴ-ル(大悟・救い・永遠の生命)に到るのです。(★二-十-二十)
そして、この「聖なる渇仰心」には、大別して「二種類の動き」が有ります。
一つは---<「上求菩提」の動き>---即ち、個人の悟り(救い)を求める動き。
一つは---<「下化衆生」の動き>---即ち、衆生の悟り(救い)を願う動き。つまり、衆生のために主の恵みを引き降ろそうと、主に祈ってやまない動きです。(=天恵の雨乞いをする動き)
このような「上下二方向の聖なる渇仰心」を「心経の大真言」は「一語のガテ-」で表しています。
では、同様に「上下二方向の神聖渇仰心」を表すような「一語」の日本語は有るでしょうか?
それが有るのです!
「ガテ-」よりも更にピッタリの言葉が、奇蹟的に存在するのです!
それが---<ぐほう (求法/弘法)>---という言葉です。
「ぐほう」はまさしく「神聖渇仰心の動き」を表す言葉であり、奇蹟的に上下二方向の動きをも表す掛詞になっています!
以上により、心経の大真言は、「ガテ-」に「ぐ法」を代入して---
<求法 弘法 パ-ラぐ法 パ-ラサンぐ法 ボ-ディ スヴァ-ハ->
と、途中まで翻訳できました。
そして、「パ-ラ」と「サン」の意味は先に示した通り(空-七-百四十七)、二つの言葉とも、「ぐ法」の「完遂を示す強調語」と言えます。
とすると、大真言の文脈からして---<パ-ラは「完遂」、サンは「全」>---という訳語が出て来ます。
<求法 弘法 完遂ぐ法 完遂全ぐ法 ボ-ディ スヴァ-ハ->
ただ、「完遂」は日常ではあまり使用しない言葉である一方、「初志貫徹」という熟語は時に応じてよく使われる身近なものなので、「ぐ法の志(発心)を貫徹する」という意味で、「貫徹」の語を当てるのが言霊としては適当だと言えるでしょう。
こうして---<求法 弘法 貫徹ぐ法 貫徹全ぐ法 ボ-ディ スヴァ-ハ->---と、途中まで翻訳でき、全訳まであと一歩となりました。
尚、日本語の語順からすると「ぐ法貫徹」の方が自然ですが、原文の語順を残す側面から「貫徹ぐ法」と訳出しています。「貫徹ぐ法」でもすぐに慣れるでしょう。
「求法は貫徹すべきもの」という真理が、この四字に強烈に表現されています。その上、「貫徹全ぐ法」と「全」で更に強調され、「必ず全部成し遂げる」という鉄の意志を含む、不撓不屈、不退転の姿勢を表す猛烈な日本語の言霊が、ここに並んだことになります。
(空-七-百五十二)
では、残る「ボ-ディ スヴァ-ハ-」は、どのように訳出すれば良いでしょうか?
「悟りよ 幸あれ」という訳は、ボ-ディを呼格(呼びかけの言葉)と解する説です。
インドには「神の名を呼んだ後にスヴァ-ハ-と付ける慣習」が見られるので、これを考慮した説と言えます。しかし、「スヴァ-ハ-」は元々「祝福あれ・恩寵あれ・祝福して下さい・恩寵を与えて下さい」という意味です。だからこそ、まず神の名を呼び、名前を呼んだその神様からの恵みを求めて「スヴァ-ハ-」と言うのです。
ところが、大真言の「ボ-ディ」は神ではないし、恩寵を与える主体でもありません!
従って、正しくは--「ボ-ディの(=という)恩寵あれ」とか「悟りという祝福あれ」という意味だと解すべきです。まことに、最高に吉祥なる「悟りという恩寵」を祈祷・願求する言葉が「ボ-ディ スヴァ-ハ-」なのです。
従って、和訳の場合は、端的に略して「悟りあれ!」とか「悟りありませ」が適切だと言えます。
但し、ここで---「ボ-ディ」は単純に「悟り」で良いのか、問題にすべきです。
前述の通り、真言は「特定の神聖思念喚起の器」です。けれど「悟り」という日本語は俗的な用法が多すぎて、手垢に塗れ、「ボ-ディ」が指し示す「本来の意味(特定の、神聖で具体的な思念)」を喚起する力が弱過ぎて、大真言の言霊としては不適当だと言えます。
そもそも、「ボ-ディ」は動詞「目覚める」の名詞形なので、「覚醒」とか「正覚」とか「本覚」とか「真覚」と訳した方が原義のニュアンスに近いと言えます。しかし、「覚醒あれ」と訳しても「正覚あれ」と訳しても「本覚あれ」「真覚あれ」と訳しても、全真言の母体としての大真言の言霊としては、まだまだ弱いと言えます。
(空-七-百五十三)
では、どう訳したら良いでしょうか。
第一案としては、思い切って「ボ-ディ」を「超脱」と訳して、「ボ-ディ スヴァ-ハ-」で「超脱あれ!」と訳す策が有ります。「ボ-ディ」は「悟り」の意味ですが、「気付き」のような浅い意味ではなく、ここでは「大悟」即ち「ニルヴィカルパ・サマディ」(相対界を超脱した無区別・空相のサマディ)への入定を意味する言葉です。(前篇第五章)
「超脱の結果が悟り」だとも「悟入の結果が超脱」だとも言えます。
仏教には「諸悪莫作」(諸悪をなすなかれ)という教えが有りますが、この諸悪を超脱した境地こそが「悟り」です。従って、「諸悪からの超脱あれ」という聖なる渇仰心の叫びと祈りは、これだけでかなり強い効果を発揮します。
(空-七-百五十四)
第二の案としては、思い切って「ボ-ディ」を「神覚」と訳して、「ボ-ディ スヴァ-ハ-」で「神覚あれ!」と訳す策が有ります。先に、「ボ-ディ スヴァ-ハ-」は「覚醒あれ」とか「正覚あれ」とか「本覚あれ」とか「真覚あれ」と訳し得るという事を述べましたが、これでも訳語としては正しいので、この訳語で祈っても間違いではないのですが、この言霊では多くの人はピンと来ない(意味を明確に想起できないまま祈る事態になってしまう)という難点が有ります。
そこで、この難点を補うべく、思い切って「ボ-ディ」の訳語として「神覚」という新語を造って当てる手が有ります。「悟り」とは「本覚=本地の叡智に覚醒すること」であり、この「本地」とは「自性有る存在」(本書では仮に大日空王主と呼んでいます)の「本居」(空-五-二一)のことであることは既に詳説した通りです。
つまり、建前上は、仏教では「神」という言葉を使うのを忌避しますが、実質的には「ボ-ディ」は「神の覚醒意識」を意味しています。従って、「神覚あれ」とすると、その意味が実に明確になります。また、音韻としては「神格あれ」にも聞こえ、「人格から神格へのステップ・アップ」を希求する言霊にもなります。そして当然、こうした崇高な「神格」を希求する表明は「諸悪を超脱した高貴な品性」をも切望している事の表明にも通じます。
従って、「神覚あれ」という言葉には、「正覚・本覚の希求」とか「諸悪超脱の祈念」とか「仏に成る(成仏すること」等々---こうした仏教の最終目的が奇蹟的に集約されている一文、と言えるのです。
確かに、第一案の「超脱あれ」にもかなり法力が有りますが、「超脱あれ」とだけ祈ると、やがて「何からの超脱か」を忘れて「漫然と超脱あれ」と祈る事態を招いてこの祈りの法力が失われてしまいます。これを避けるために、「諸悪からの超脱あれ」といつも祈れば良いのですが、これでは大真言の簡潔な言葉としては、長過ぎます。
---以上の点から、仏教が示す「ゴ-ル」を最も短い言葉で表現するとしたなら、「神覚」の語がふさわしいでしょう。
「神覚あれ」---こう訳すと、「全真言の母体としての大真言」にふさわしい強烈な言霊が立ち現れます。人生では実に様々な苦難・苦厄が待ち受けていますが、それらに遭遇しつつもそれを乗り越えて行く道のりは、すべて「神覚を得るためのもの」なのだと、スト-ンと納得できるでしょう。そして、修行の道心と勇気と力が湧いて来るでしょう。
(空-七-百五十五)
かくして、「翻訳不可能」と言われていた心経の大真言の日本語訳が完成しました。
<求法 弘法 貫徹ぐ法 貫徹全ぐ法 神覚あれ!>
これは、まことにまことに凄まじい日本語マントラです。毎日心を込めてこれを唱えていれば、ほどなくして、このマントラの凄まじい力を実感できるはずです。
尚、「ガテ-」は処格であり、ここは「~した時に」の意味なので「時」を入れて---<求法 弘法 貫徹ぐ法 貫徹全ぐ法時 神覚あれ!> でも良いでしょう。
(空-七-百五十六)
ここで、日本語訳の大真言」を唱えるに当たっての、「深い奥義」を一つ、明らかにしましょう。
「自性を備えた存在」(本書では大日空王主と呼んでいます)である偉大な御方は、「生きとし生けるものの、段階的な成長」を願っておられます。大日空王主は「成長物語」という「一つの壮大なドラマ」を演じるこめに、衆生を存在させ、衆生に化(な)っておられるからです。
そうだとしたならば、「神覚」を求める高貴な志を抱いて「求法の旅」に出た場合、主がこの動きに反対したり、この動きバック・アップしない、という事があるでしょうか。いいえ、そんな事はあり得ません。
そればかりか、「真摯・真剣・熱心な、神覚の求法行為」---これは「主の御意志、主の御心」にジャスト・フィットした「動き」なのです。 いえ、そればかりではありません。
「神覚・求法の動き」こそ「荘厳なる無為」の働きであり、「無形の神身」そのものでさえあるのです。(前篇第二章第二節参照)
この奥義が分かれば、「熱心な求法時」に、主の「大法力」が働いて、その修行者が摩訶不思議な霊力で「守護される」という事も「理の当然」と分かるでしょう。
これが分かると、「正しい求法時には絶対、必ず、神のご加護が有る」と、神に絶対的な信を置く事ができるでしょう。
だからこそ---「求法 弘法 貫徹ぐ法 貫徹全ぐ法 神覚あれ!」と大真言を唱えて精進する行者は、主の大法力の御加護で、しっかり守られるのです。
★ 但し、(求法ではなく)「弘法」に関しては、次の点、注意を要します。
神はモンキ-(猿)をすぐに解脱させ神覚を得させようとは、願ってはおられません。長い年月を経て、徐々に段階的な成長の旅、輪廻転生の旅を用意なさっておられます。
物事には踏むべき順番というものが有ります。この点を忘れて、「流れ」に反する「無理・無茶な弘法行為」をする事は、「神のダルマ」「神の決め事とご計画と手順」を無視して踏みにじることになるので、そういう事は心して避けなければなりません。ゴリ押しの弘法行為や折伏(しゃくぶく)行為は<無知なるエゴ(有為)の働き>でしかありません。
(空-七-百五十七)
(51) 般若波羅蜜多心経
漢訳版の心経を締め括る言葉です。漢訳版では、表題と同じものが最後にも来ています。一方、梵語原文では「イティ プラジュニャ-・パ-ラミタ-・フリダヤム・サマ-プタム」となっています。「イティ」は「ここに」の意味。
「サマ-プタム」は「ア-パ(★ )=終わる・終える」に接頭辞「サム」を付けた動詞の過去受動分詞形です。直訳すると「完全に終結せられた」という意味です。
日本語の慣用句では「ここに~を終える」という形なので、「真髄和訳」では日本的な表現を採用しています。
「経」の意味の「ス-トラ」は省略されています。
「フリダヤム」は二義の「掛詞」になっています。「語義解析4」空-七-三一)
---以上で、「ステップ4 全単語を正しく理解する」を終了します。
←←前ページに行く 次ページに行く→→このページの最終更新日 2005/5/8
著作権について
■ ■ ■ ■ Copyright (c) 2003~2012 Aomi Ryu All Rights Reserved ■ ■ ■ ■